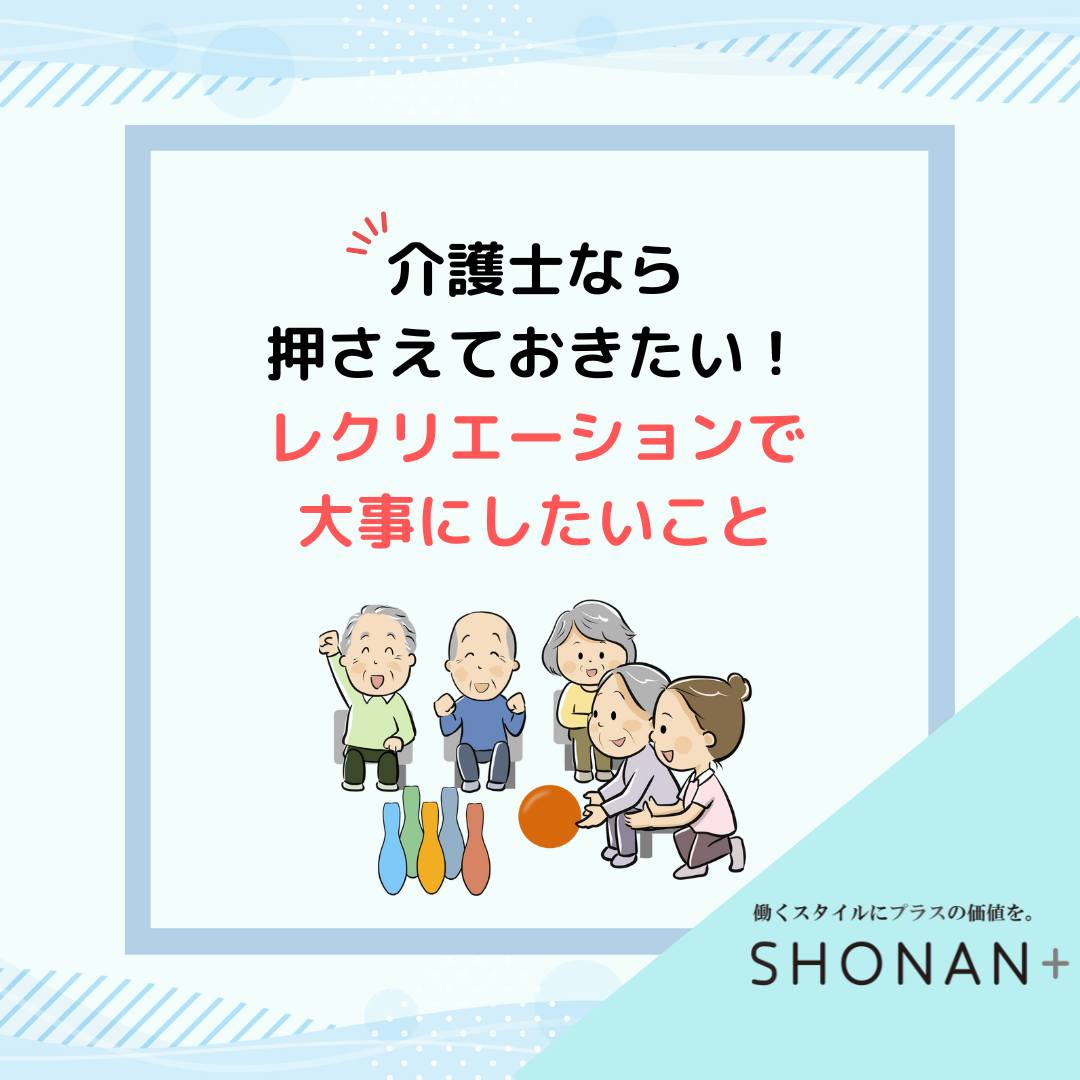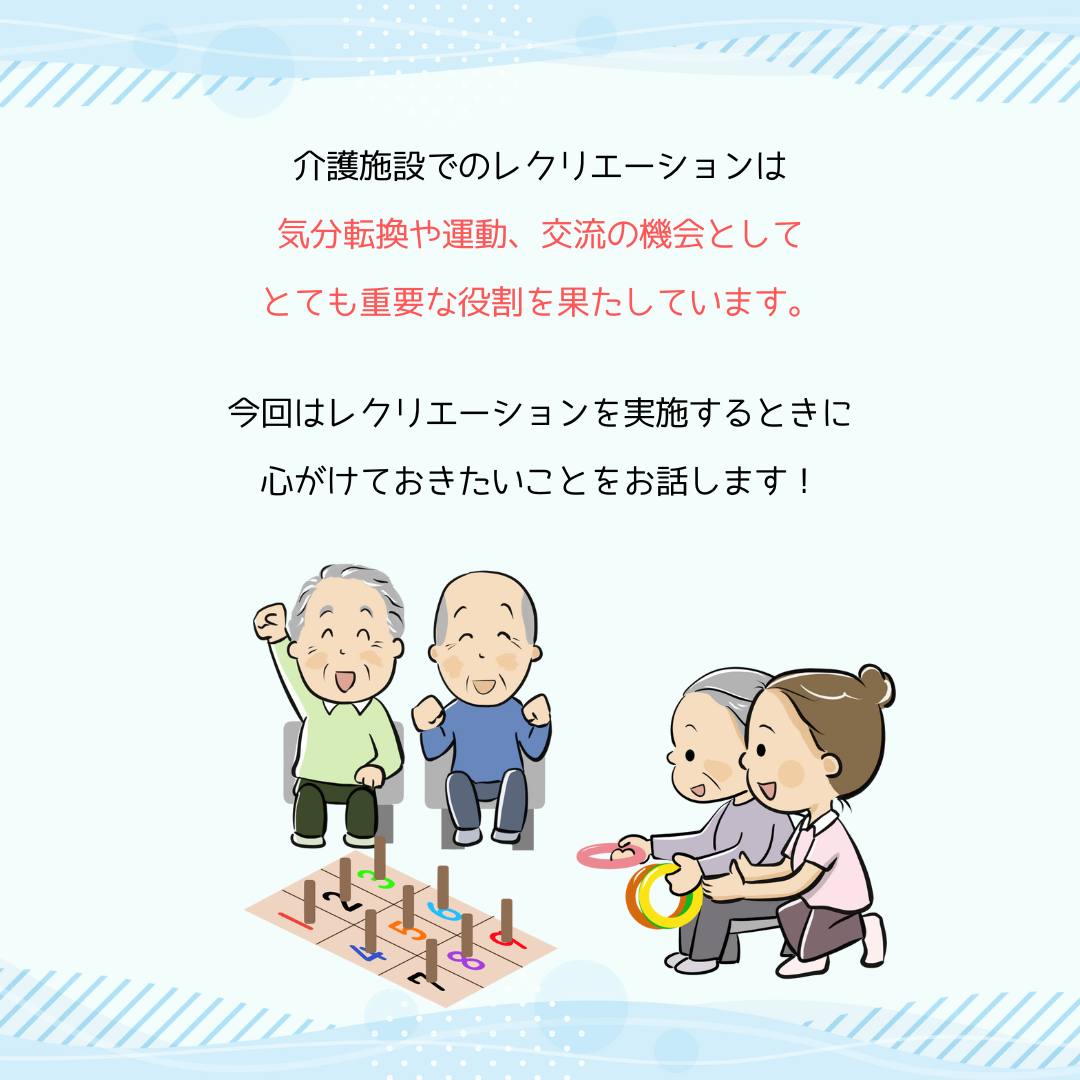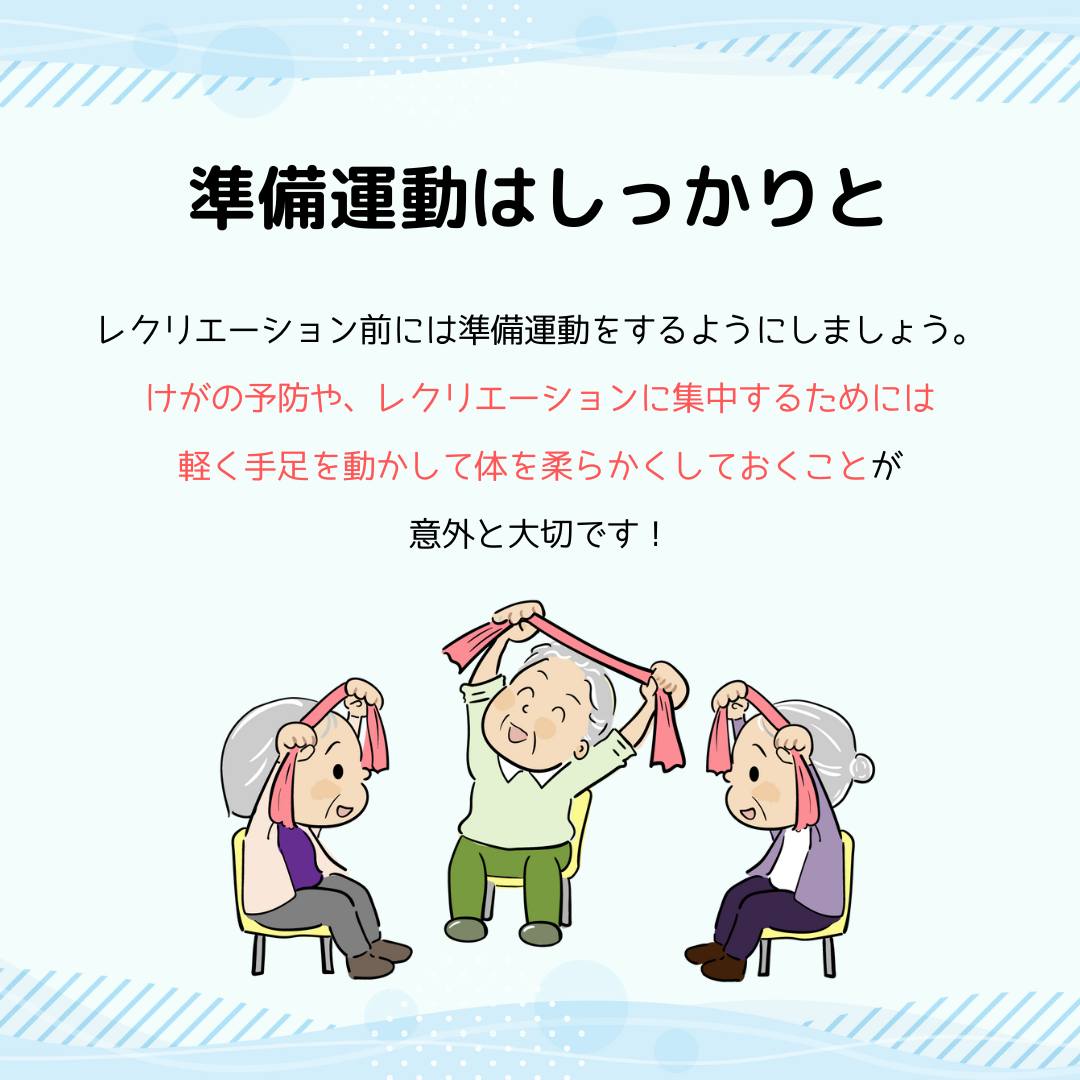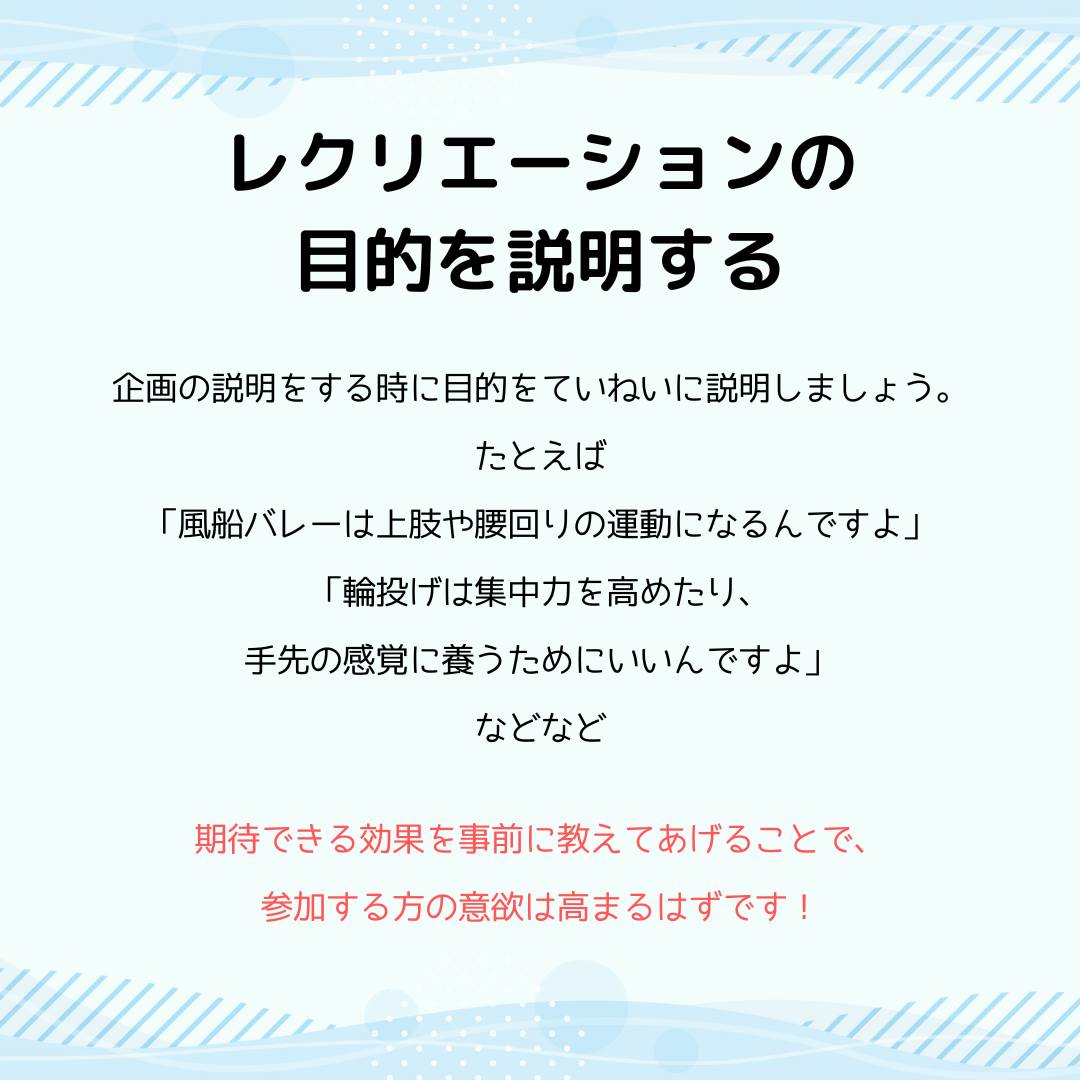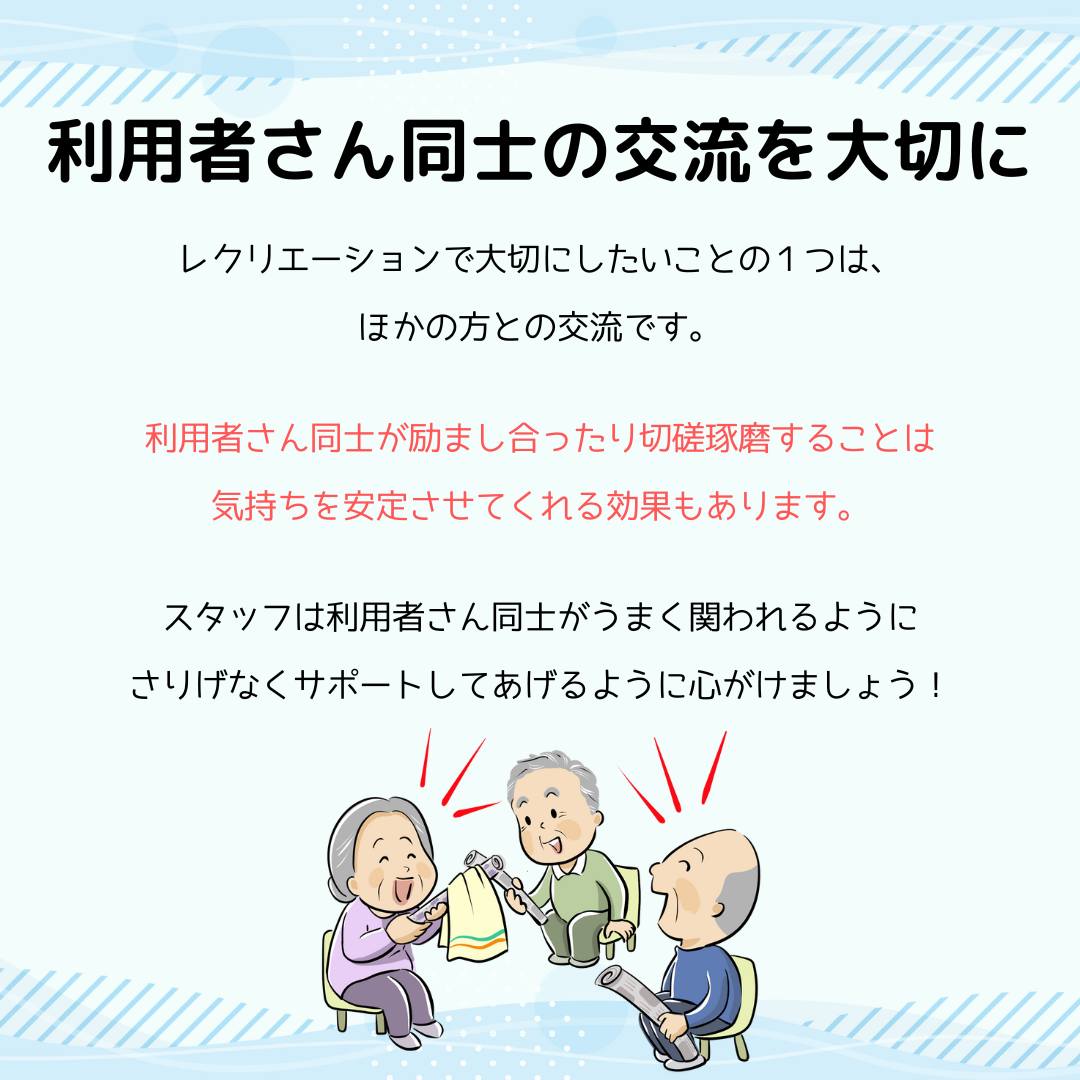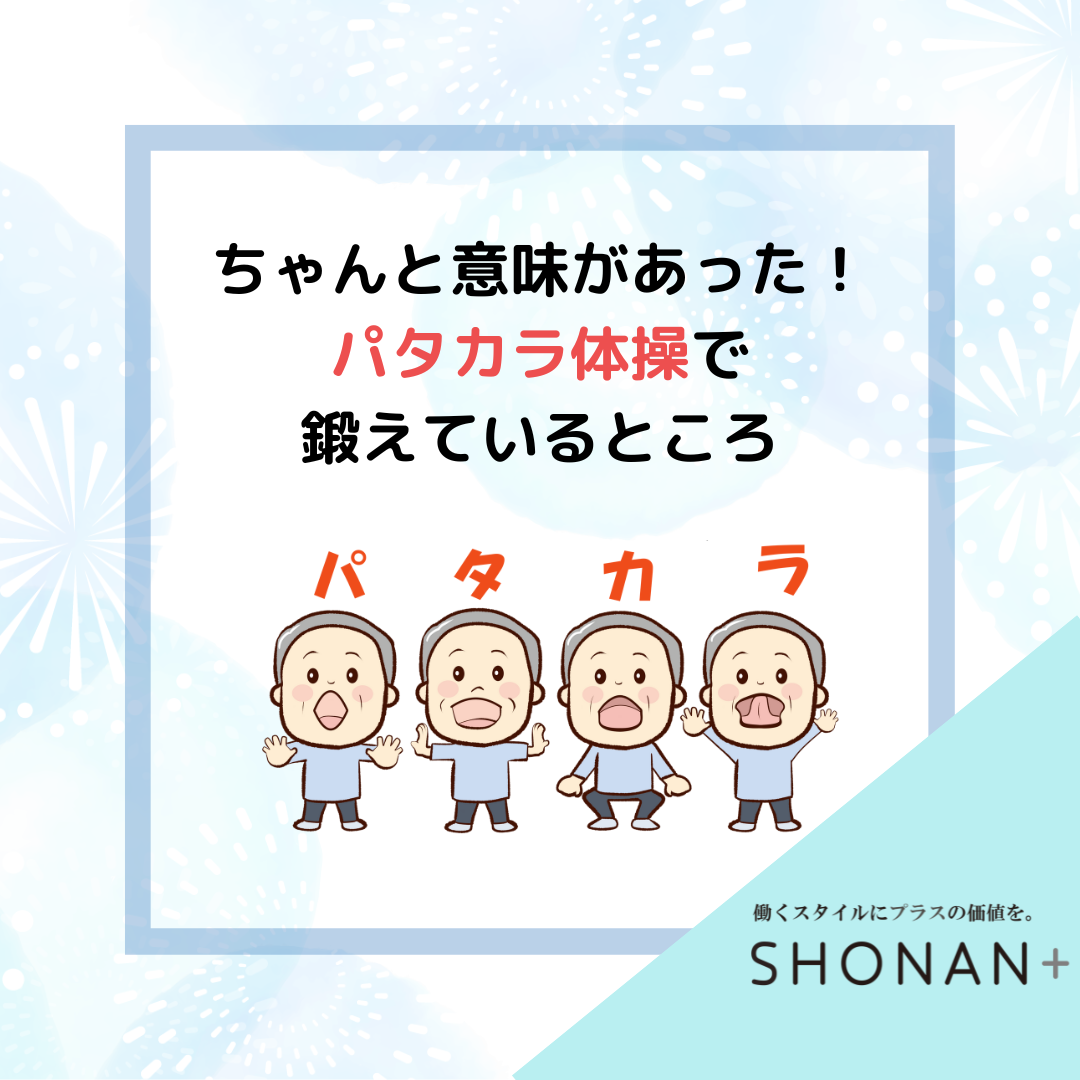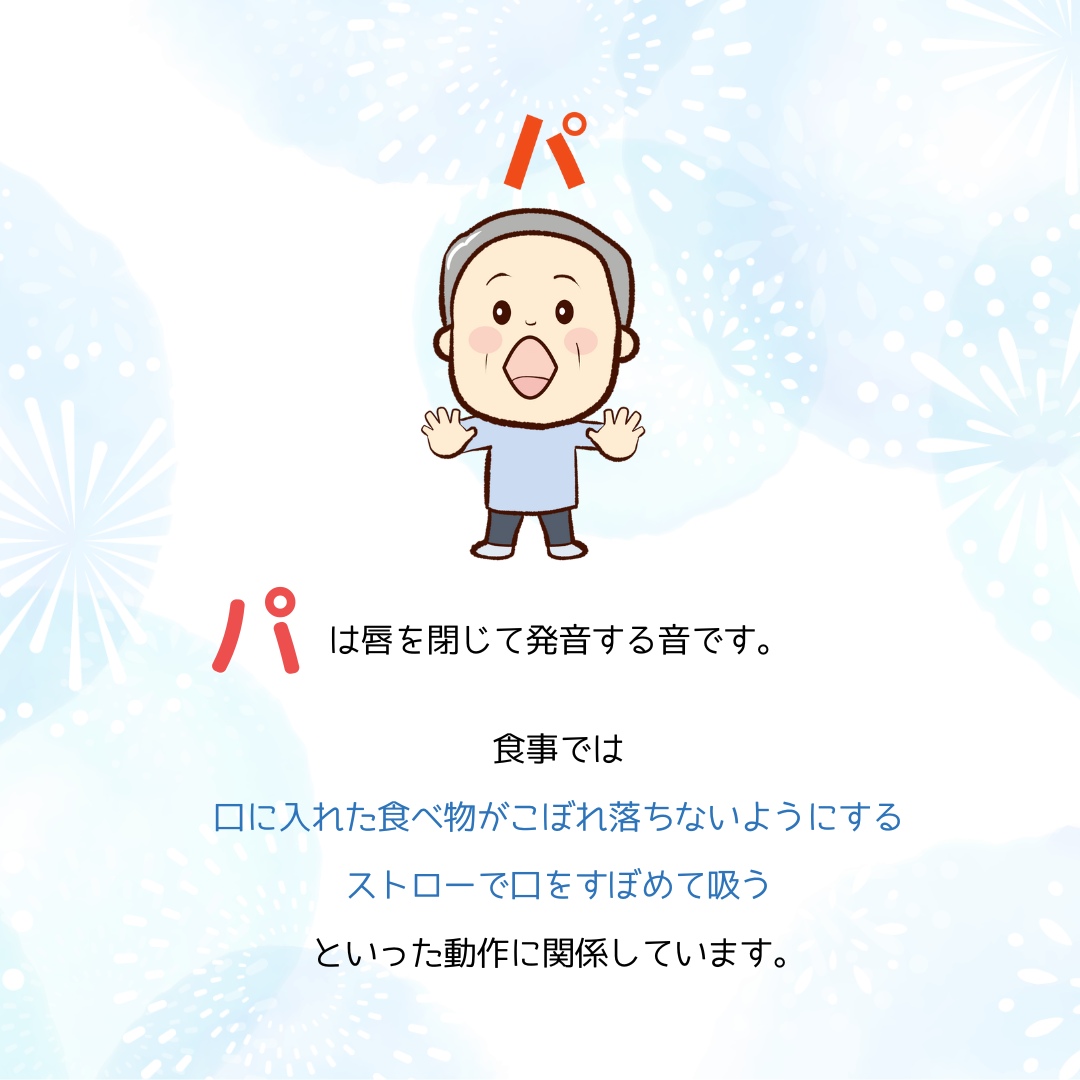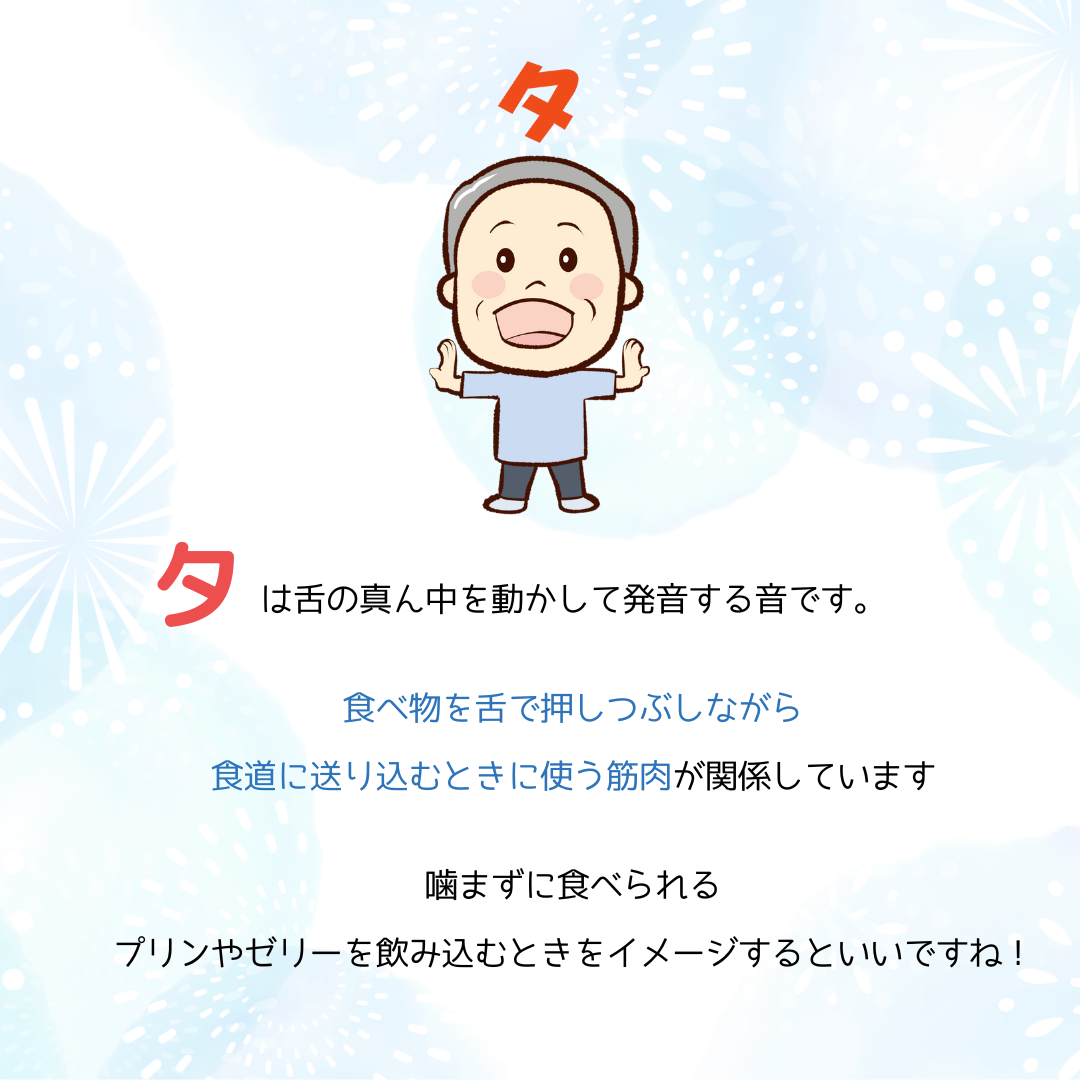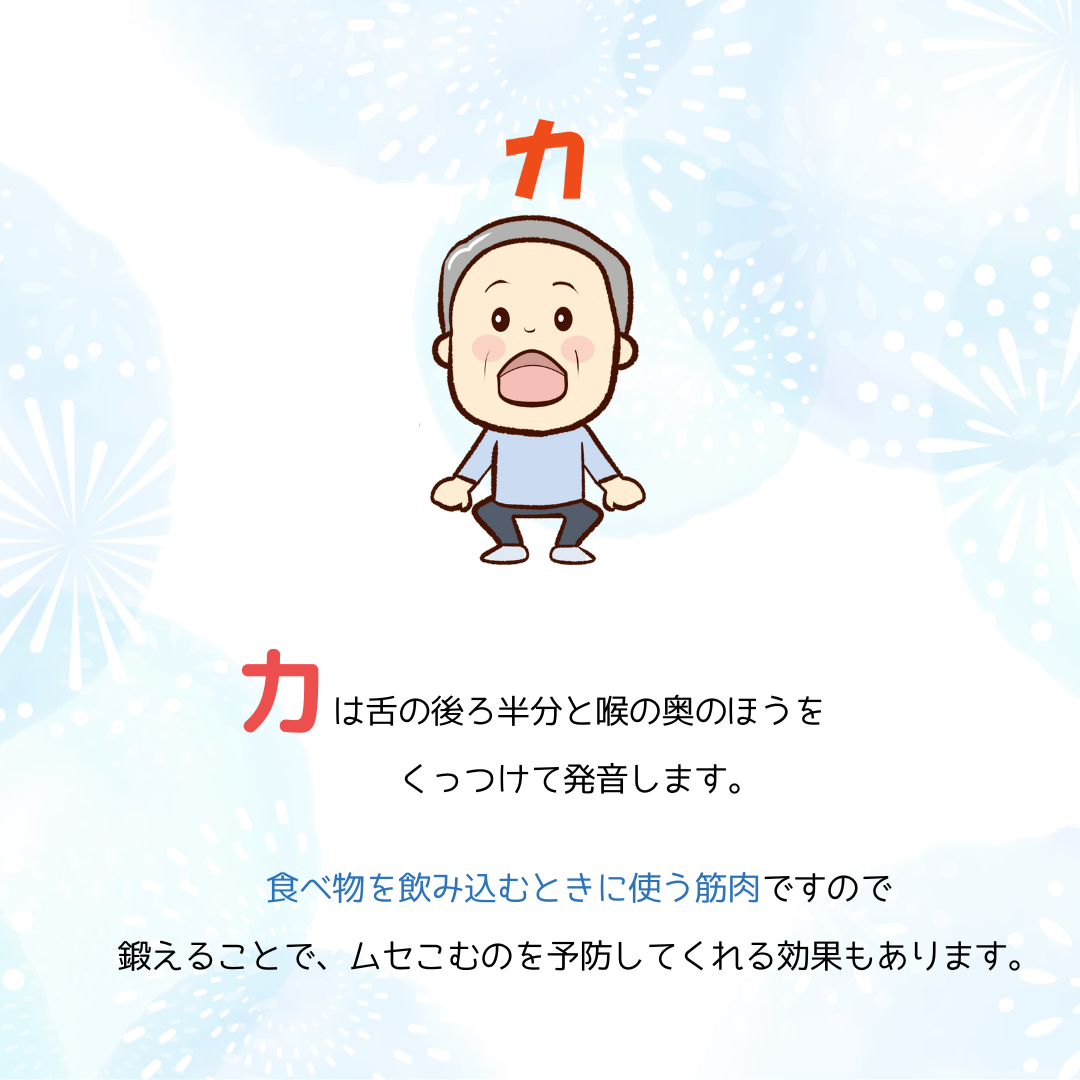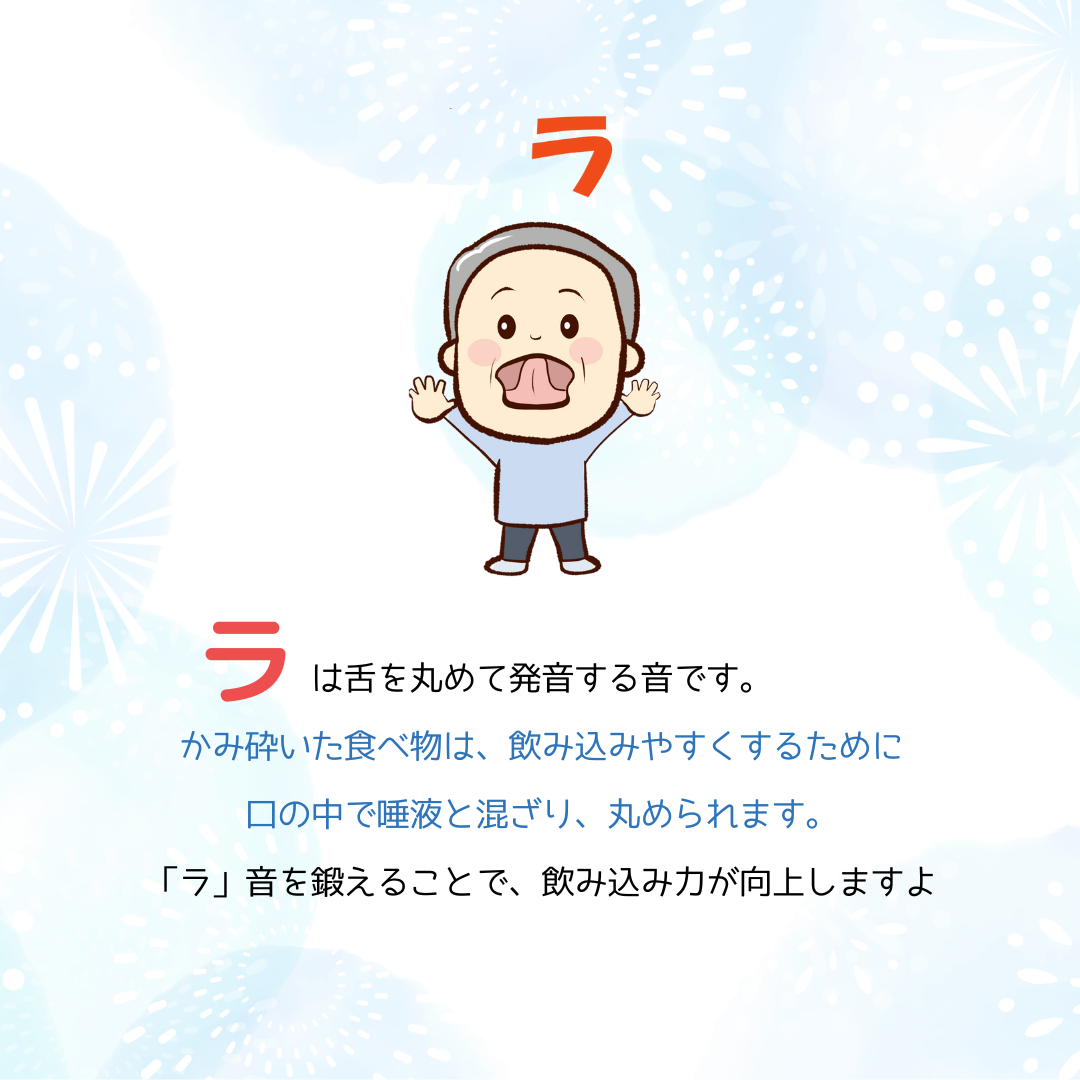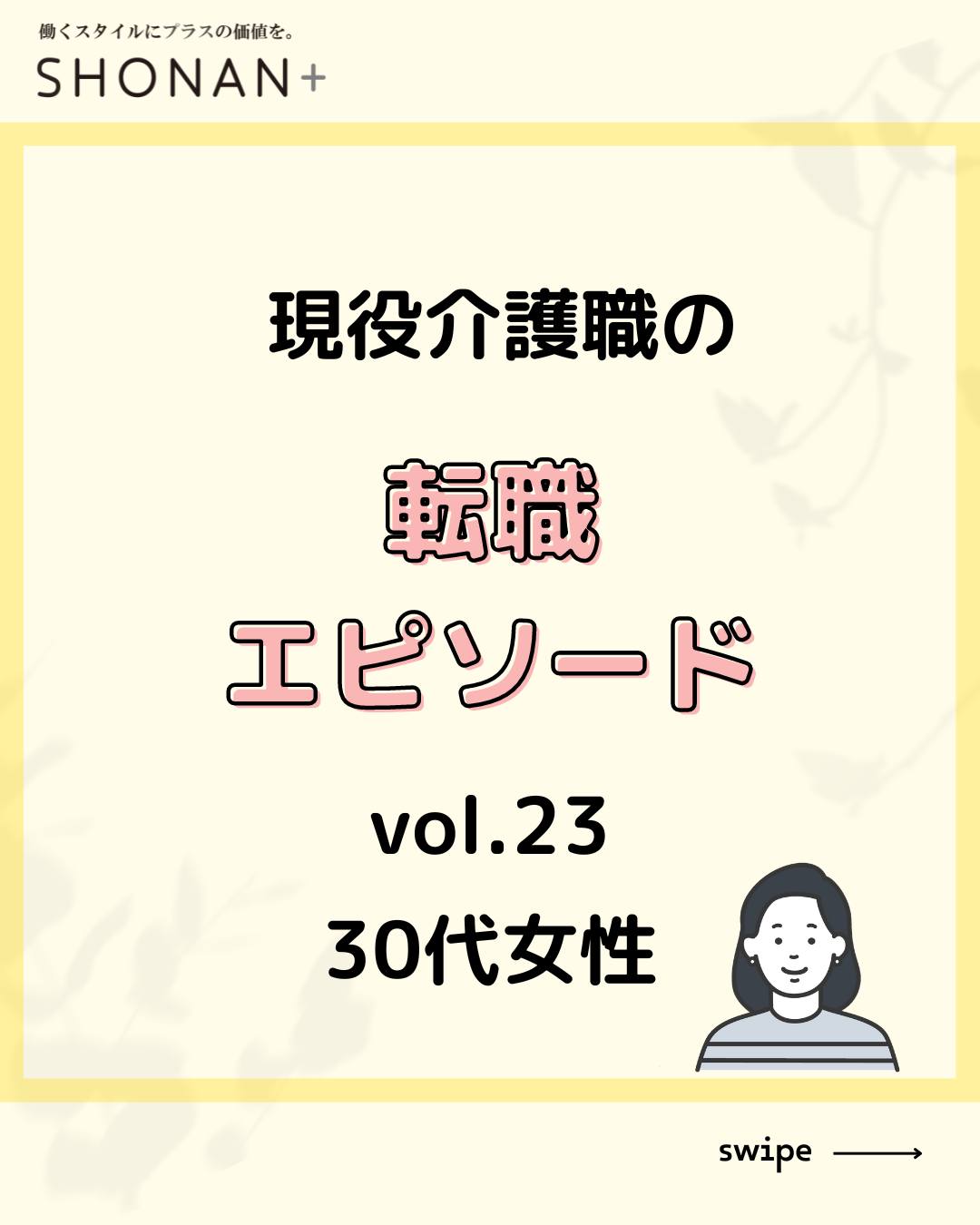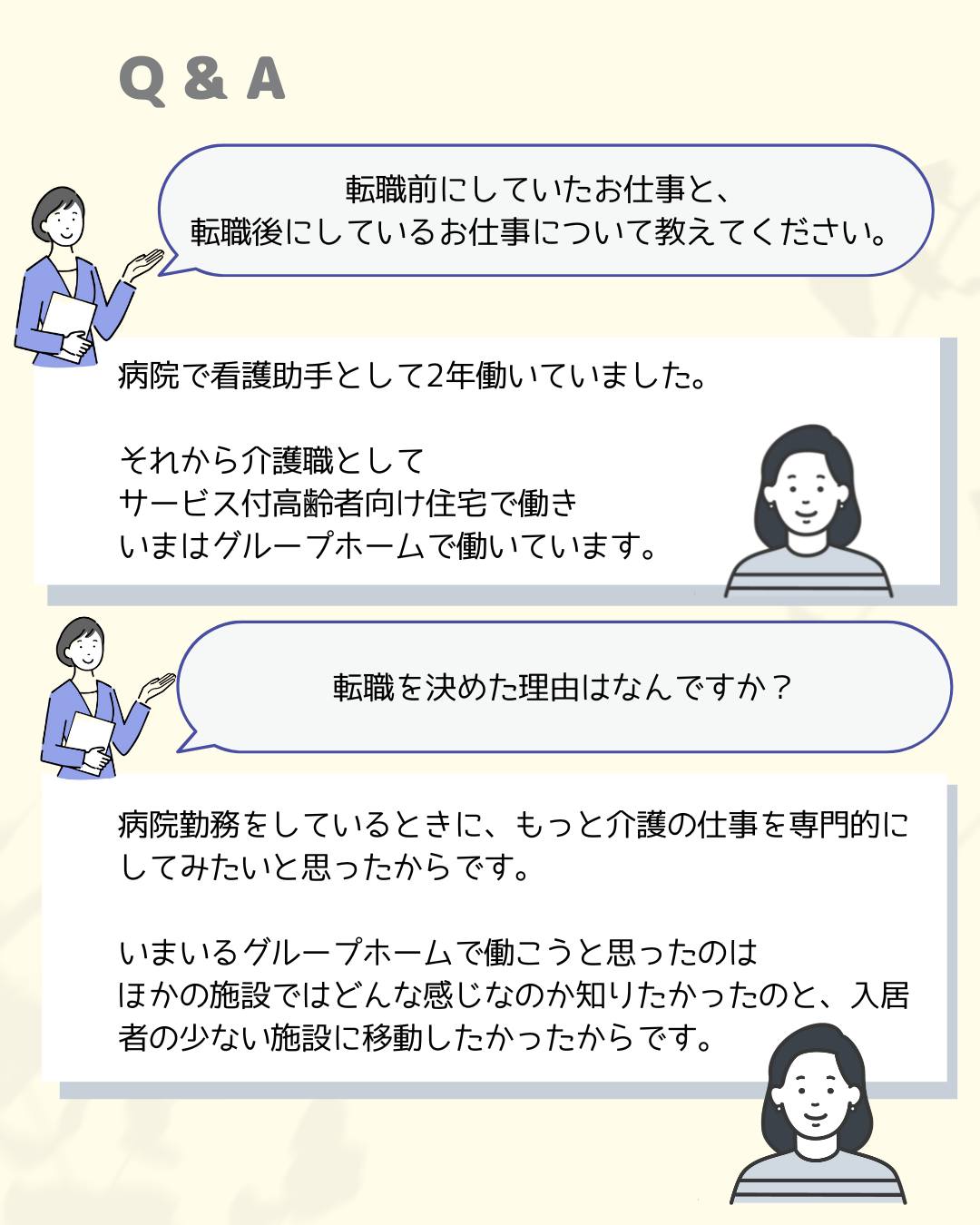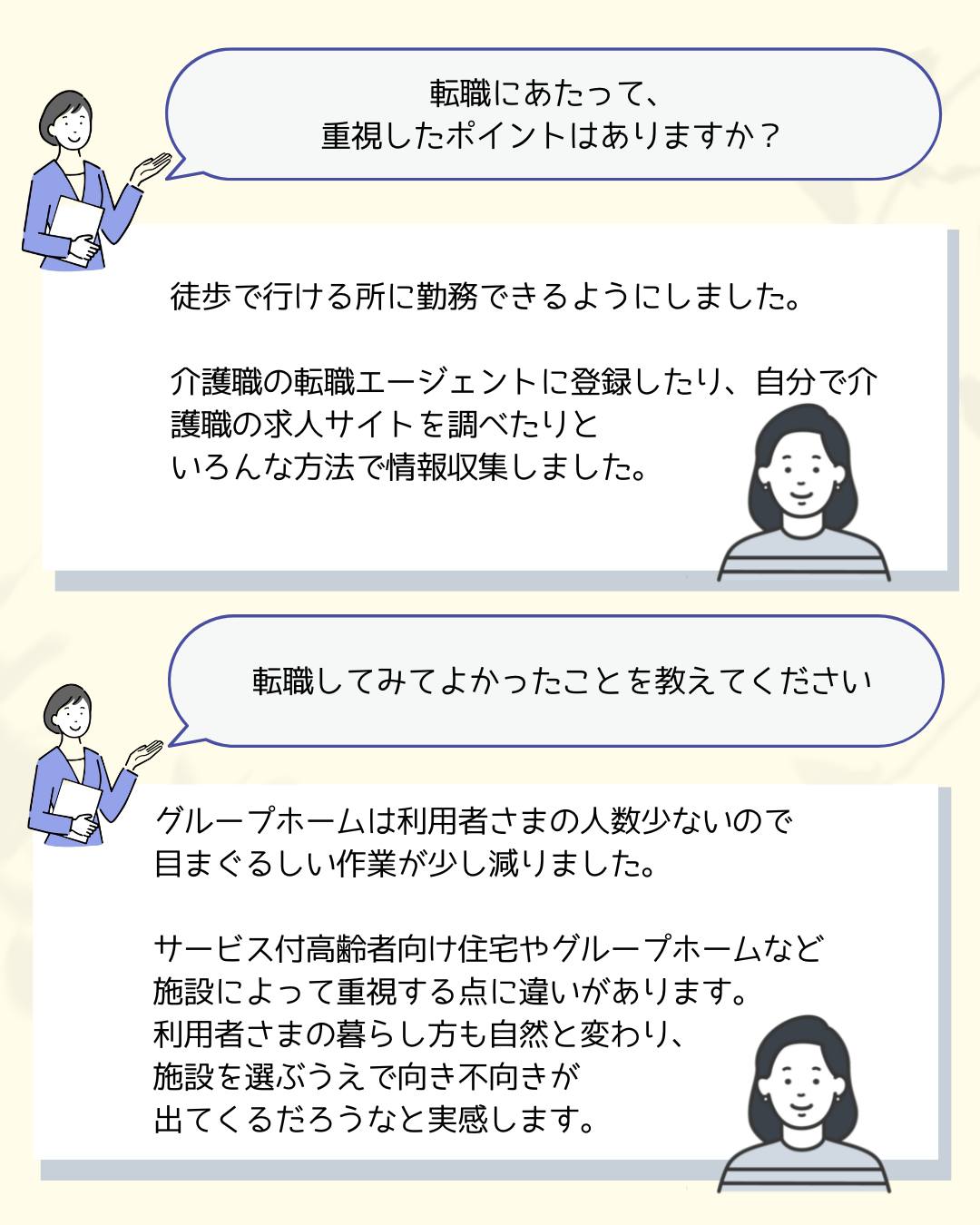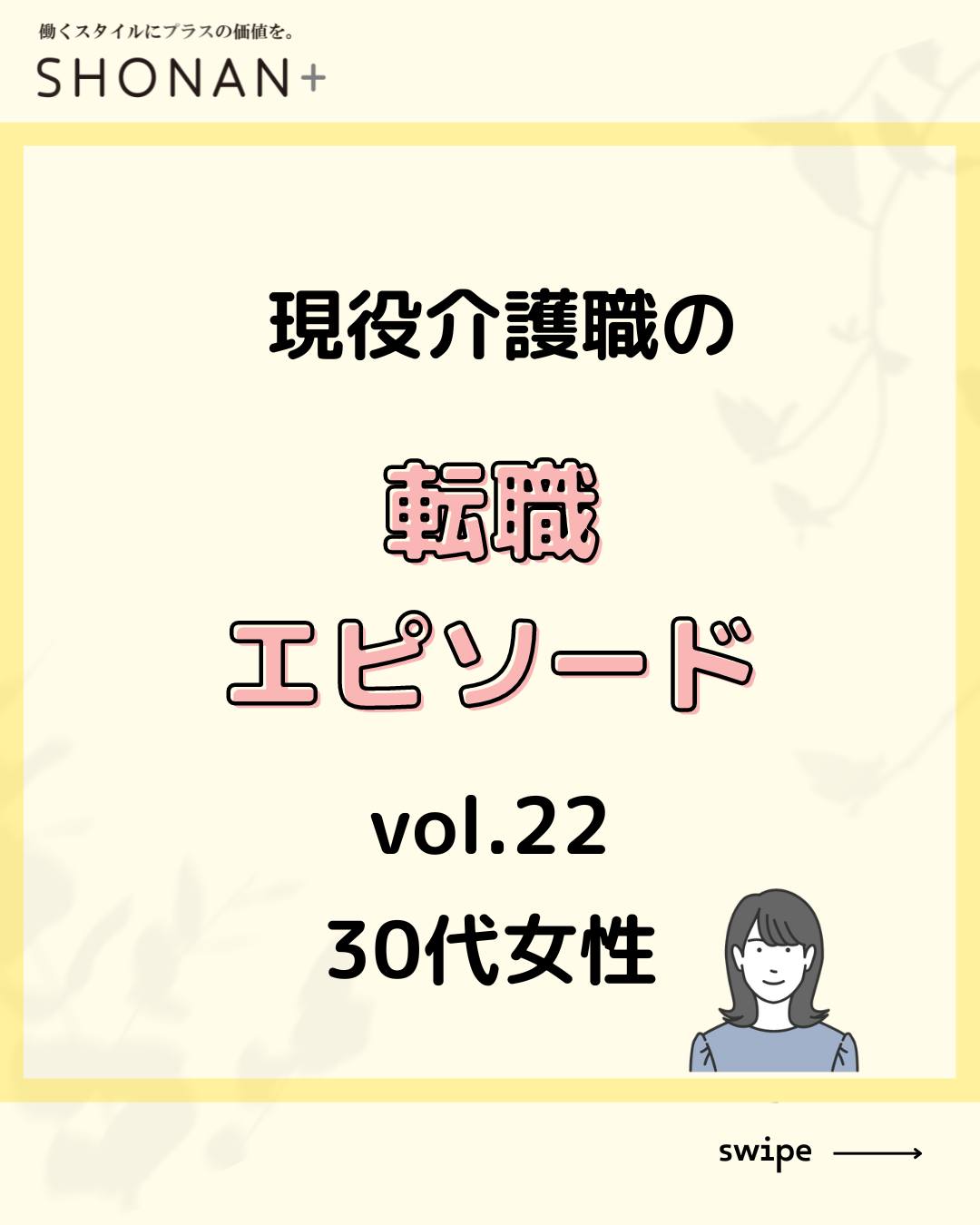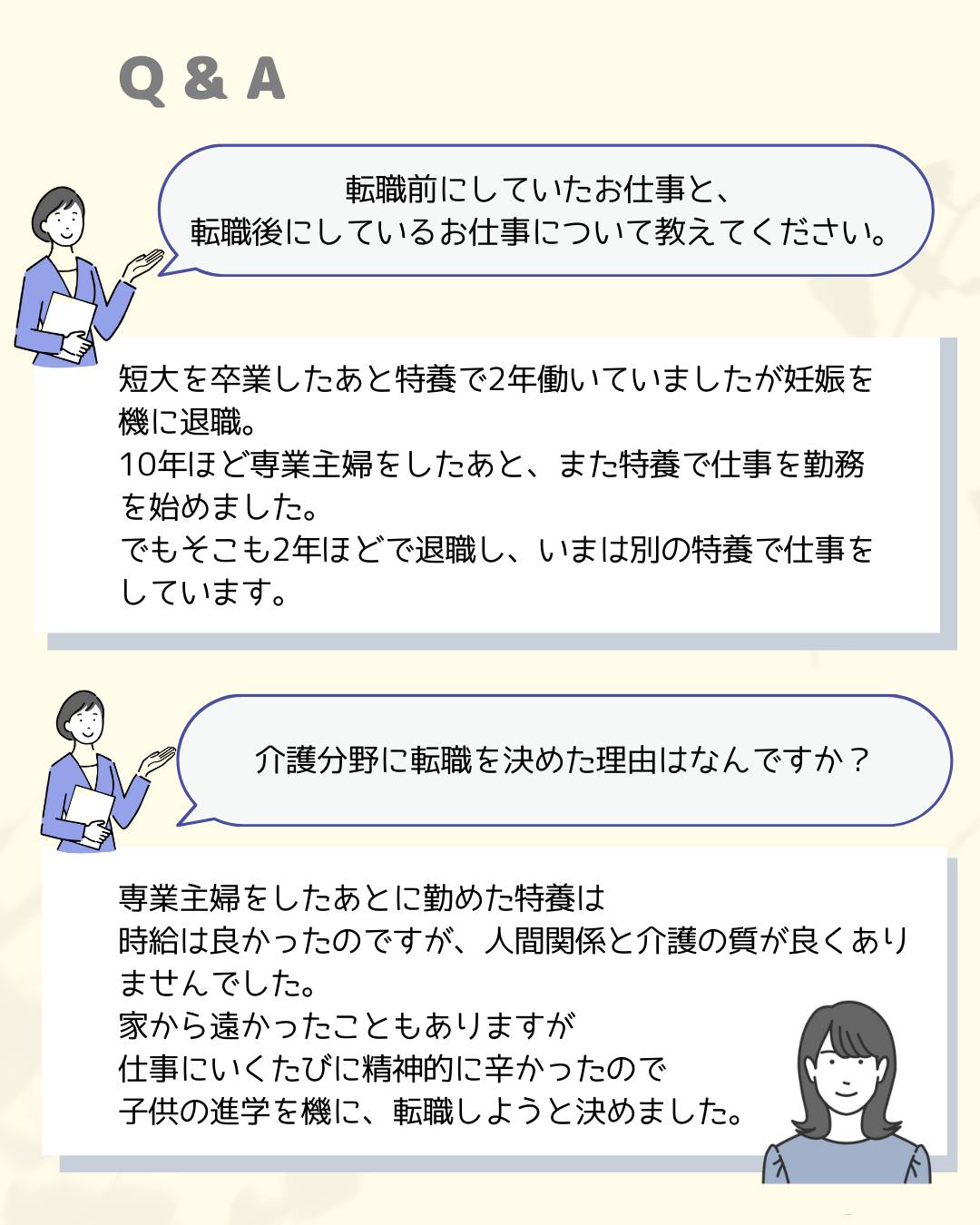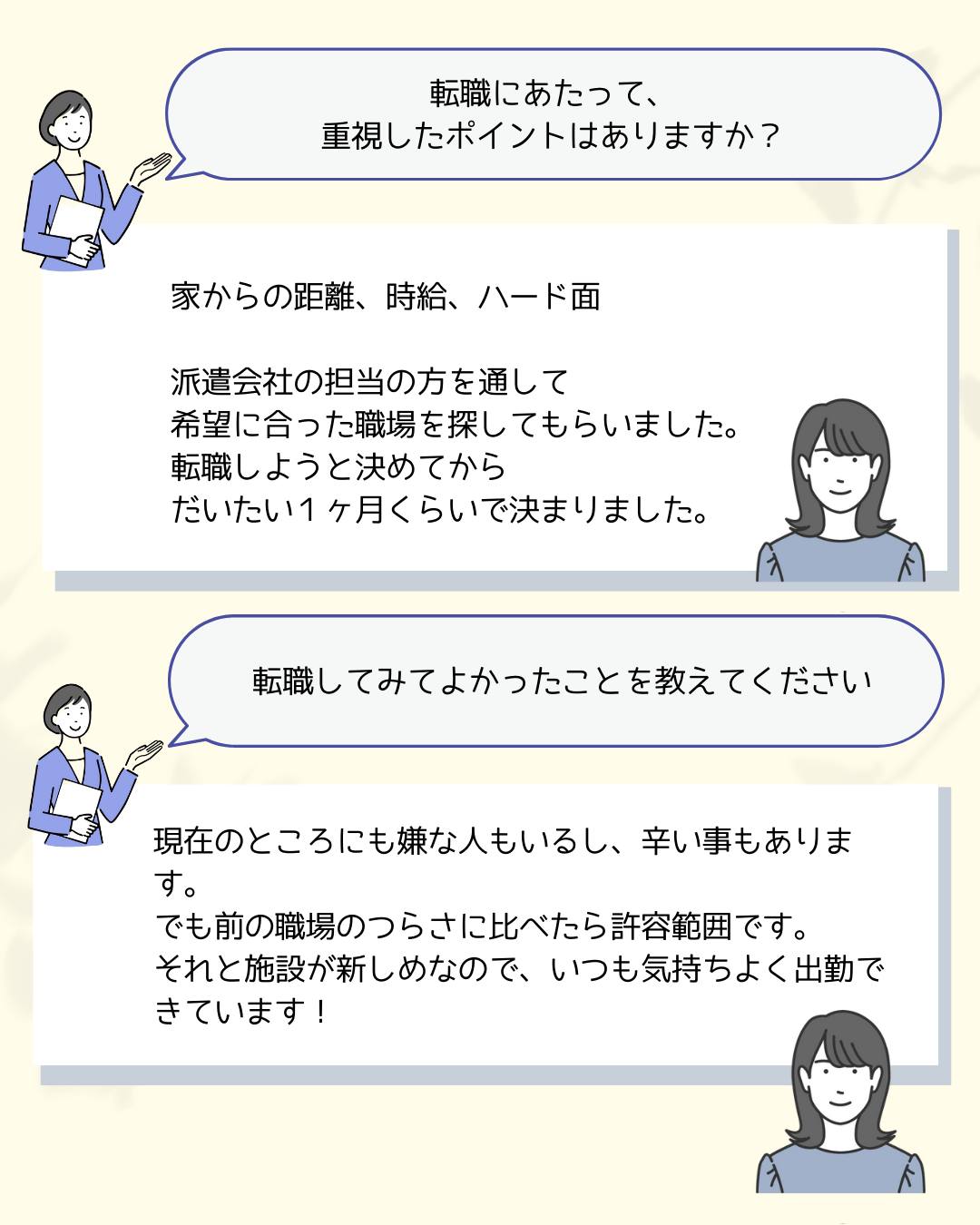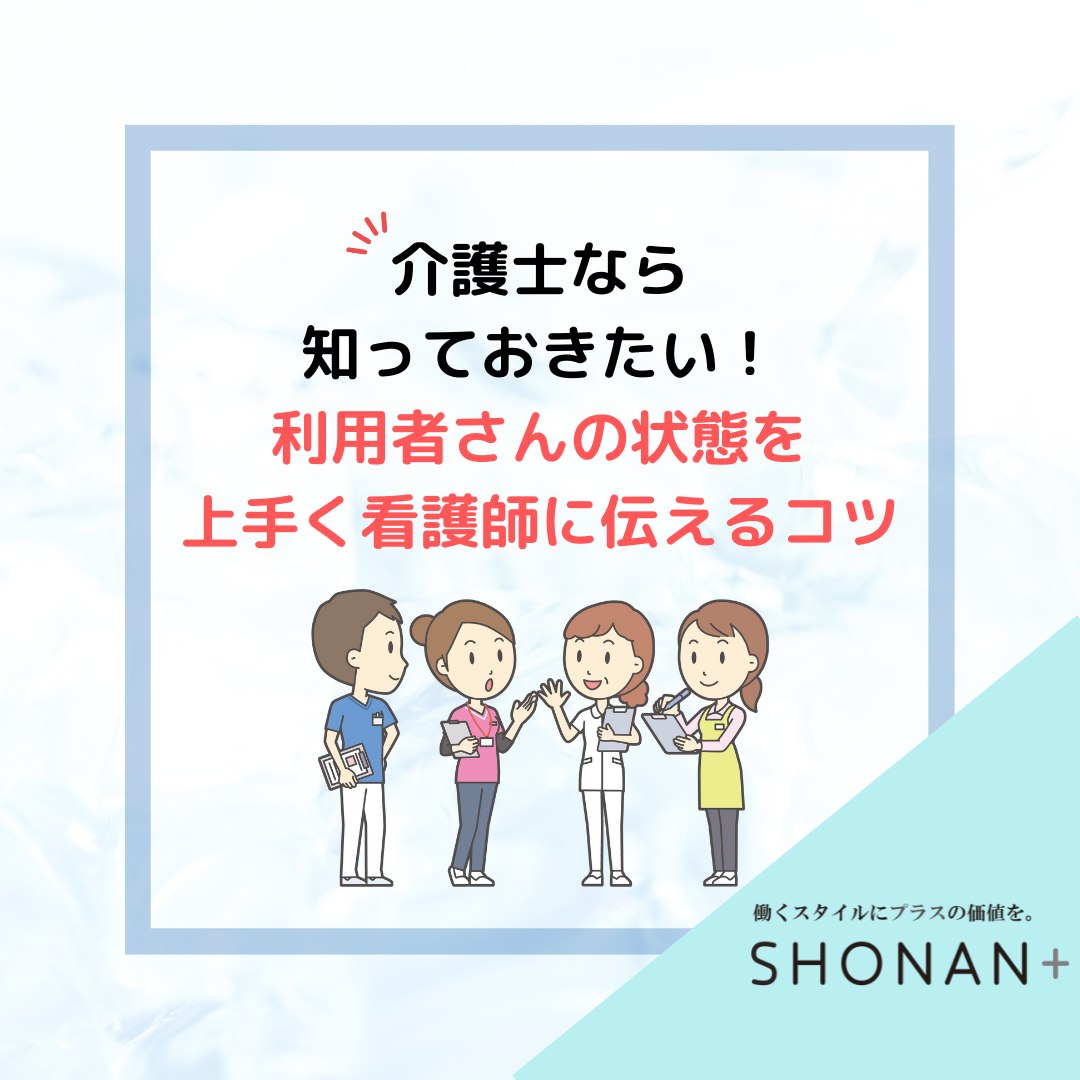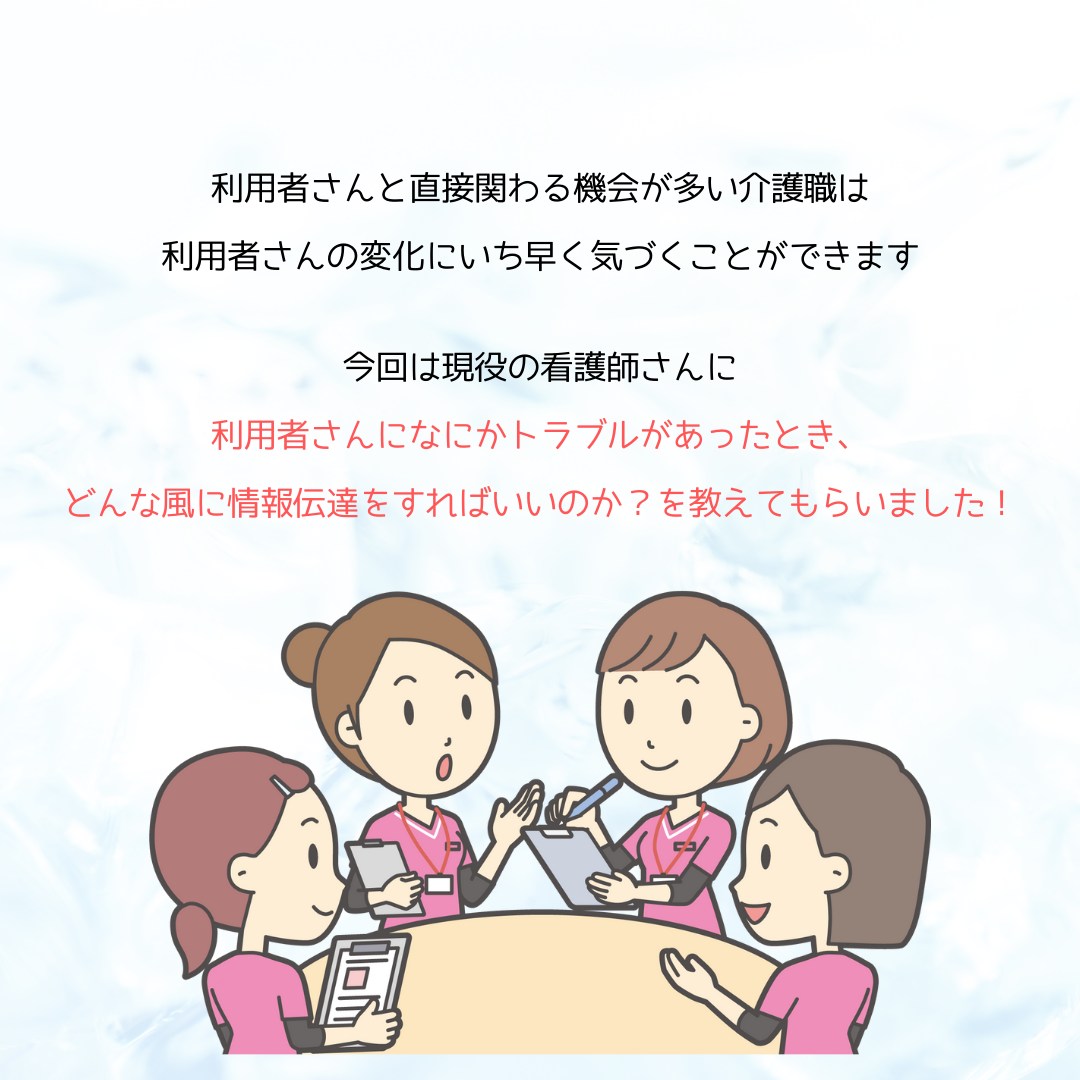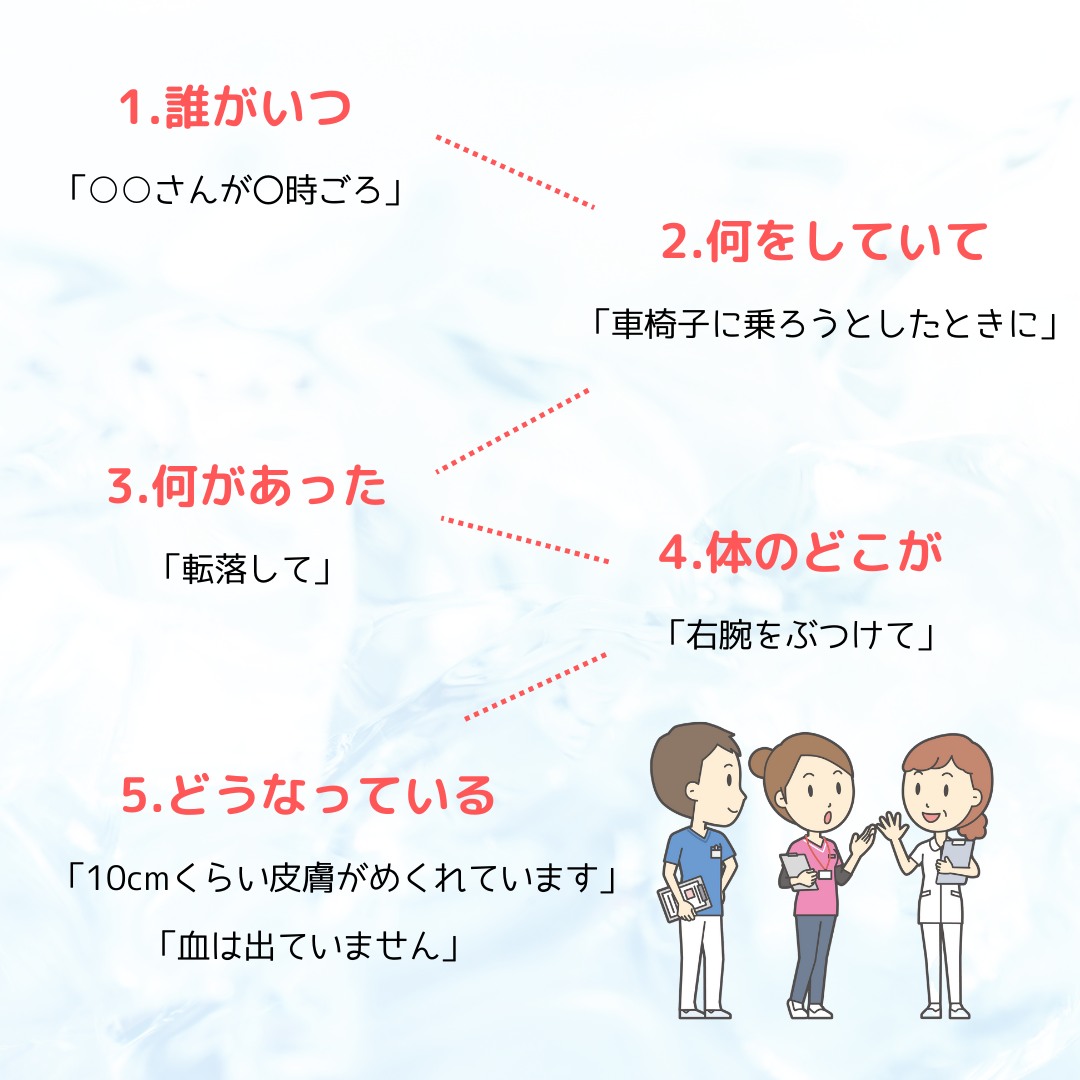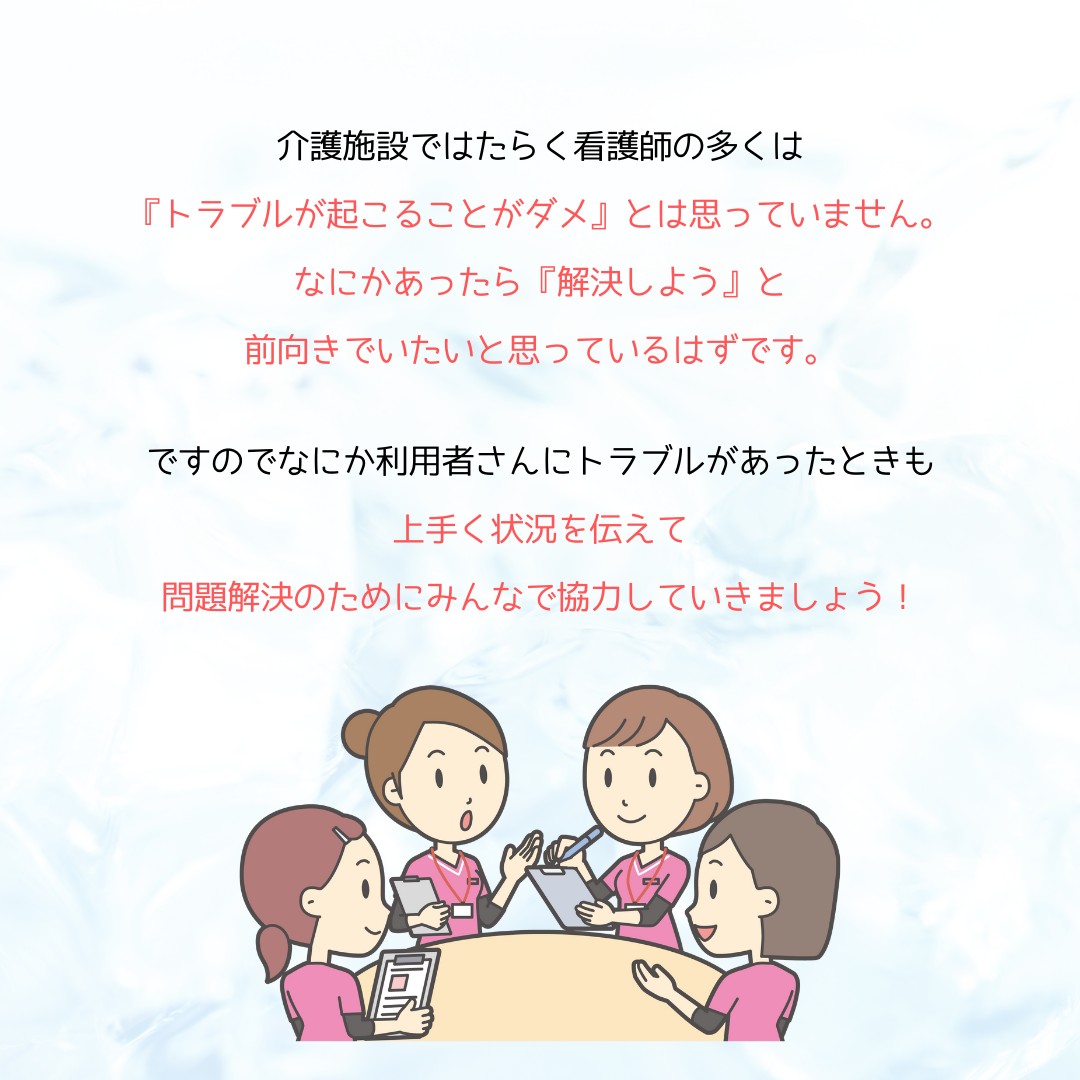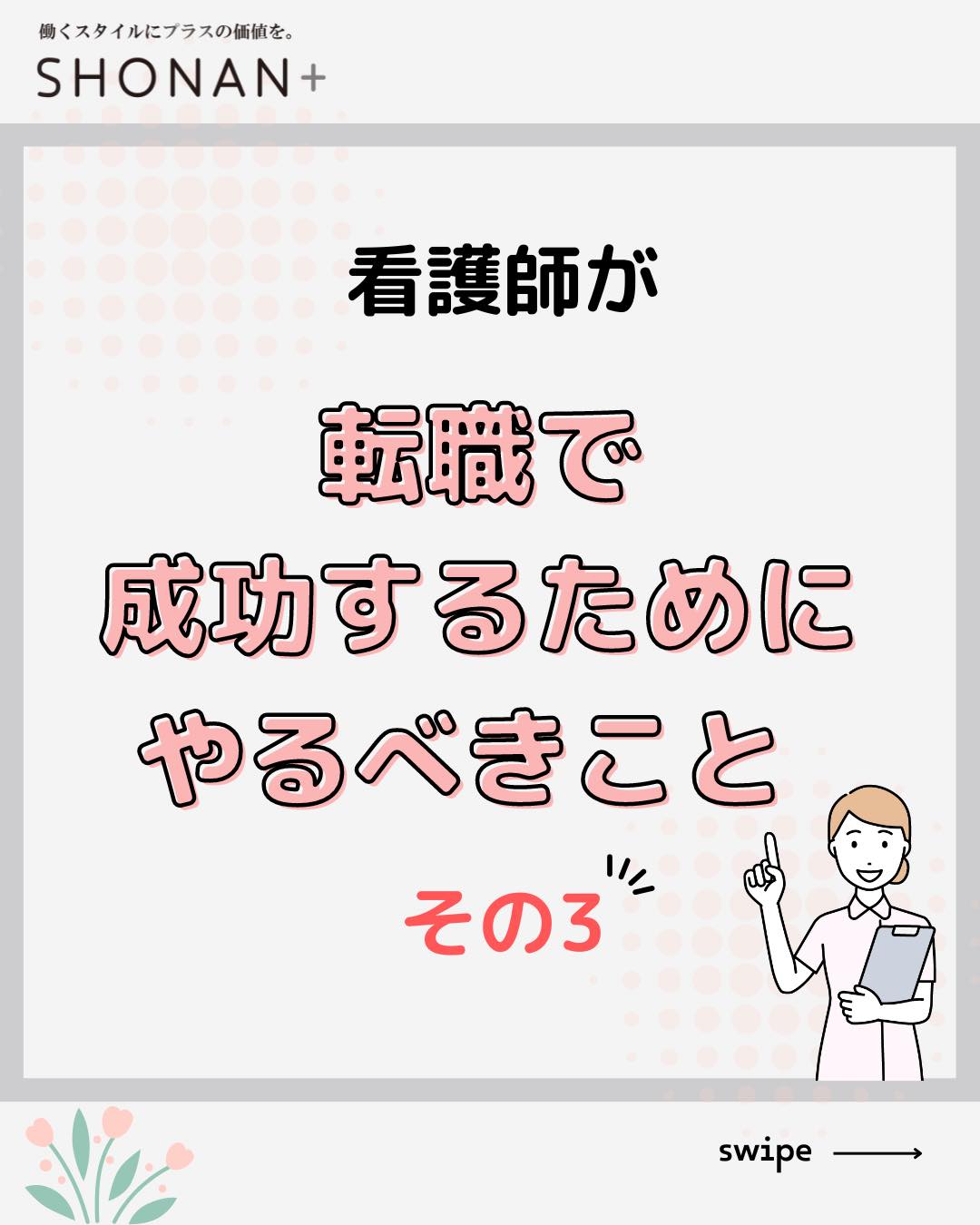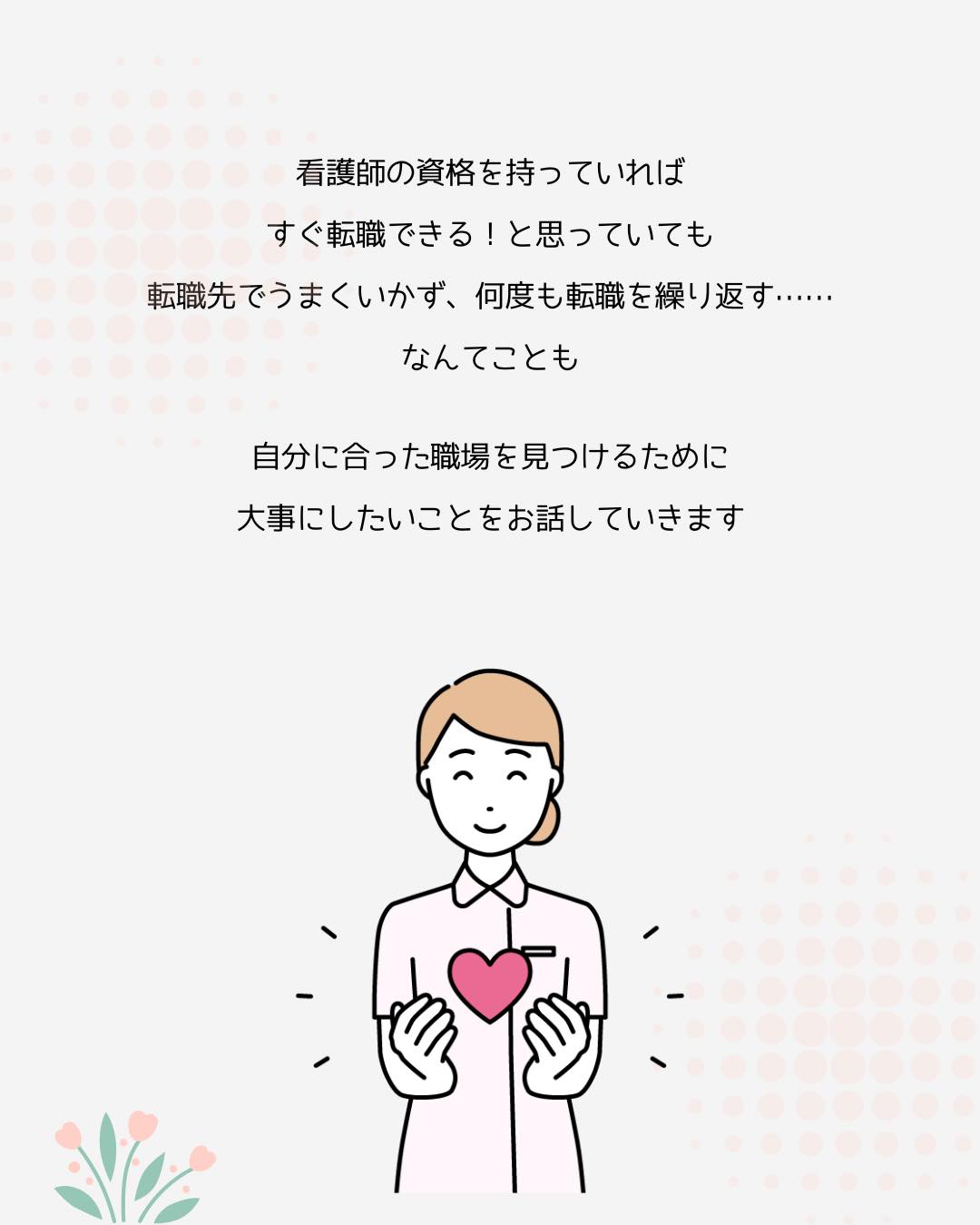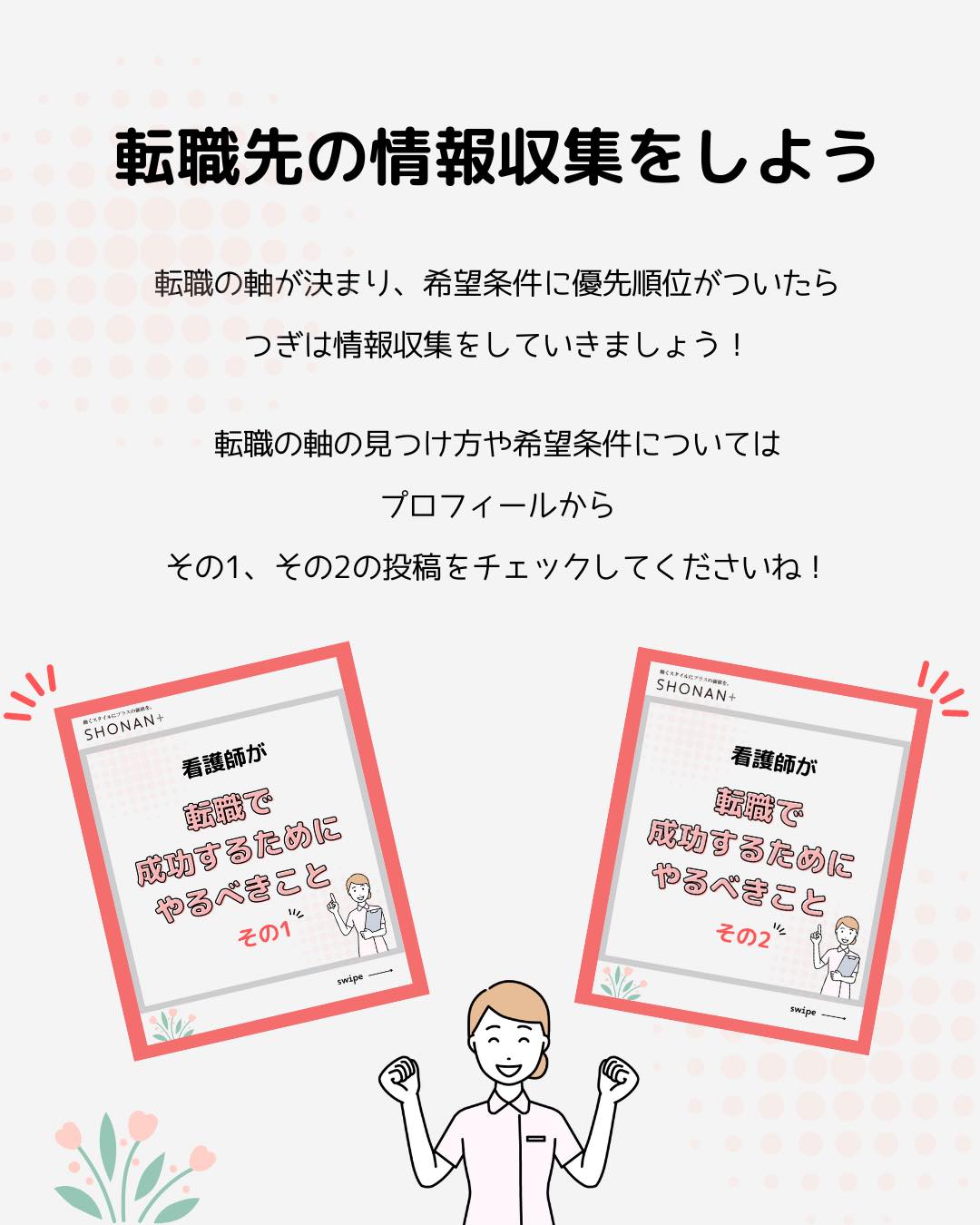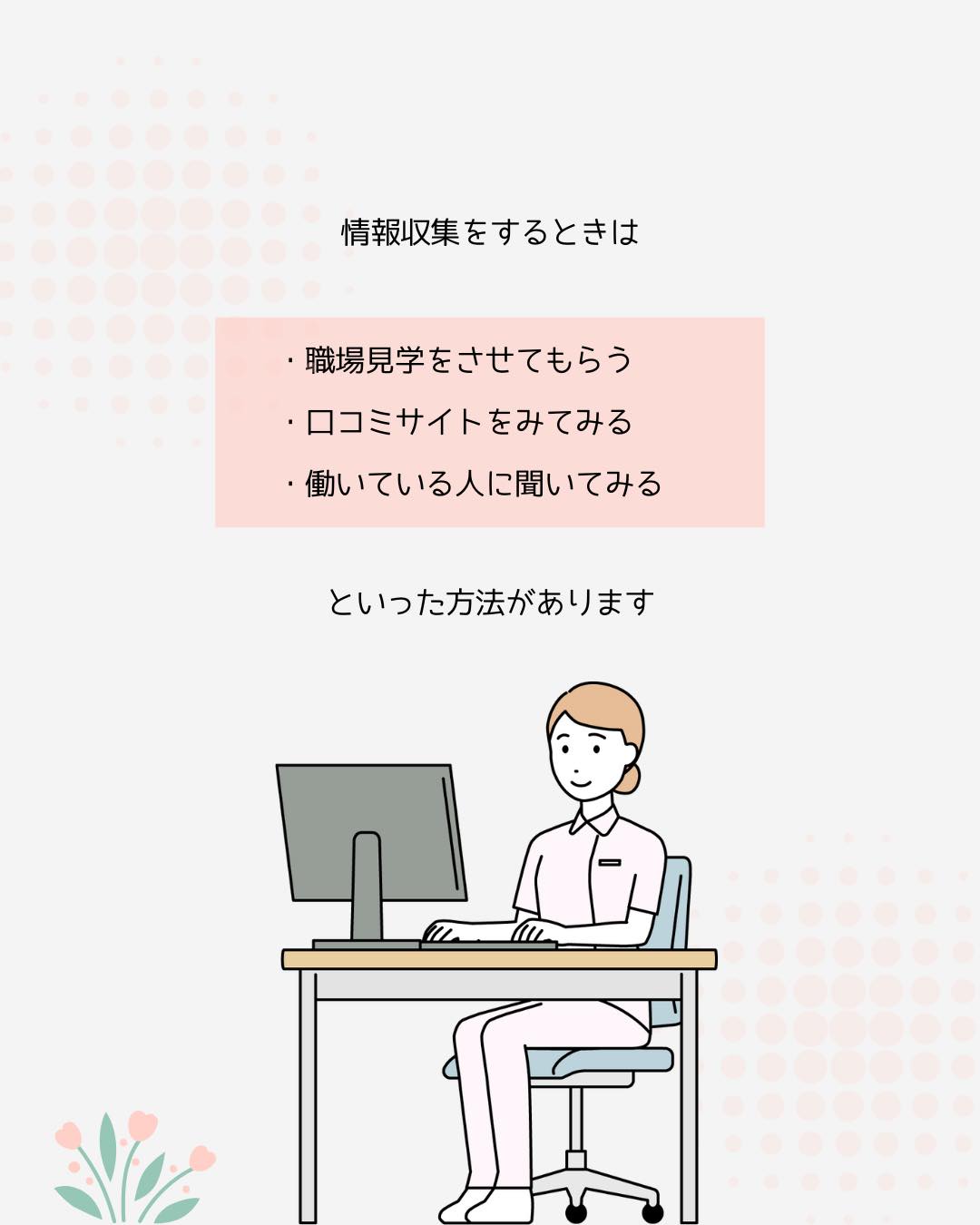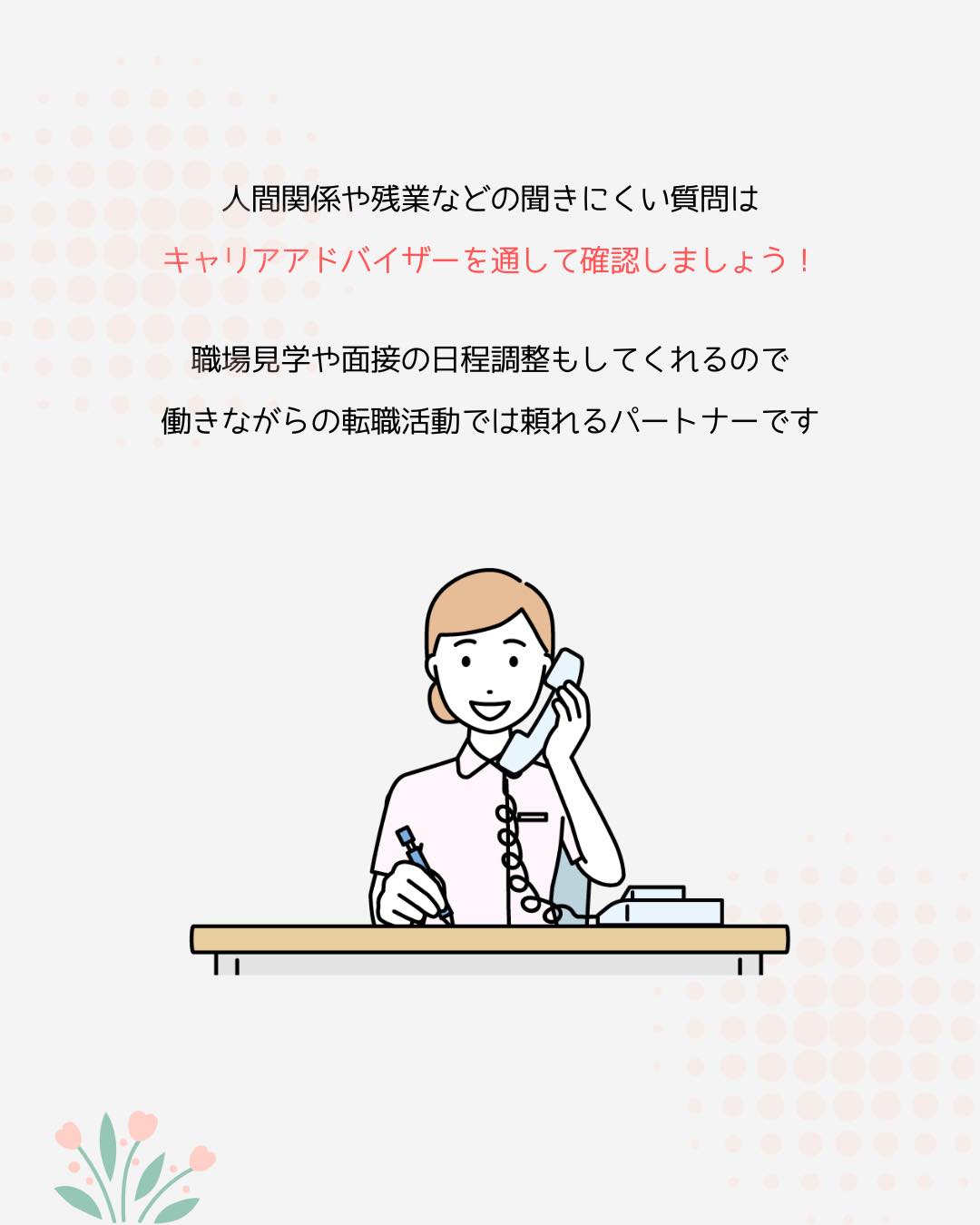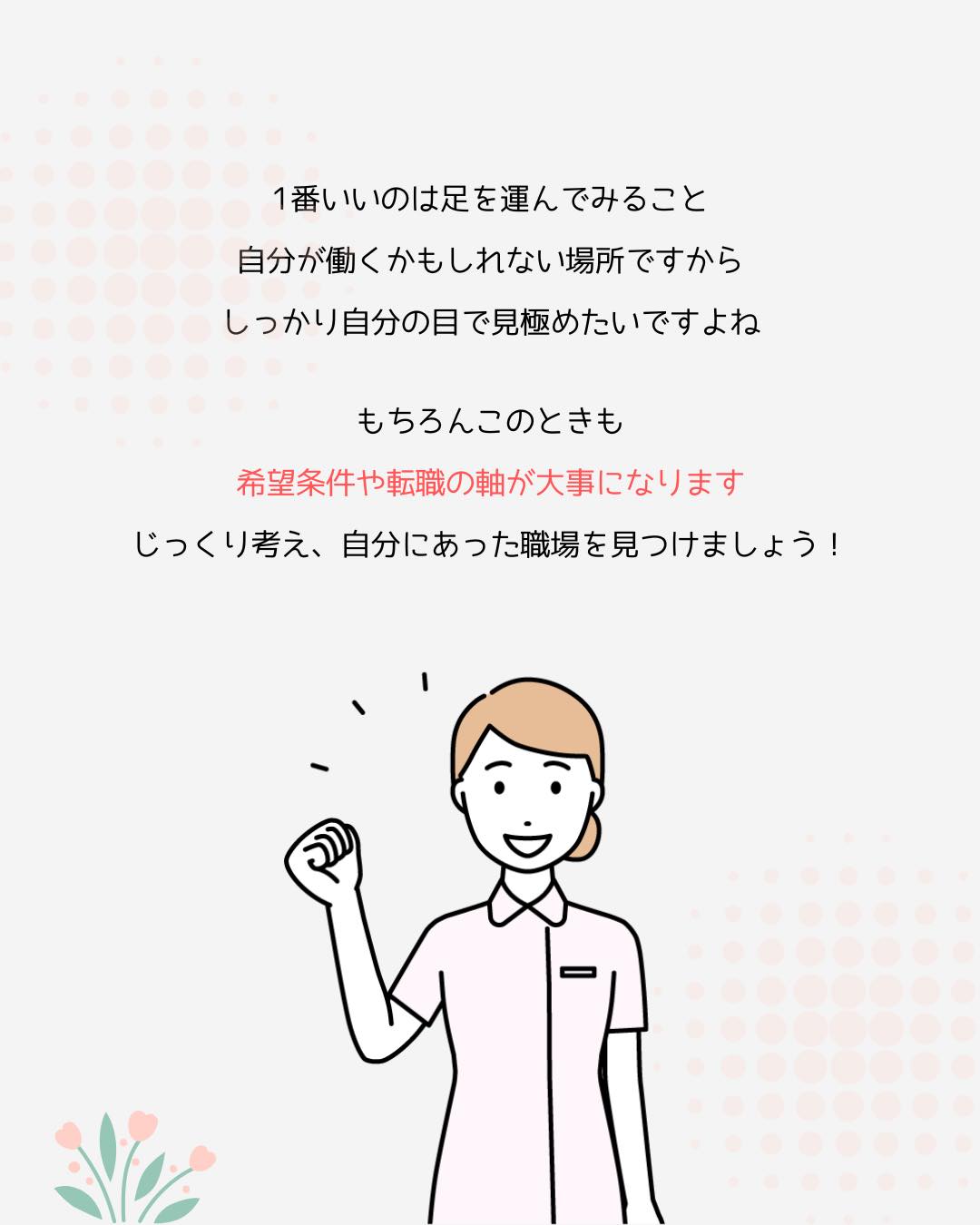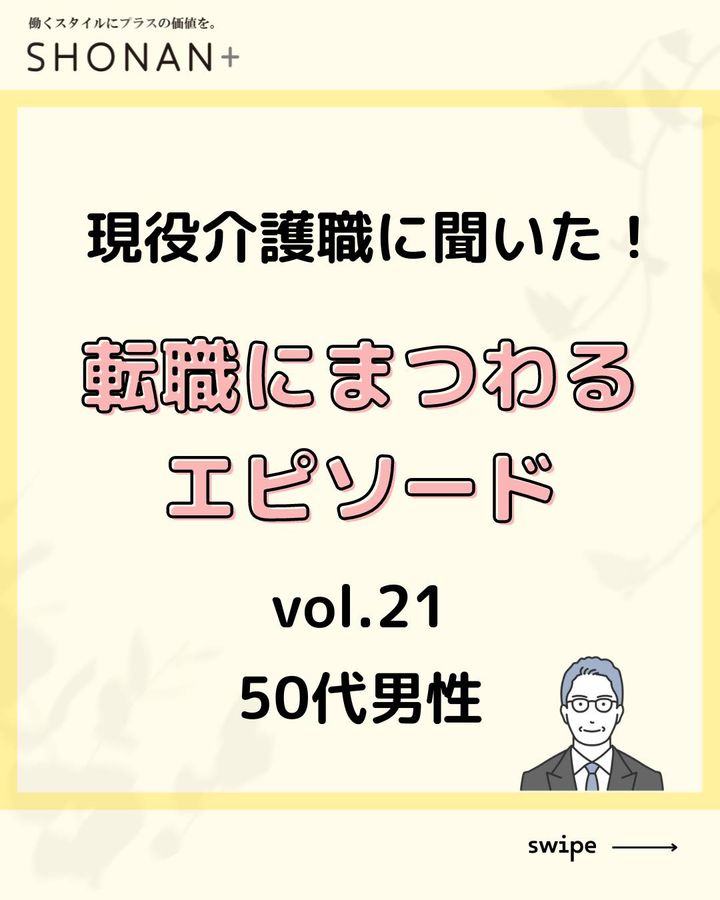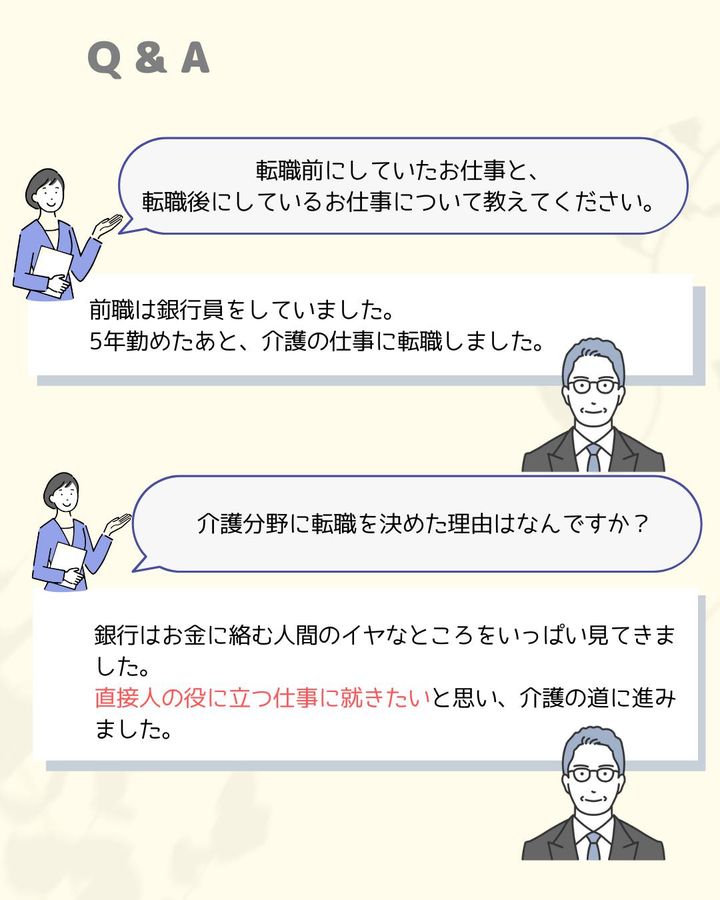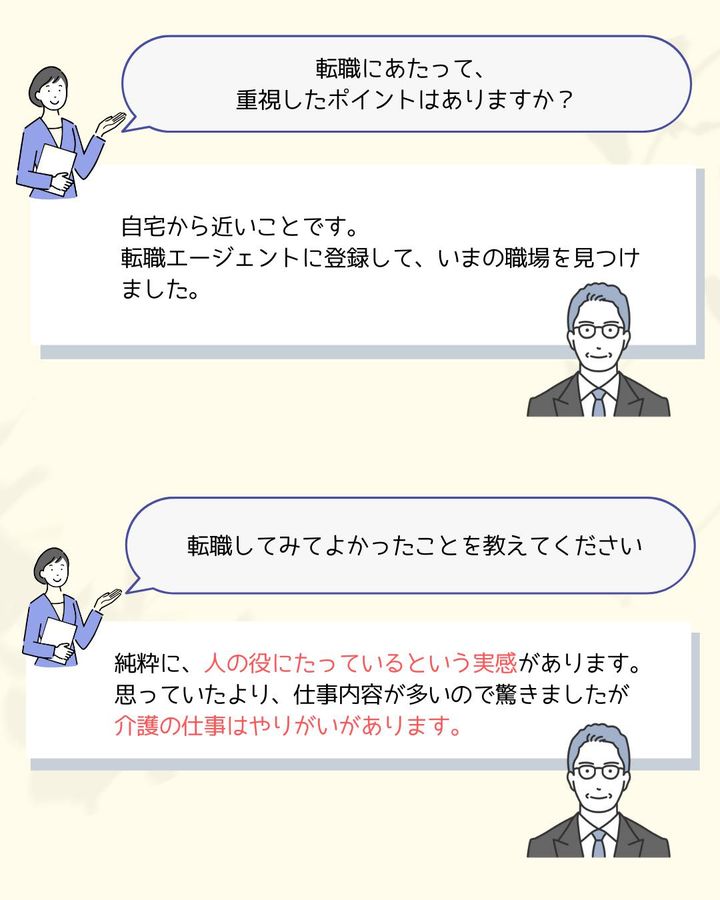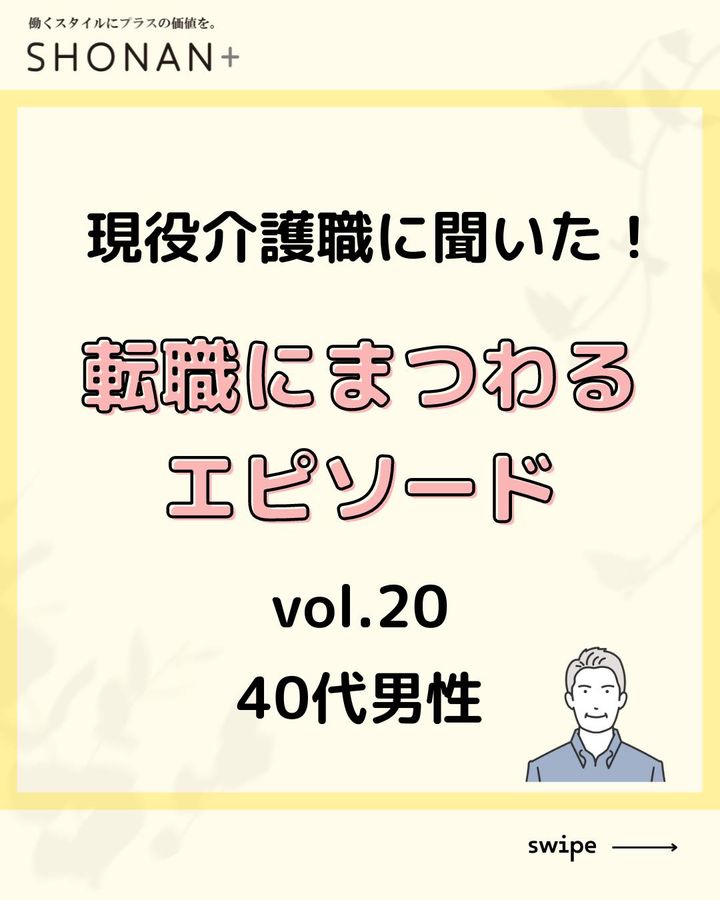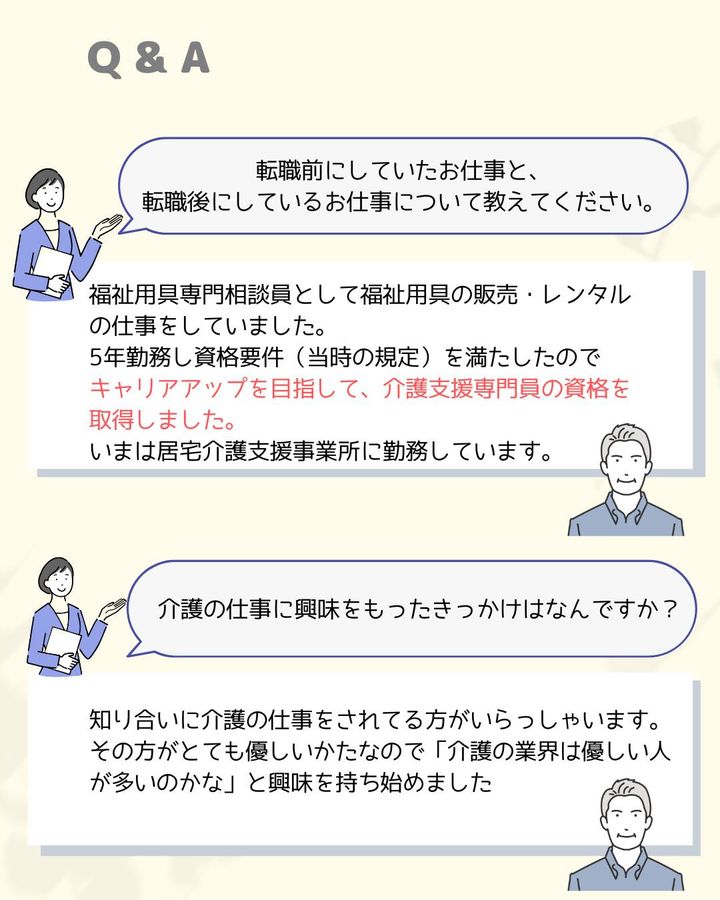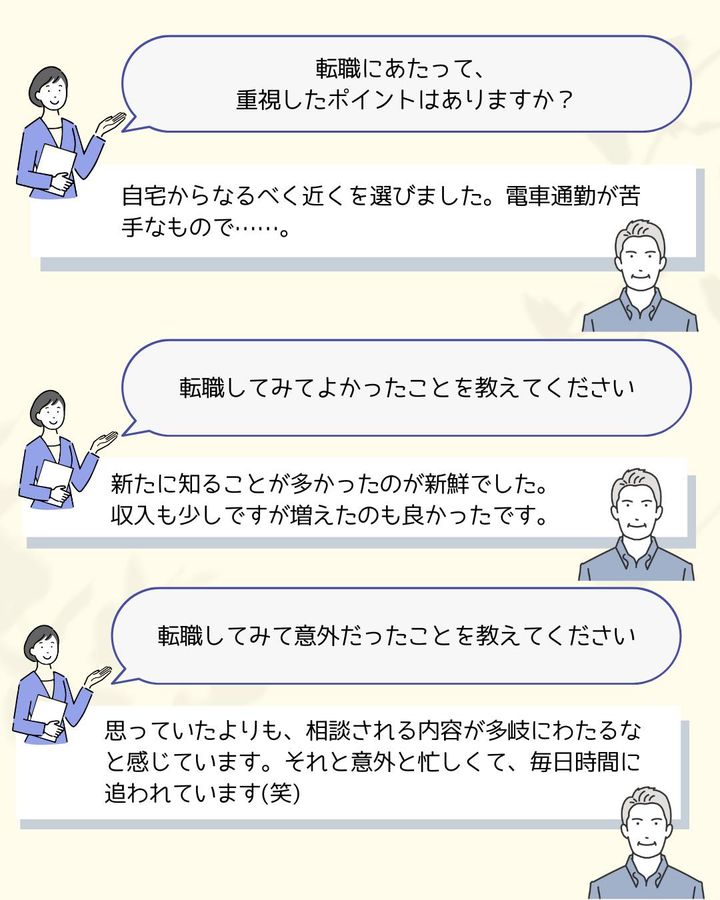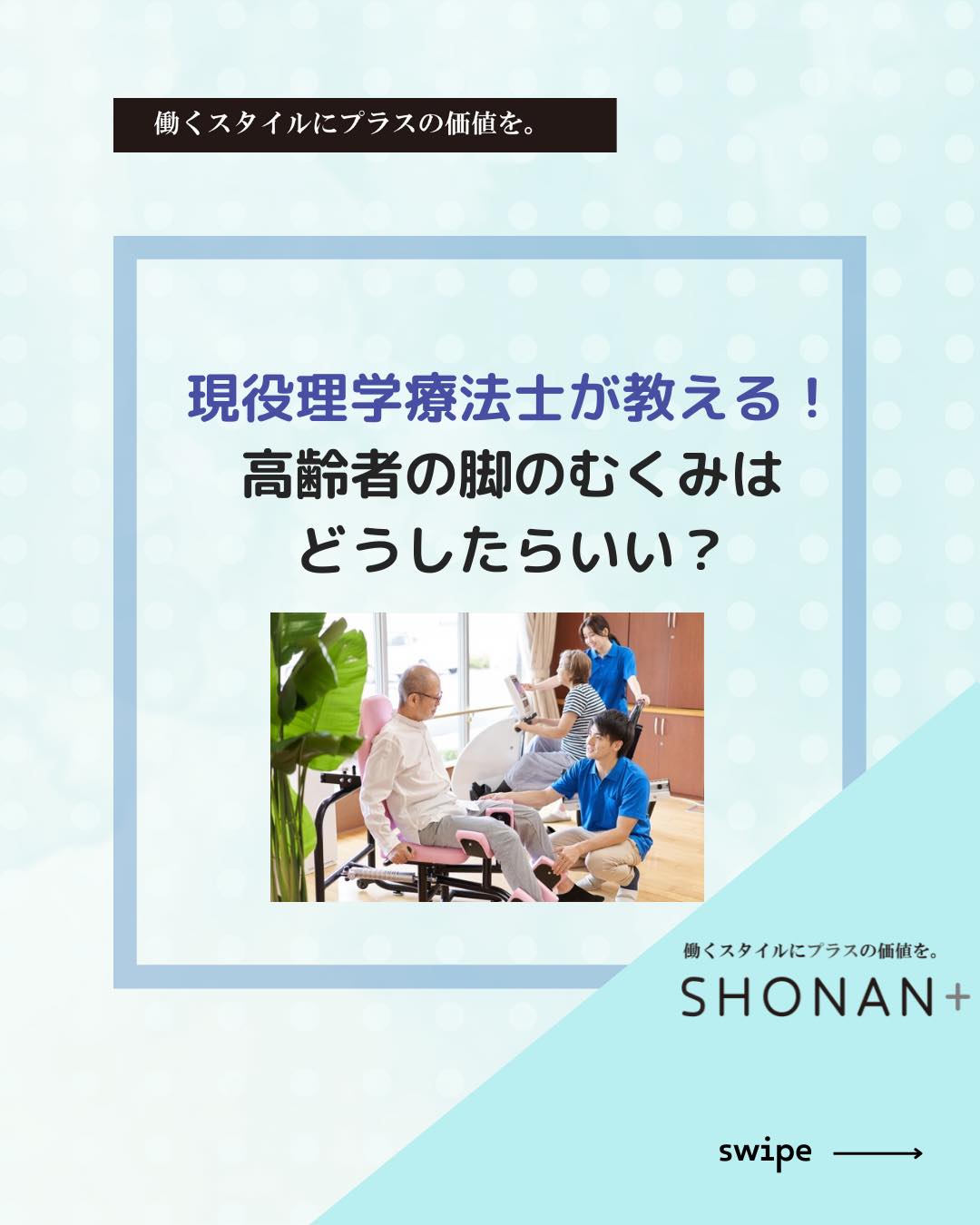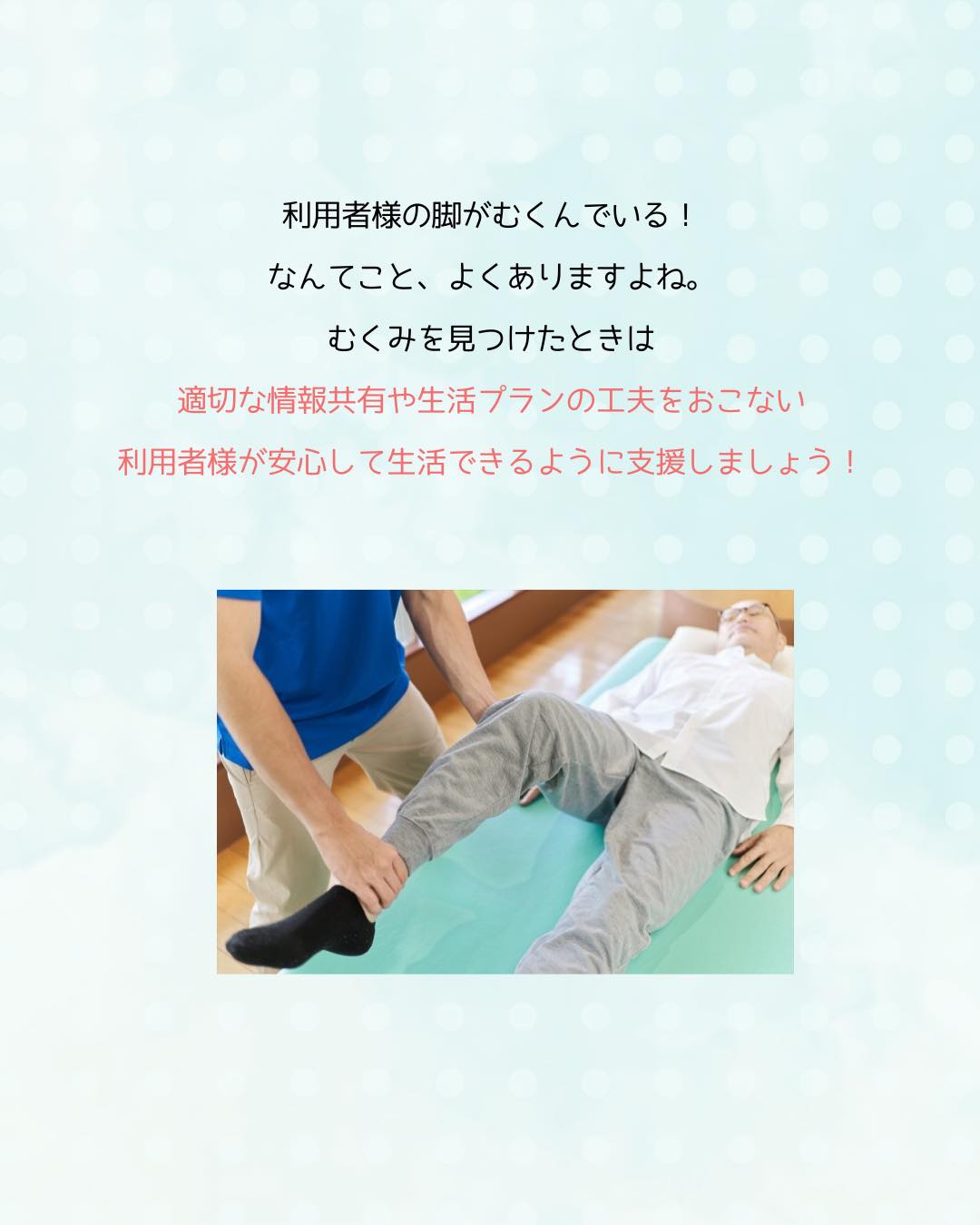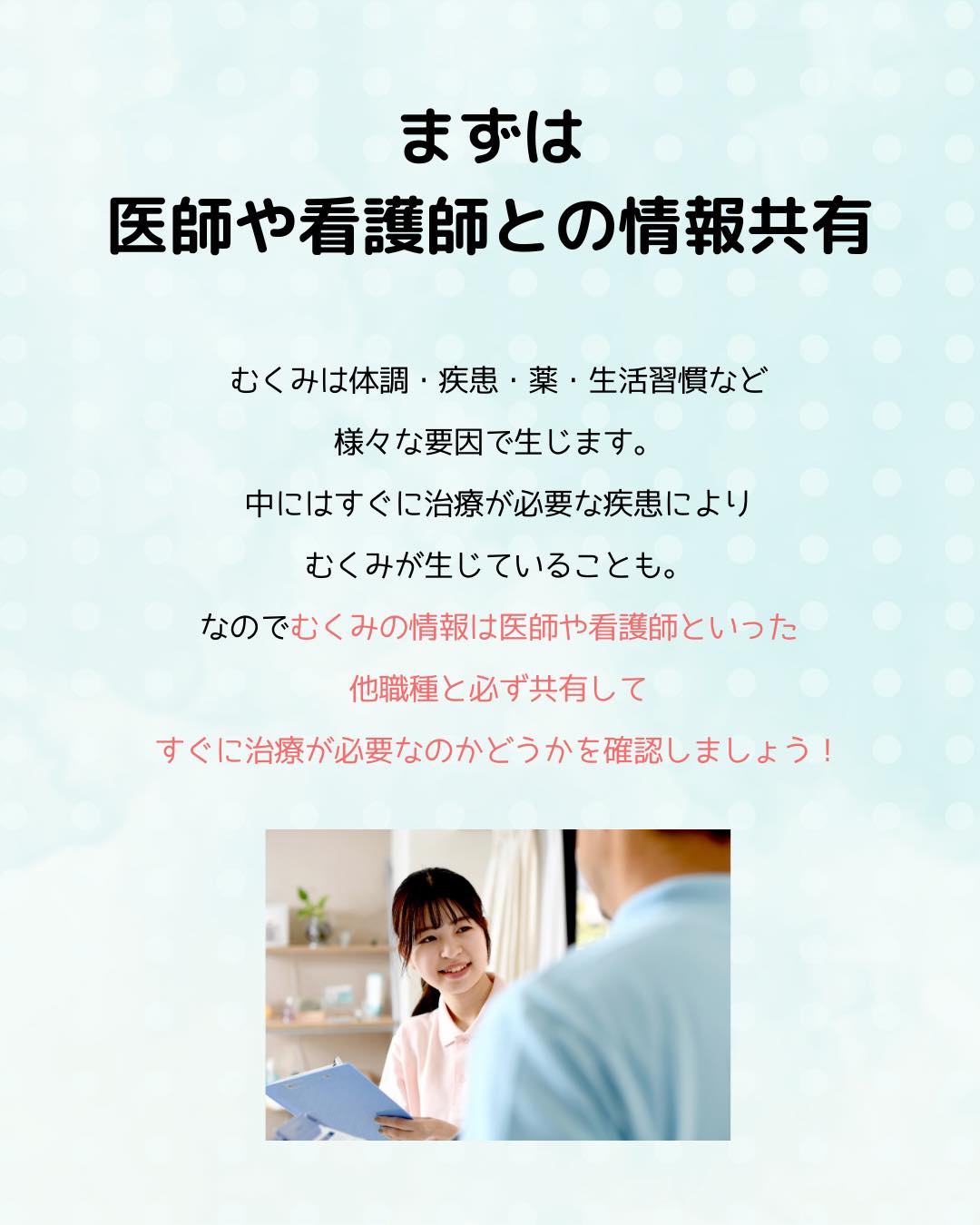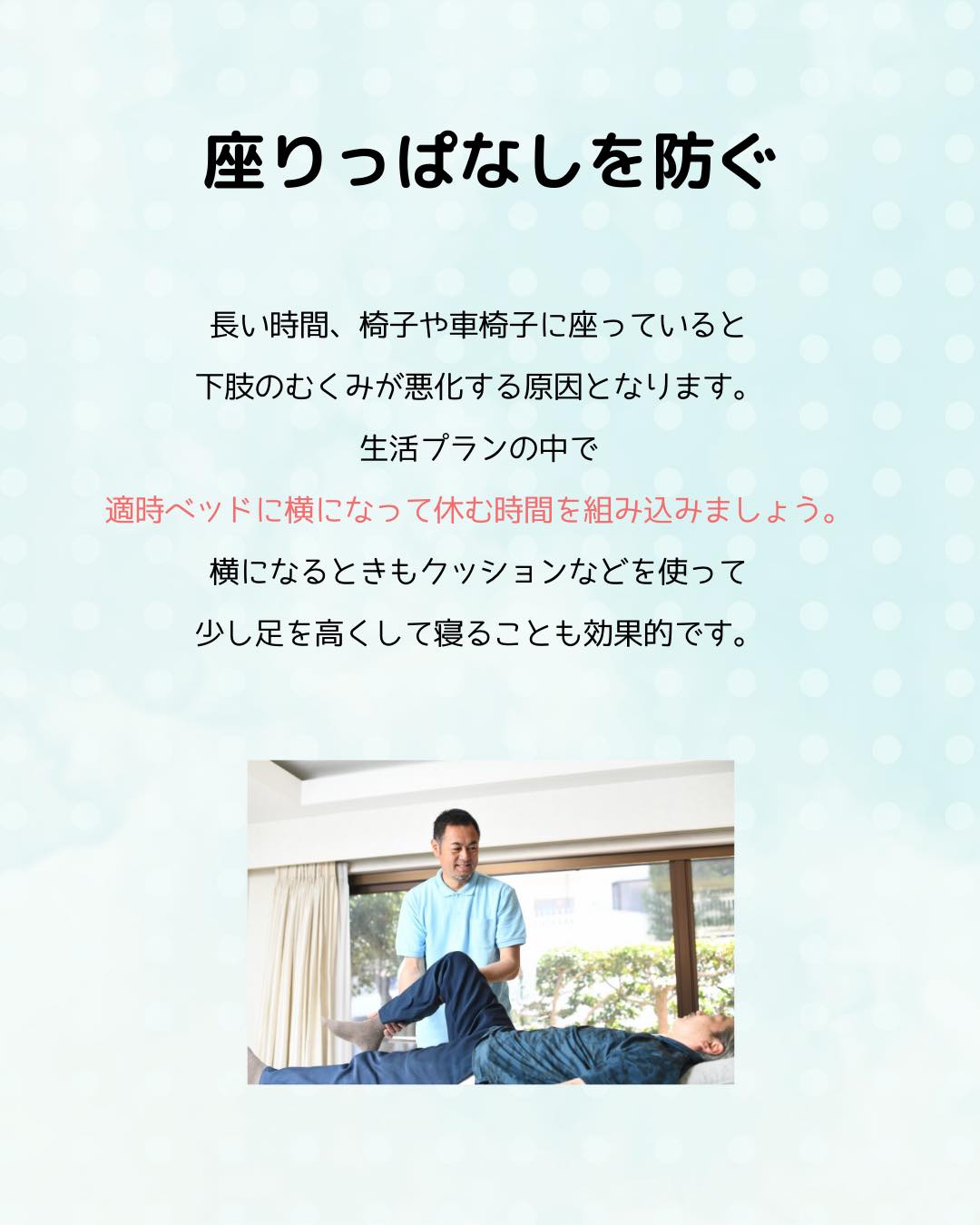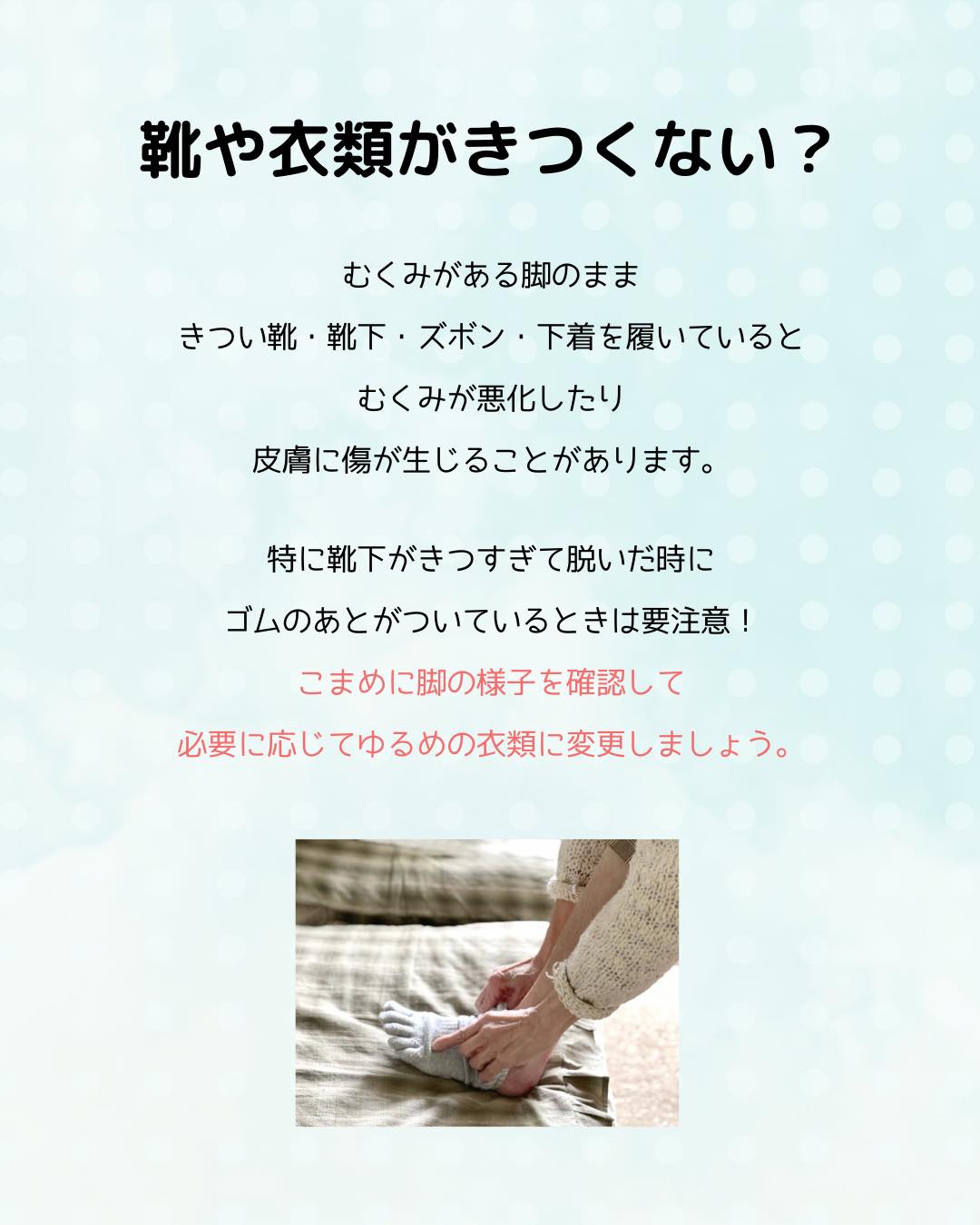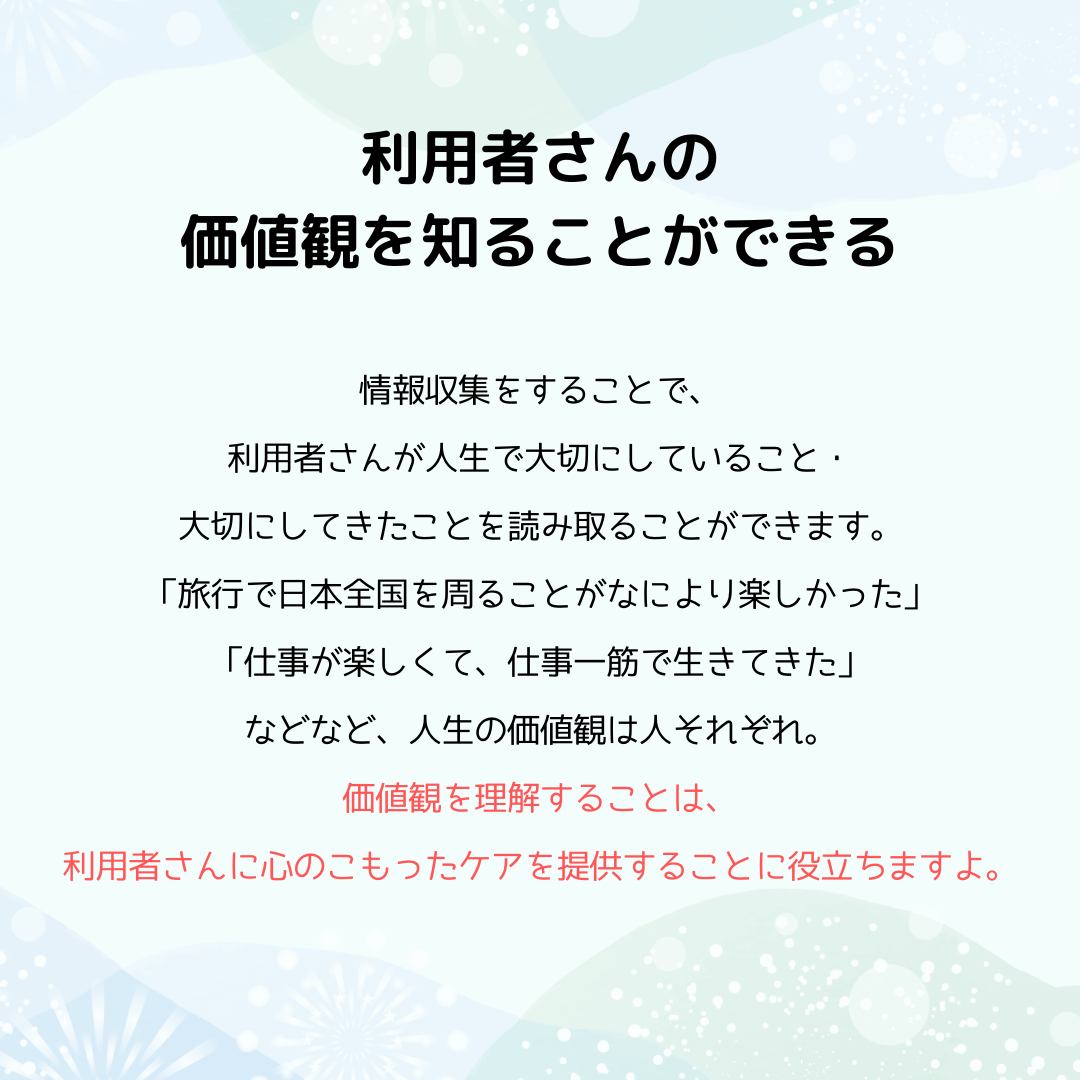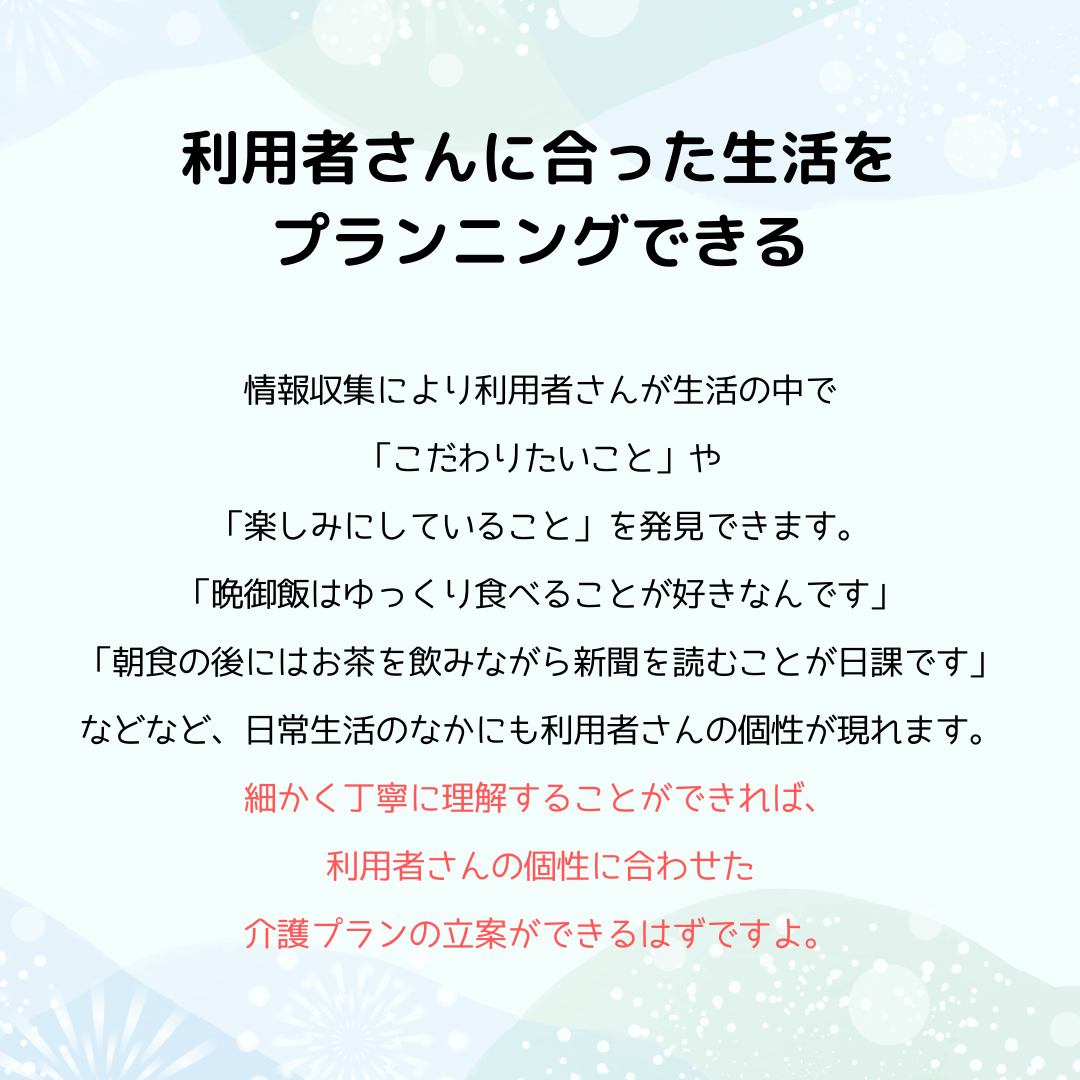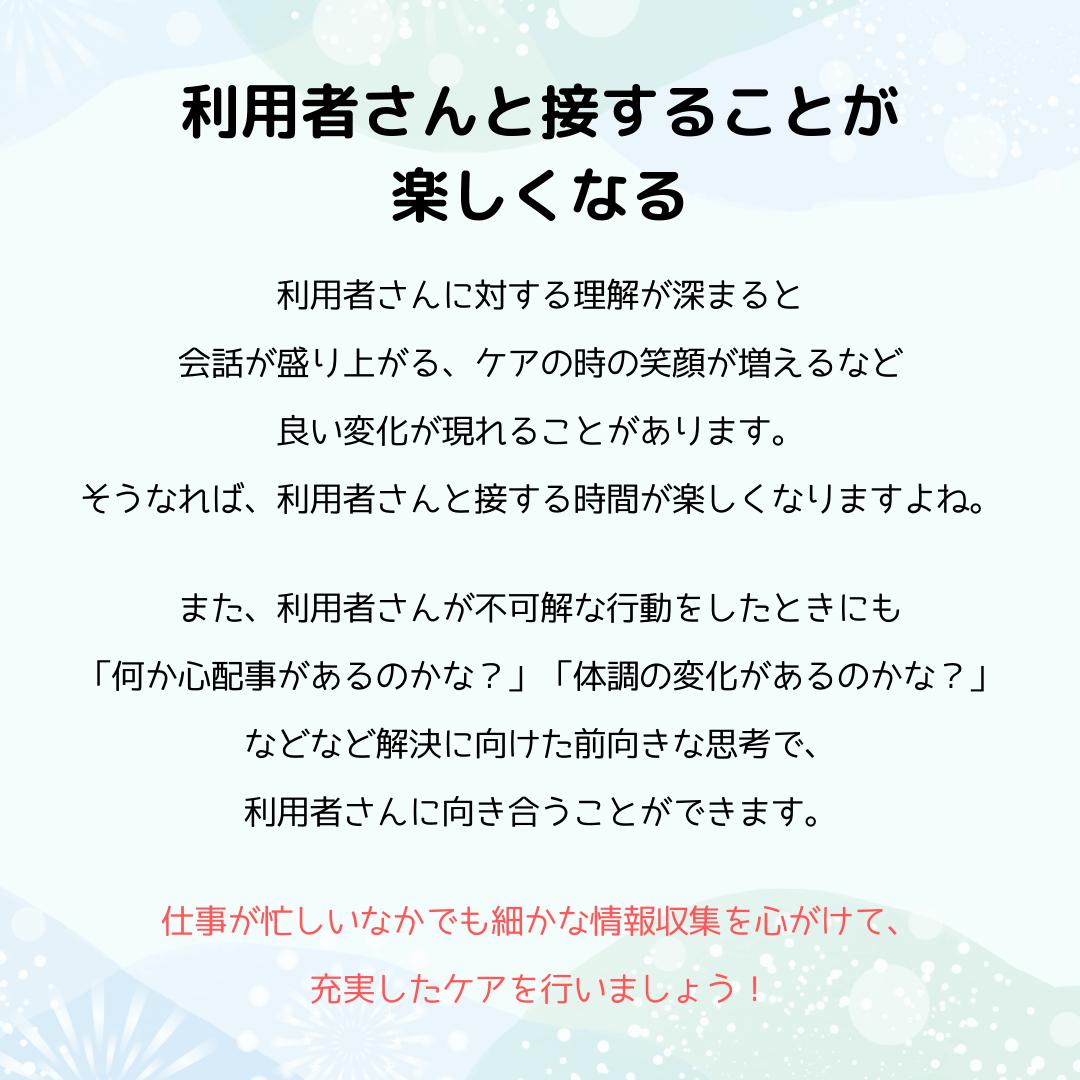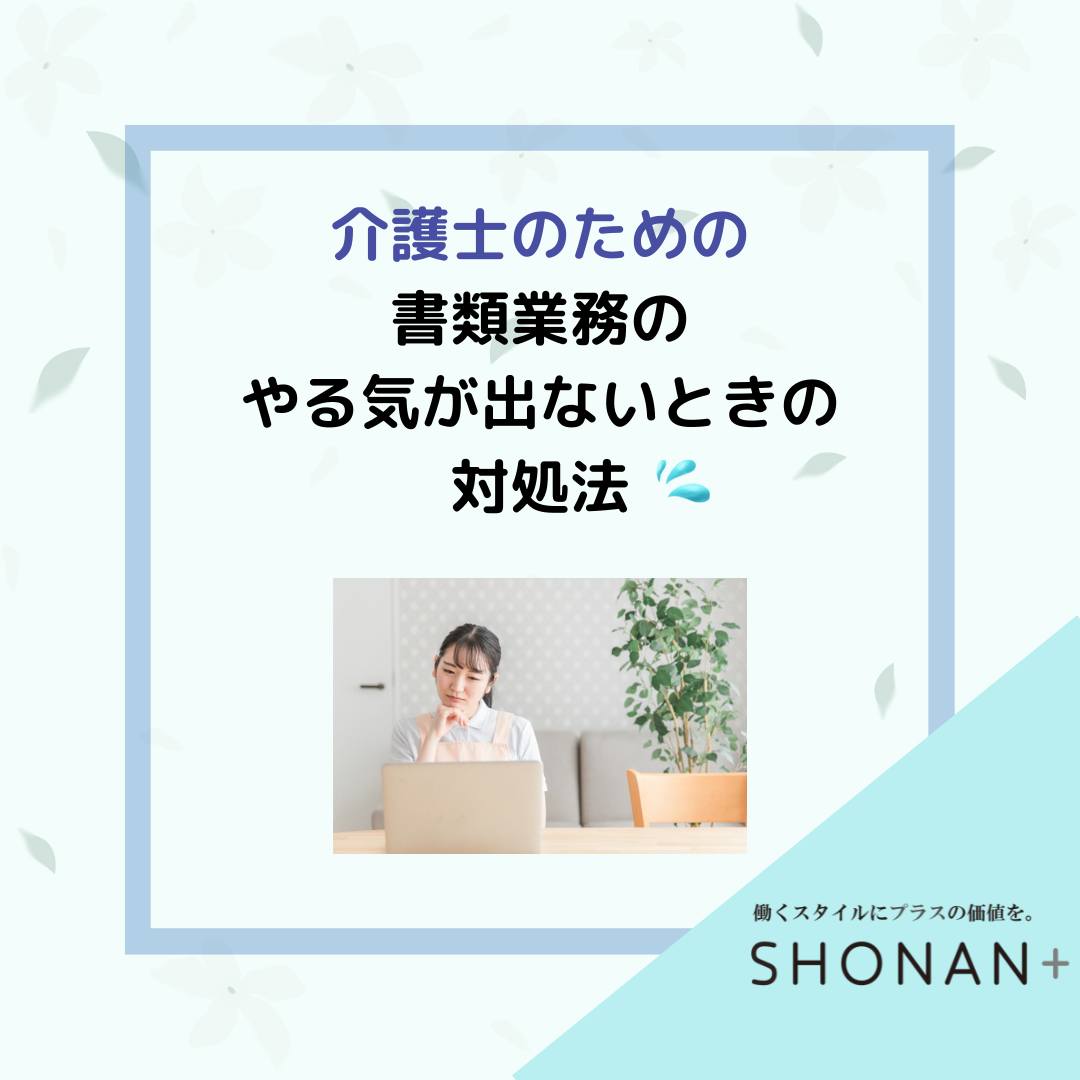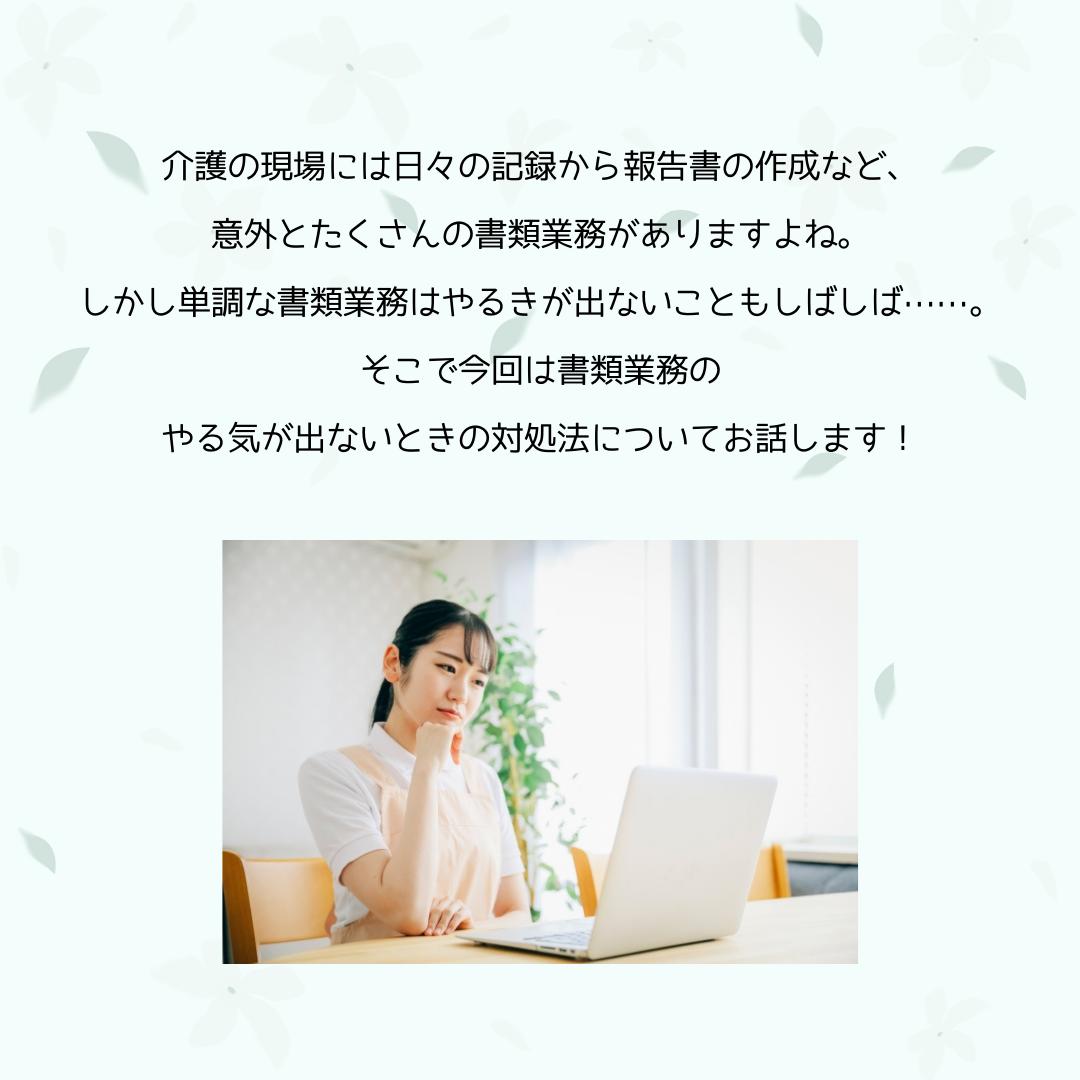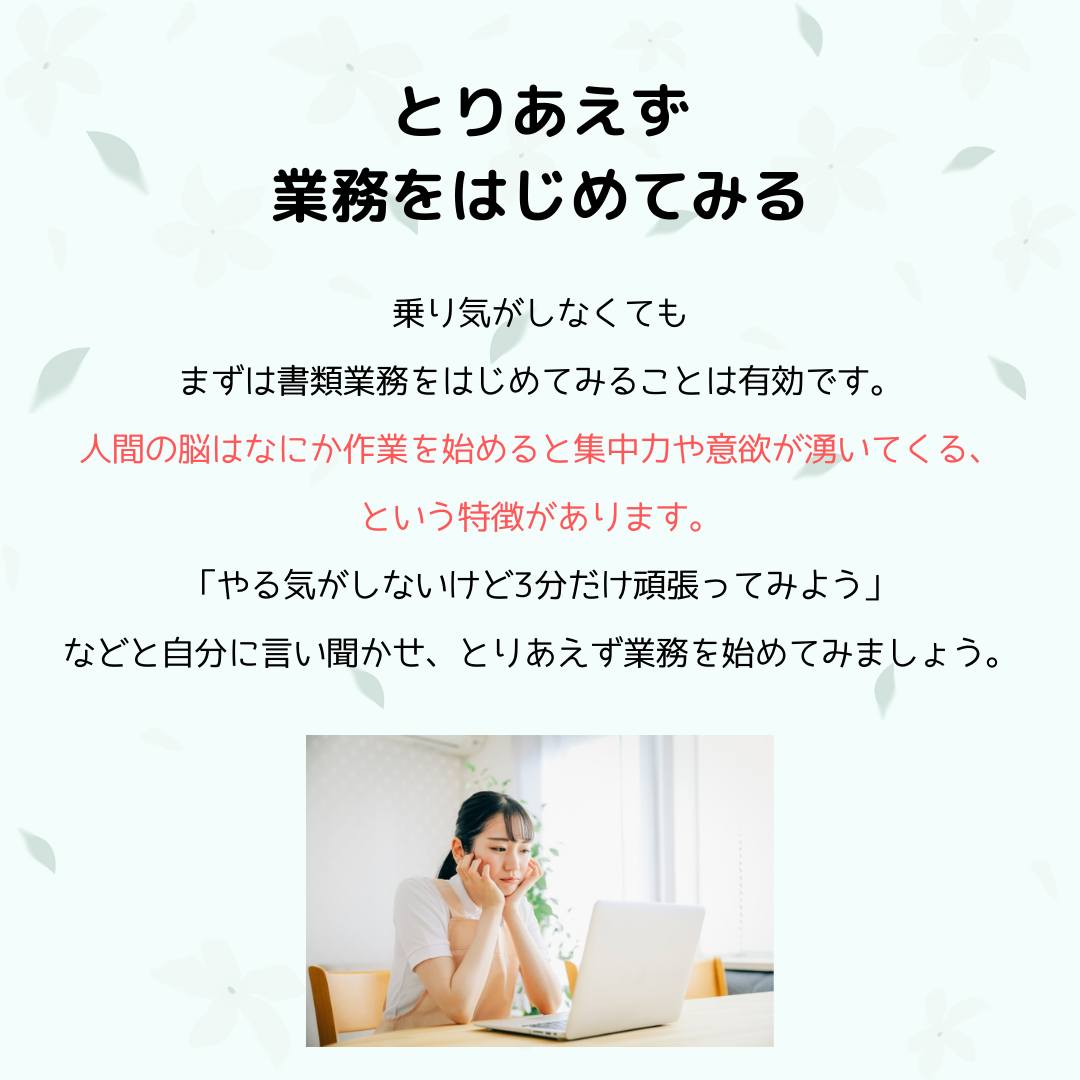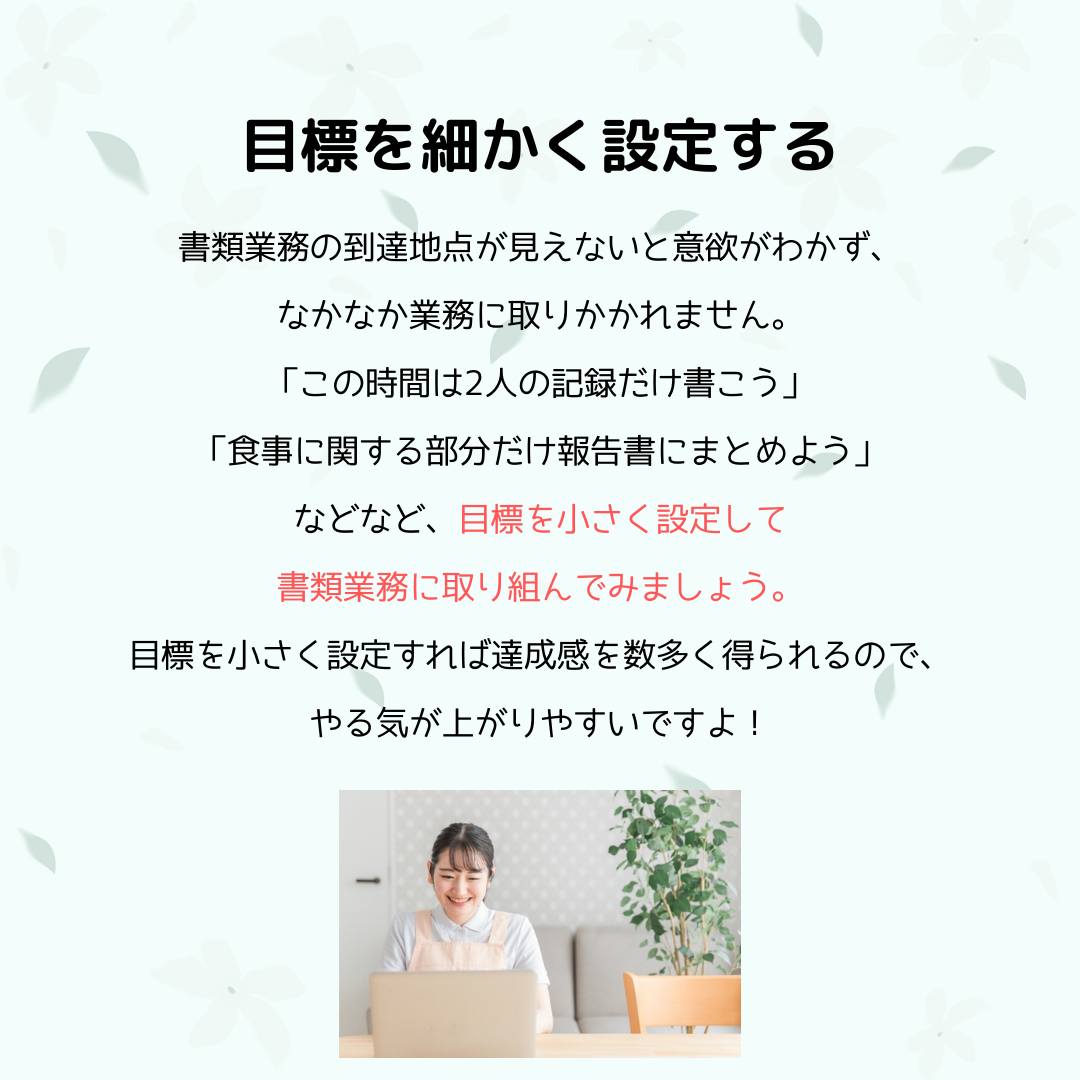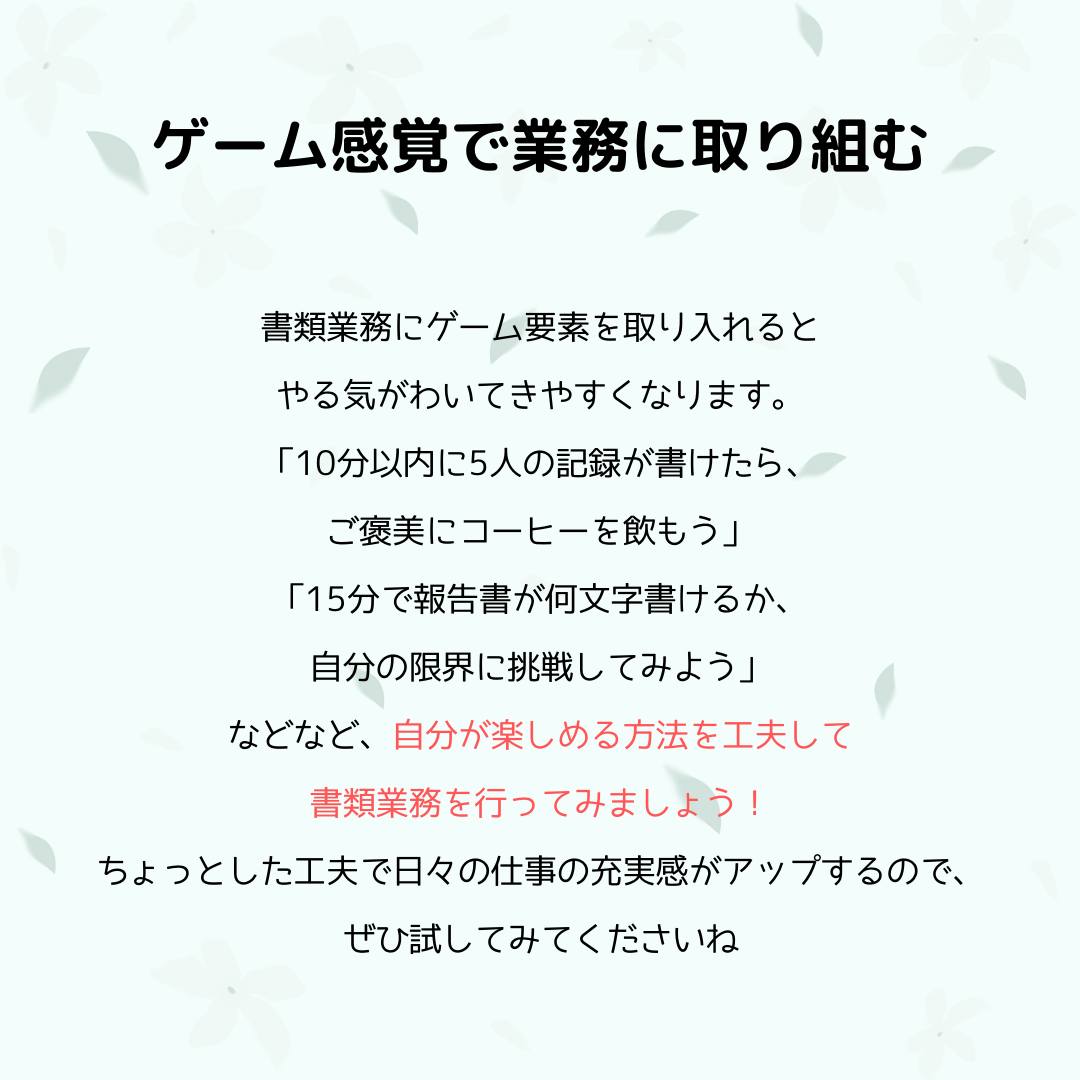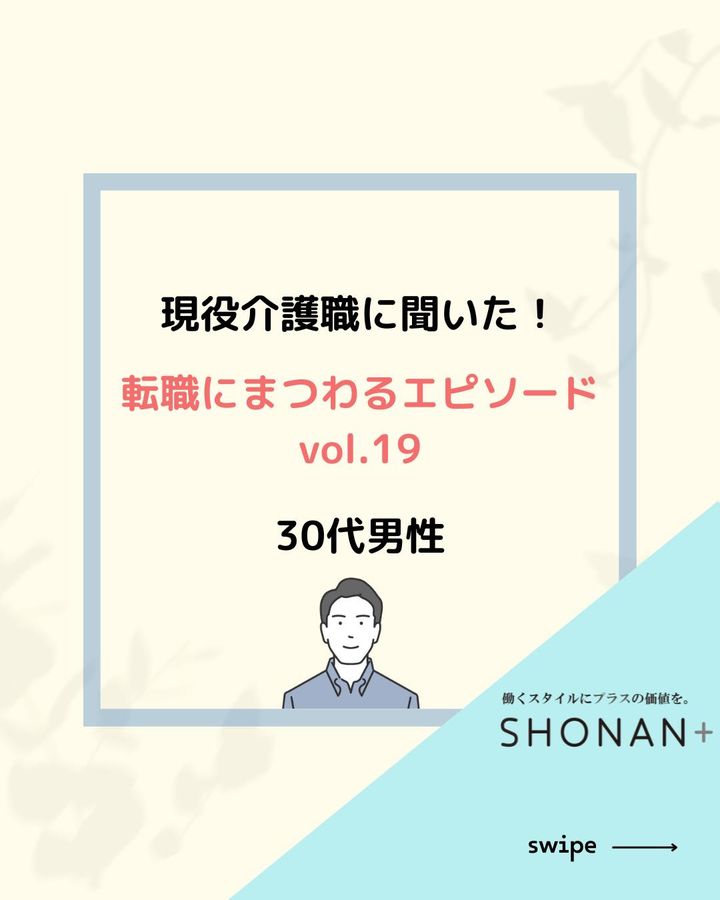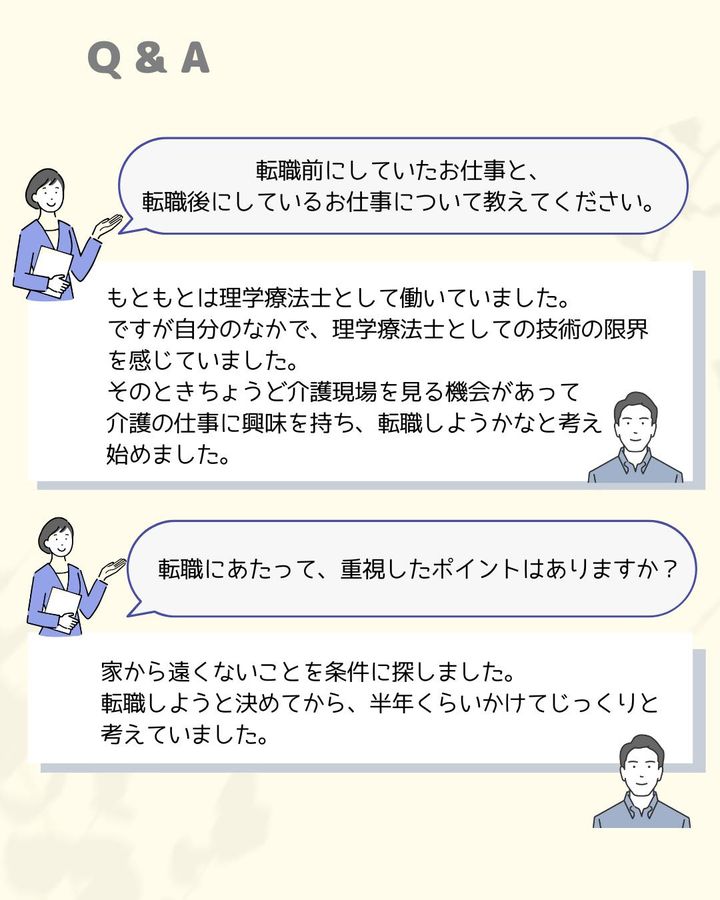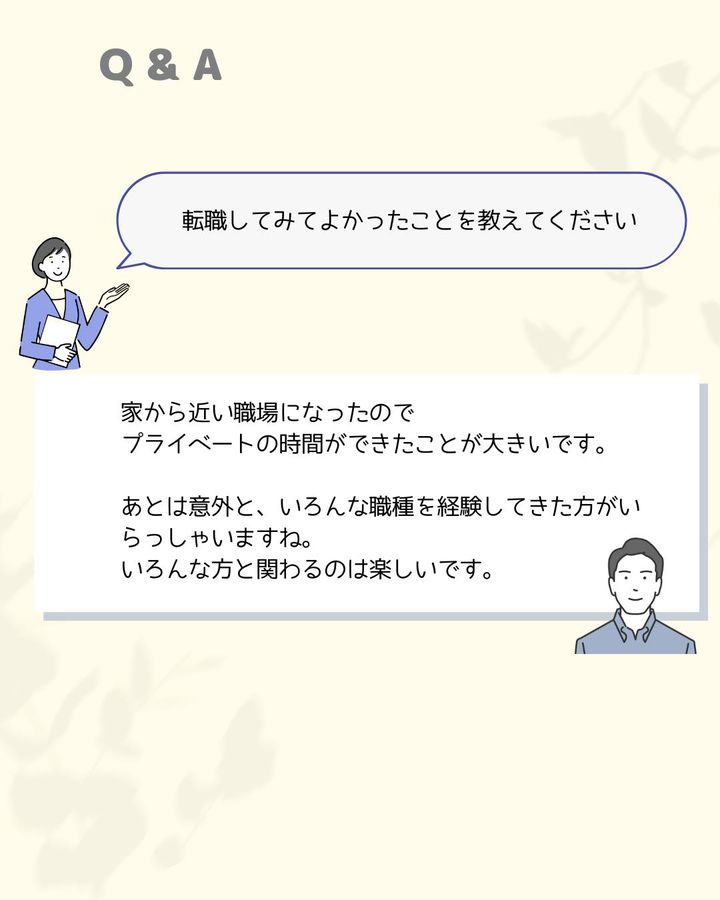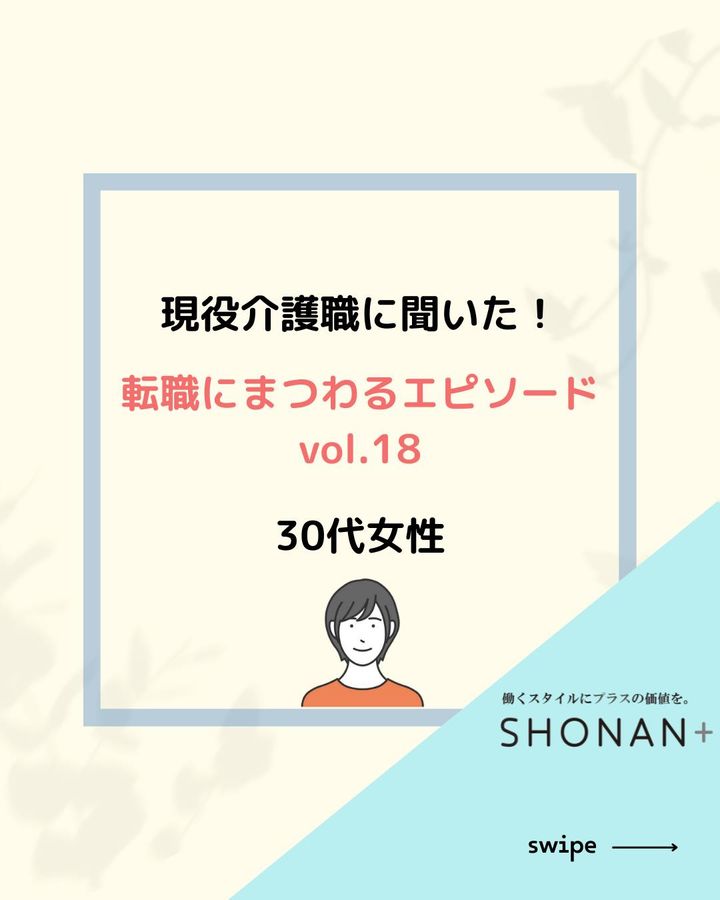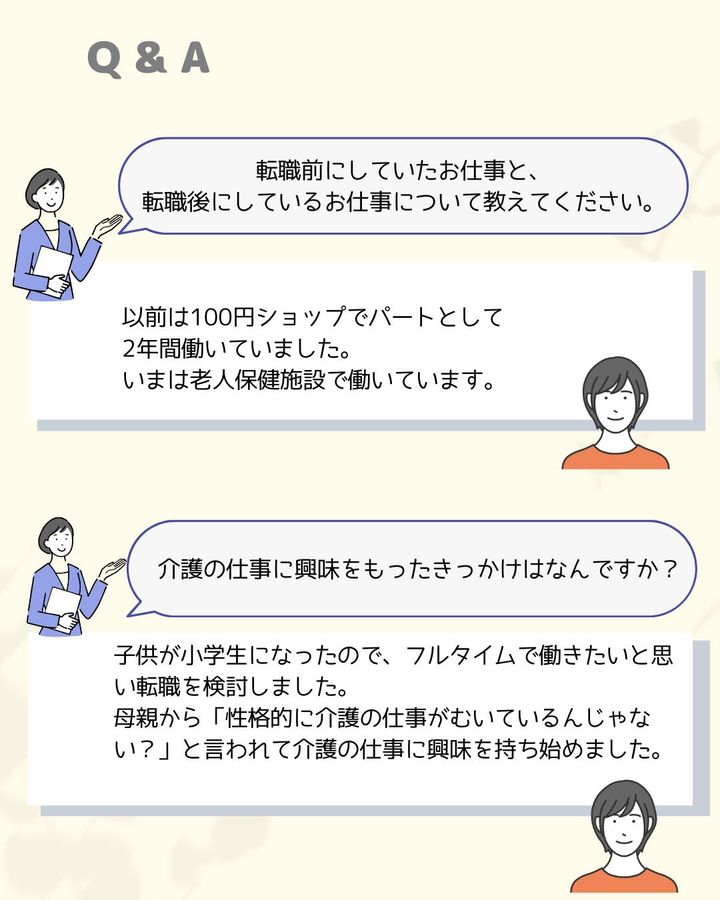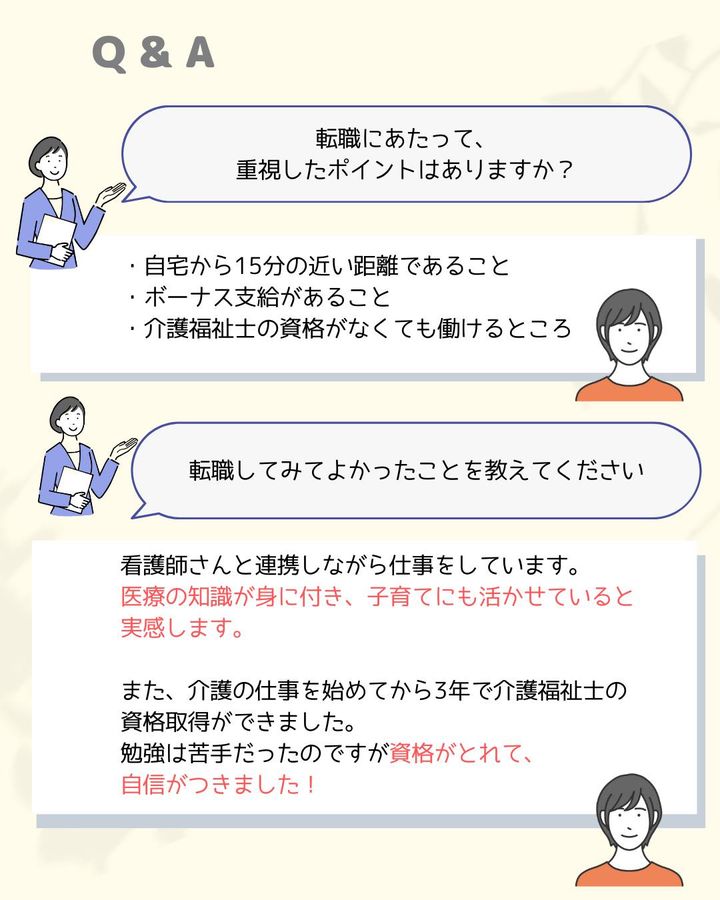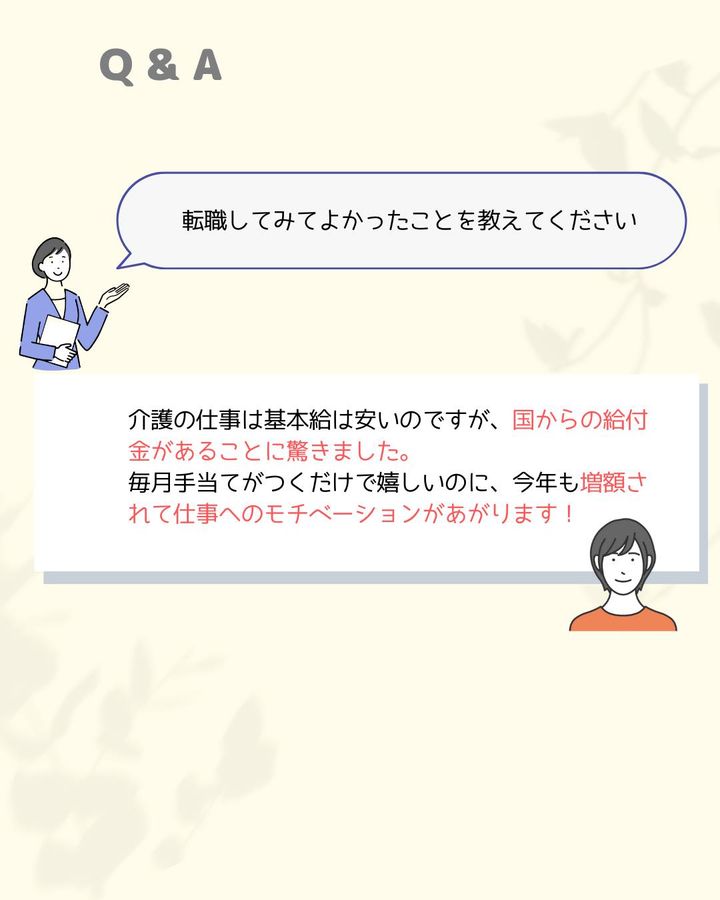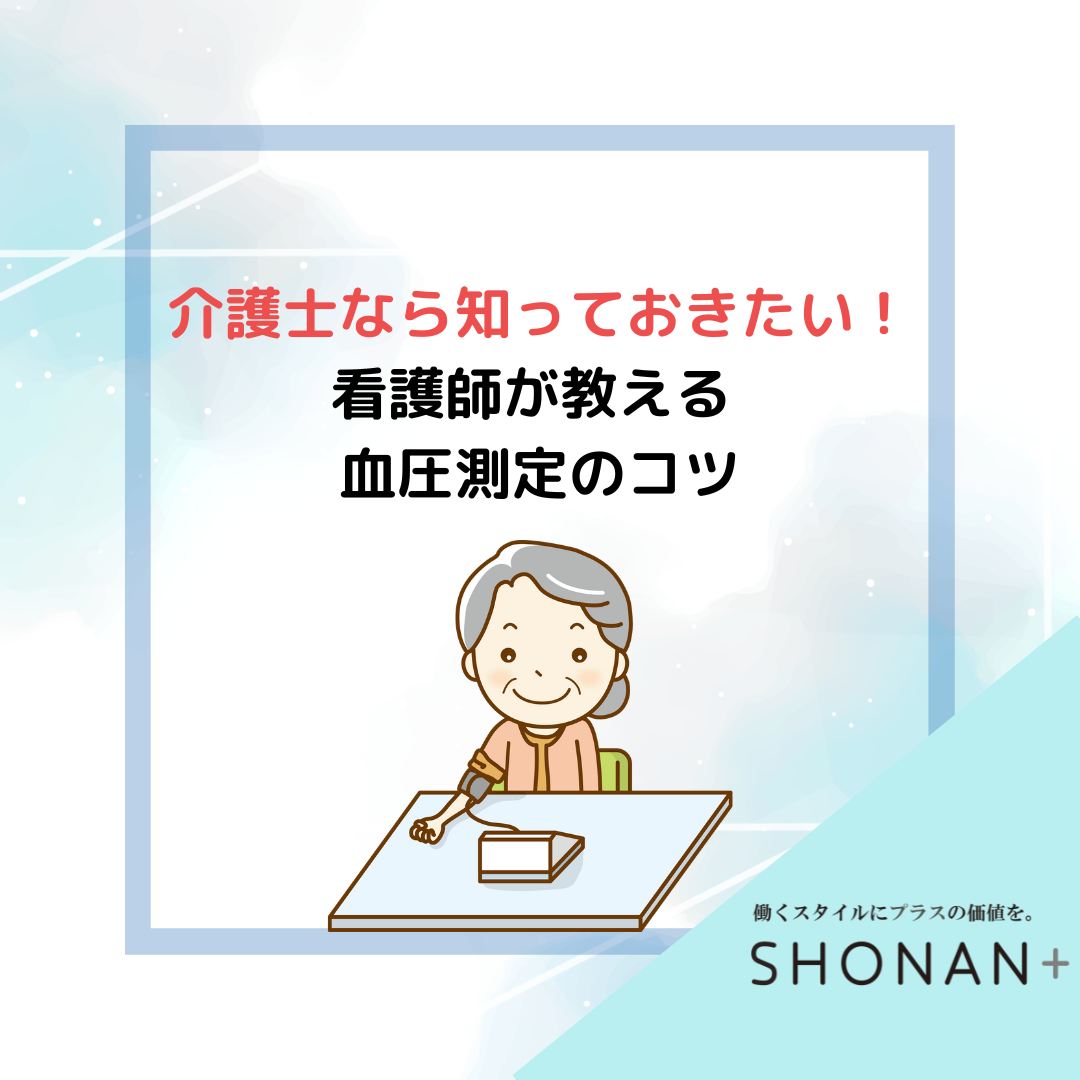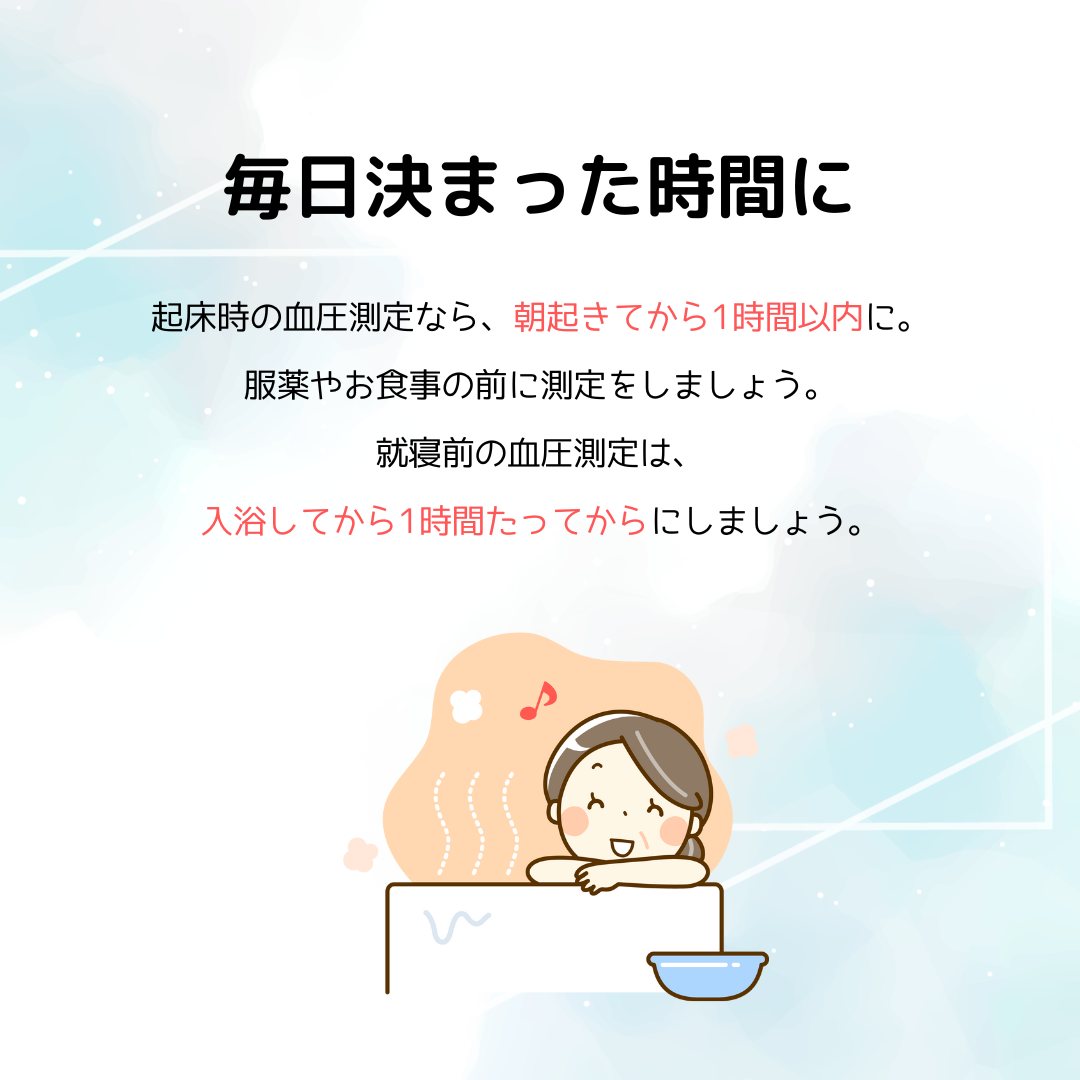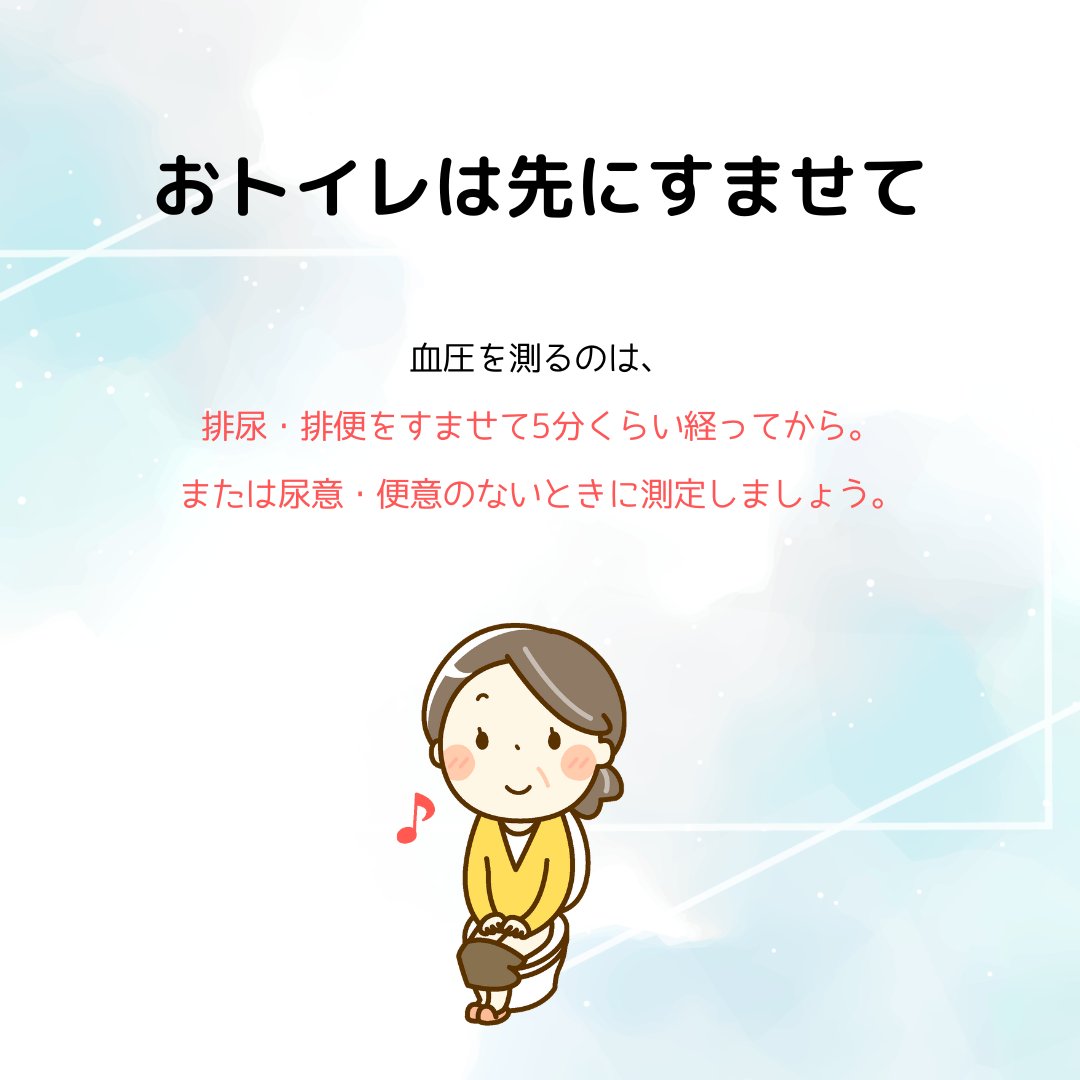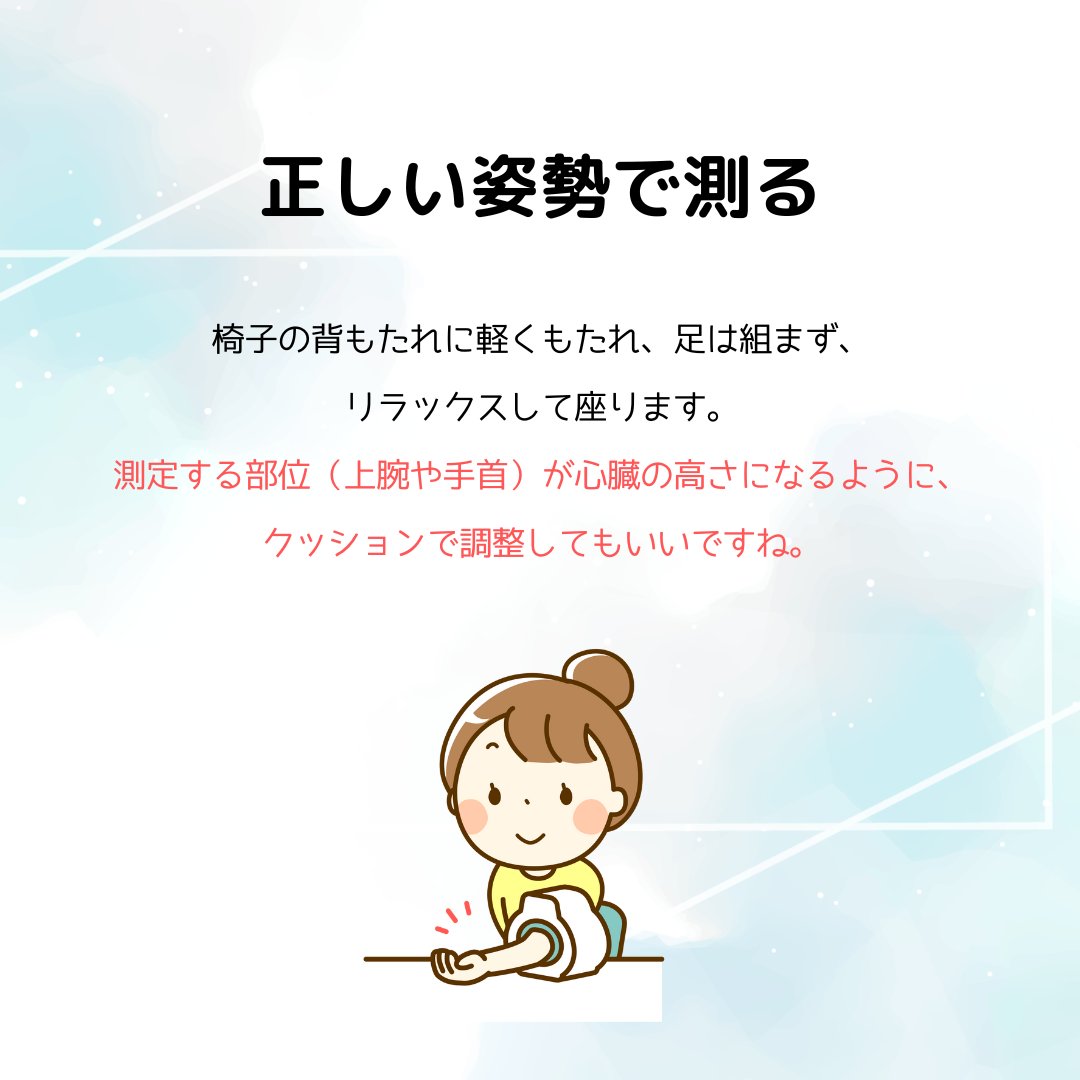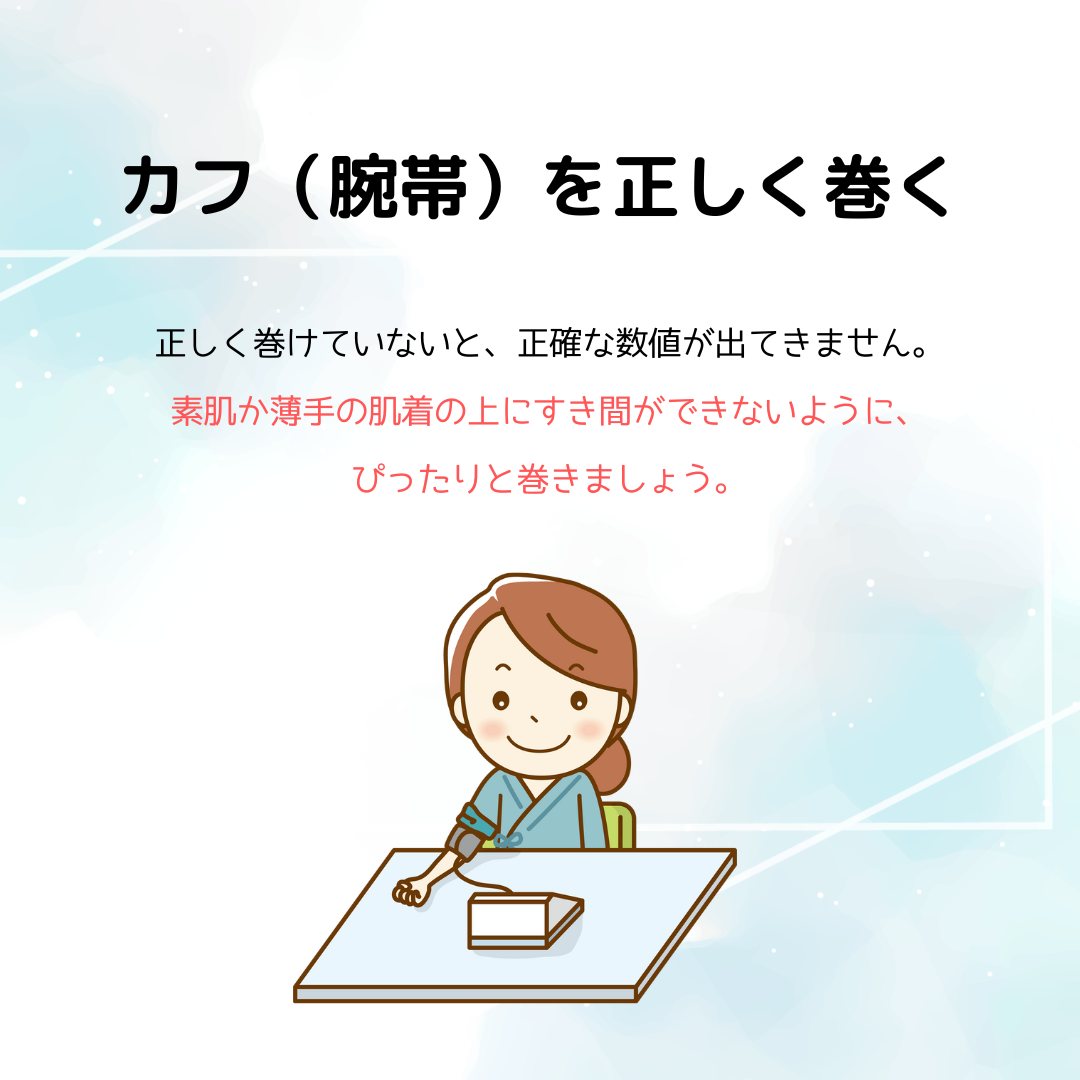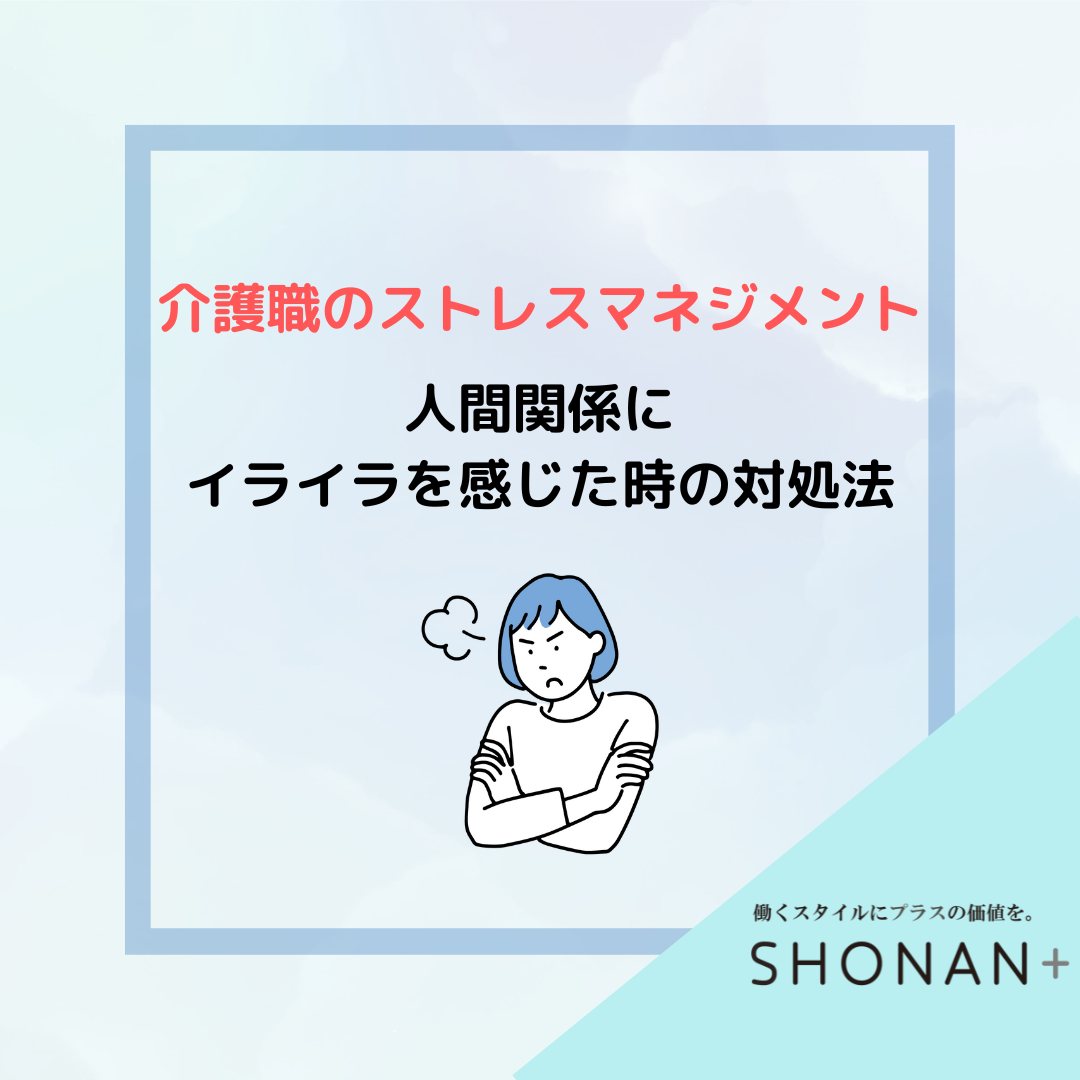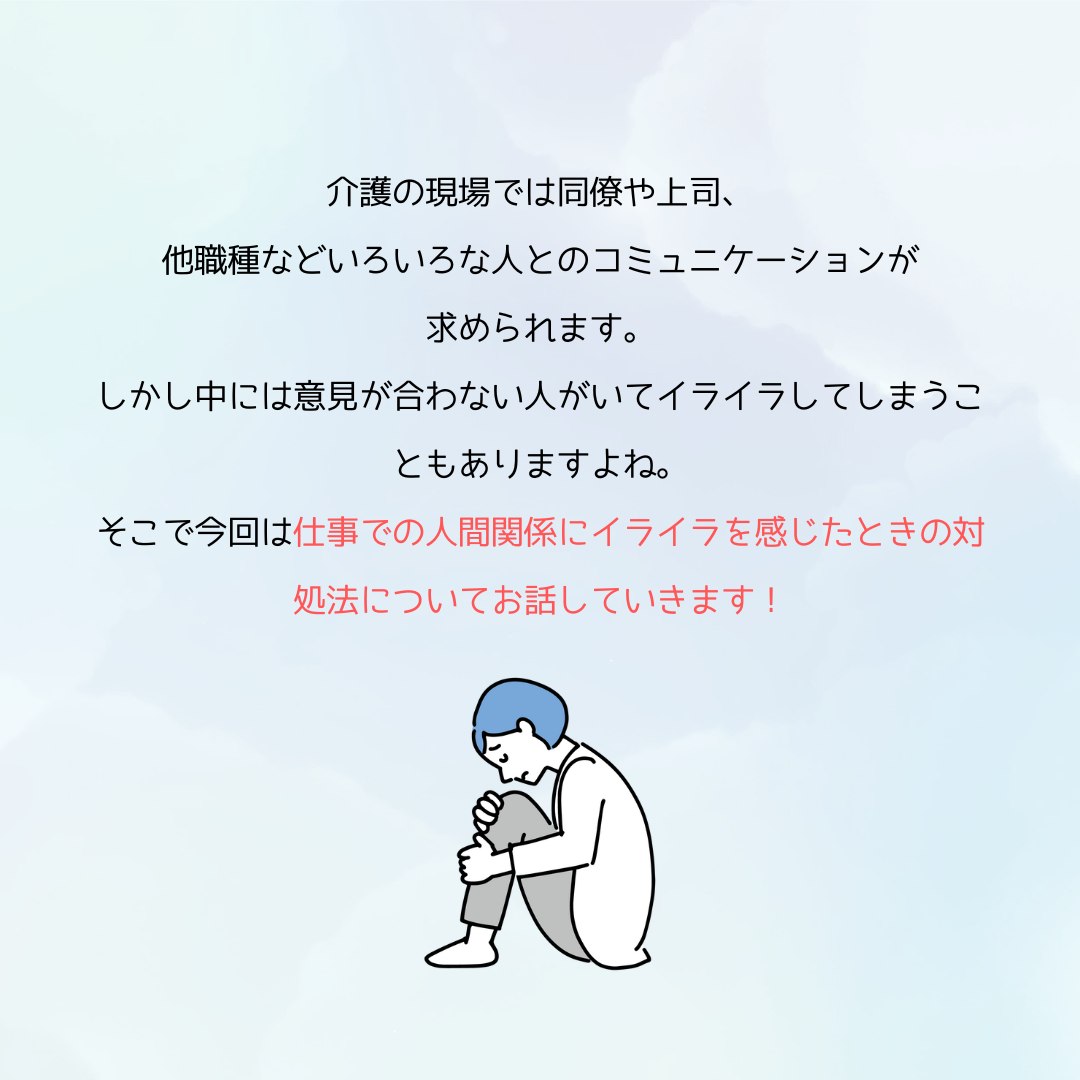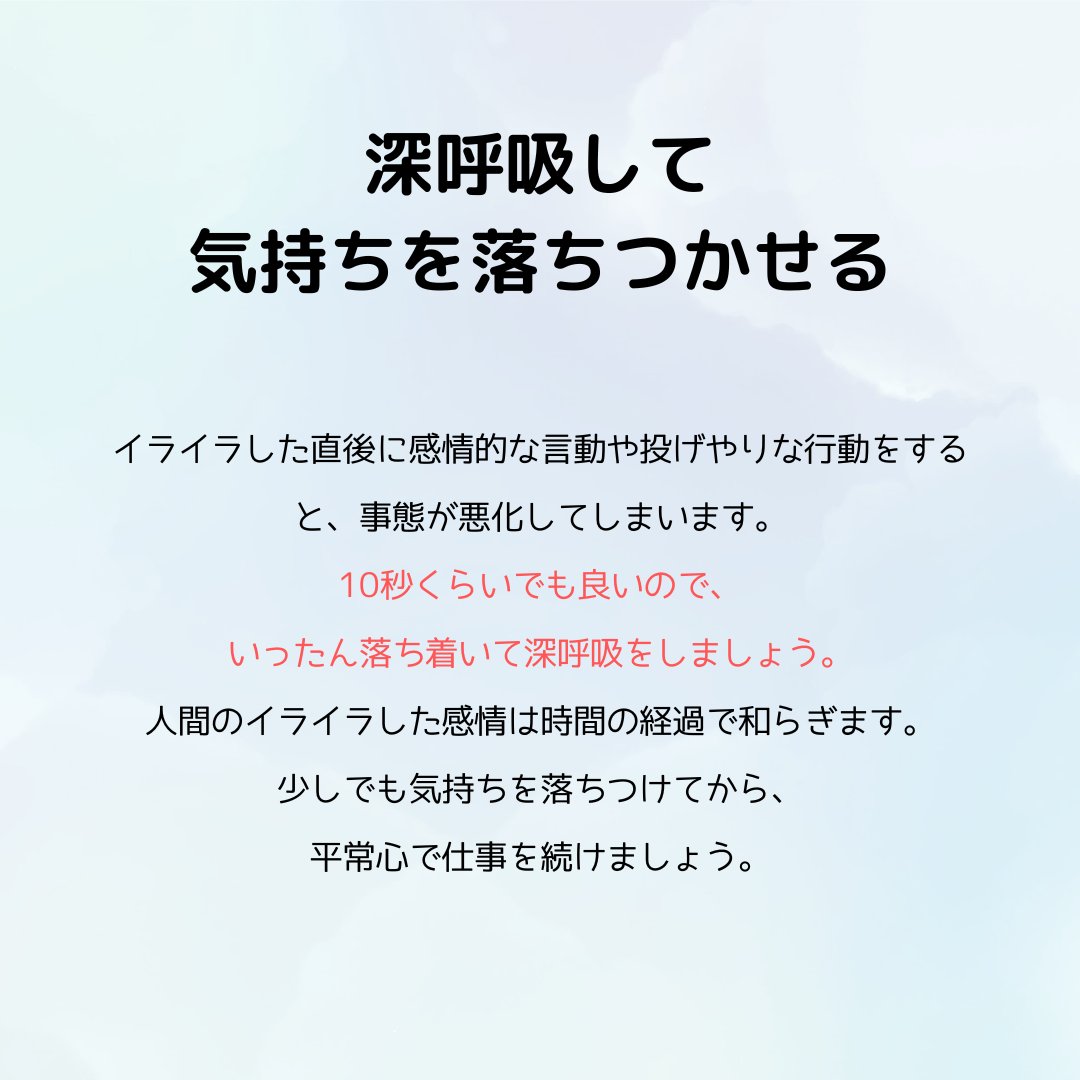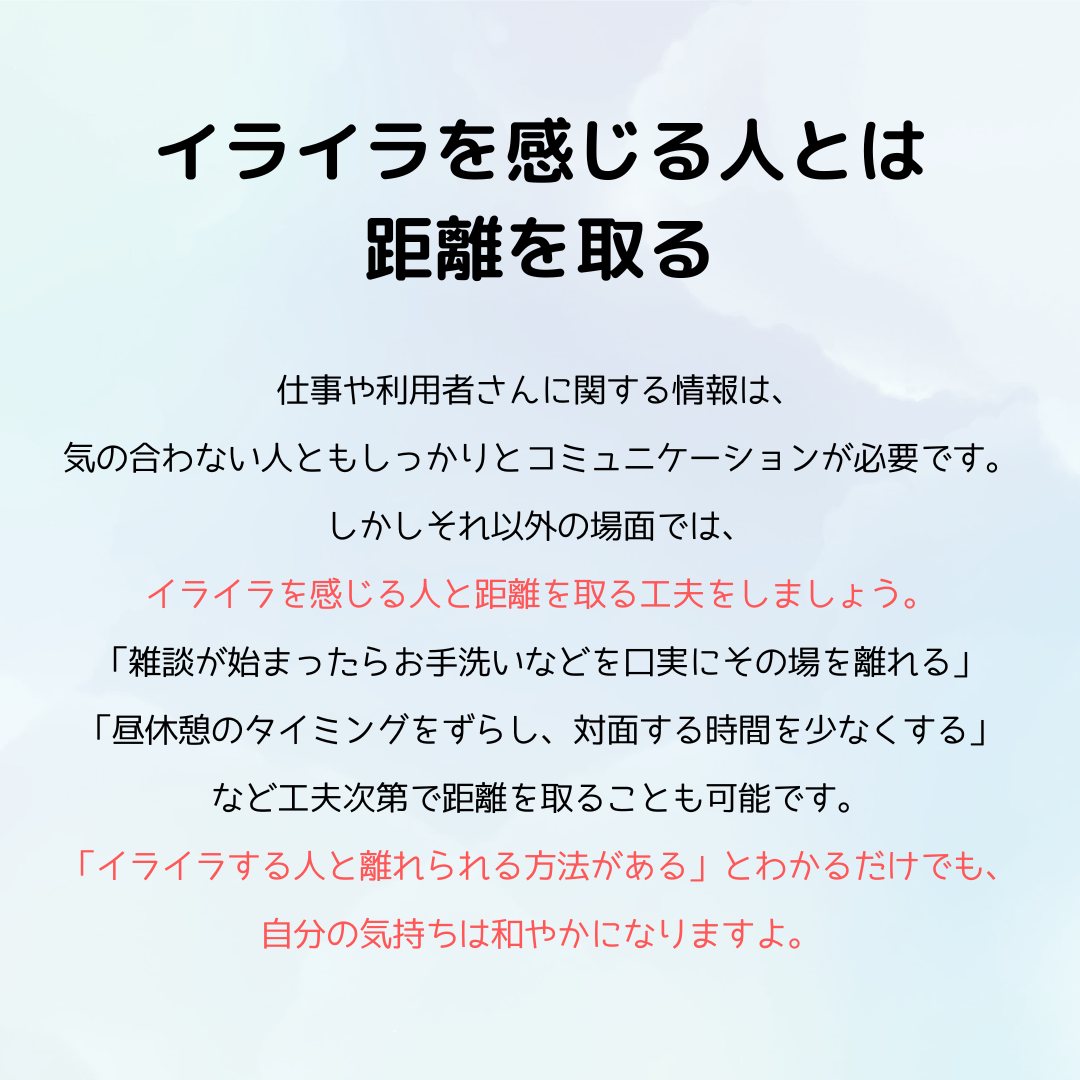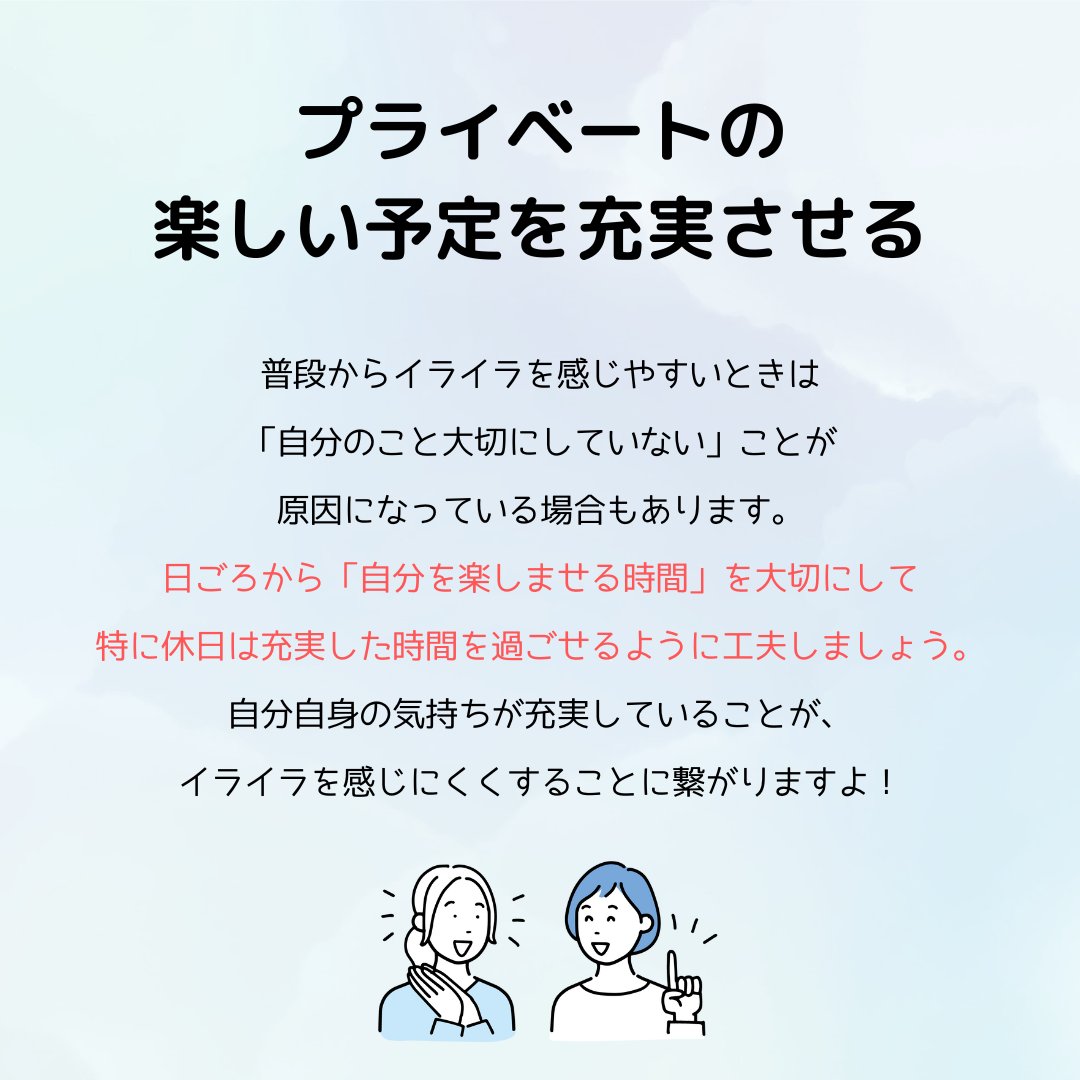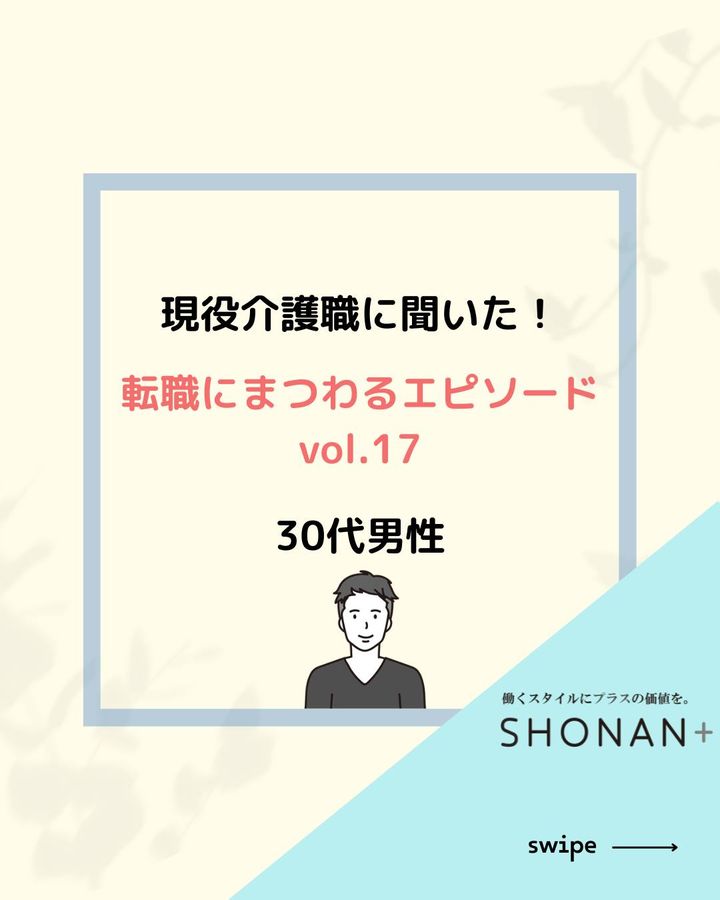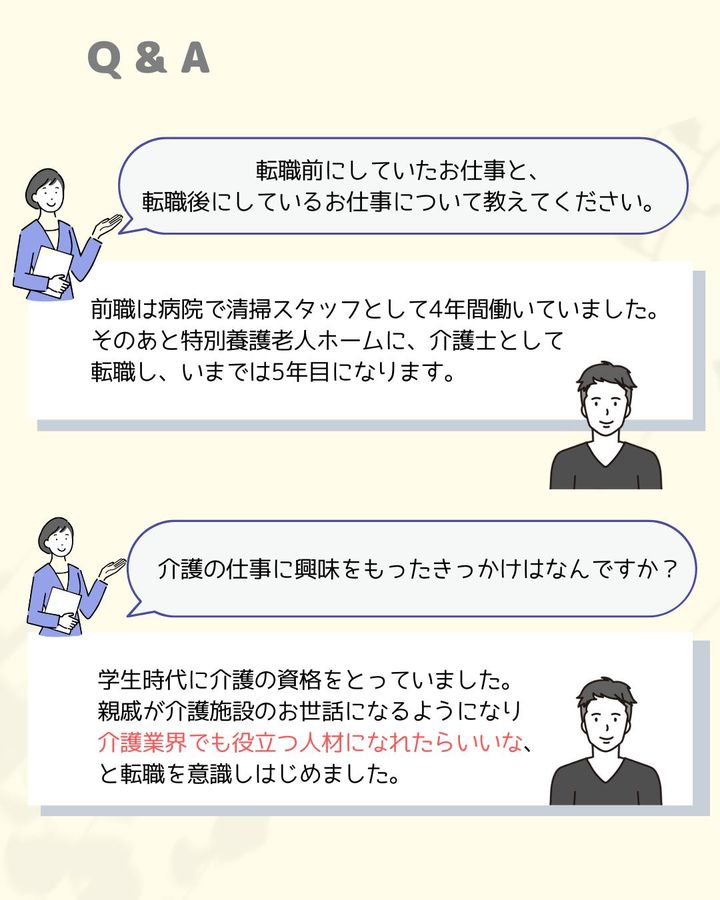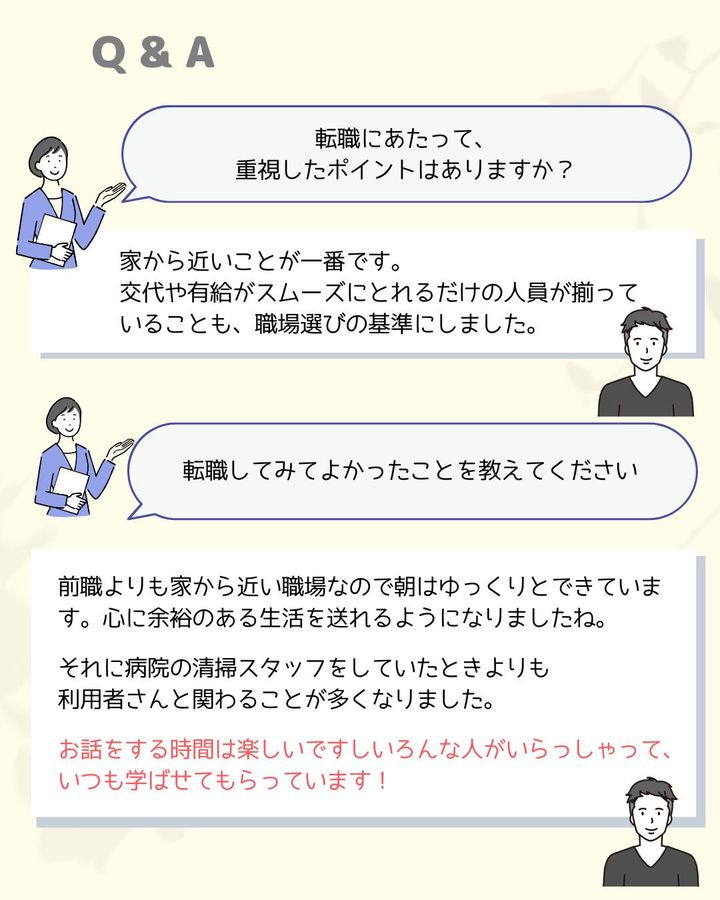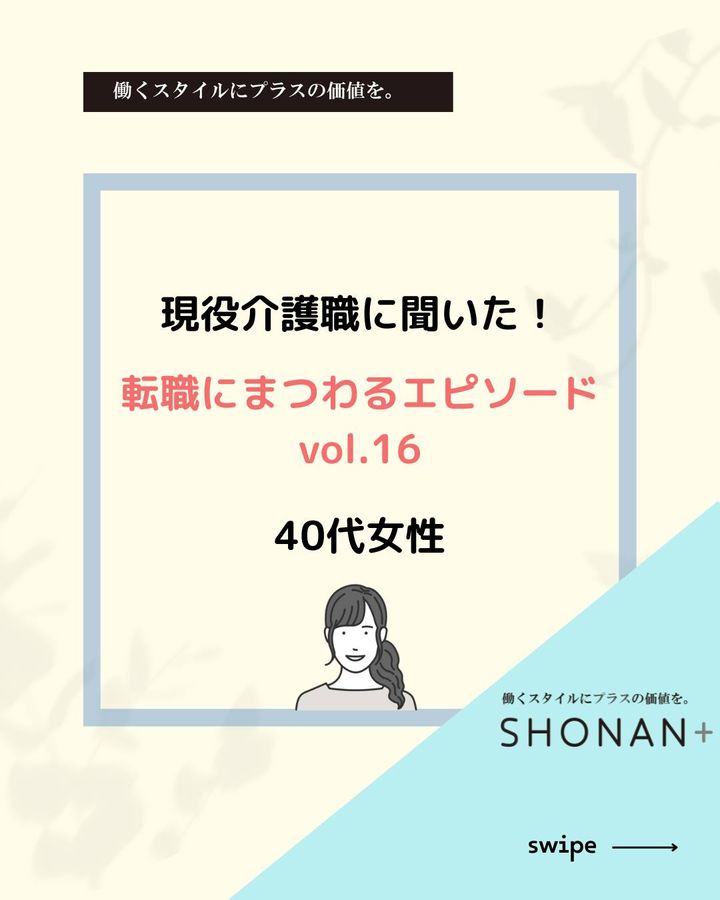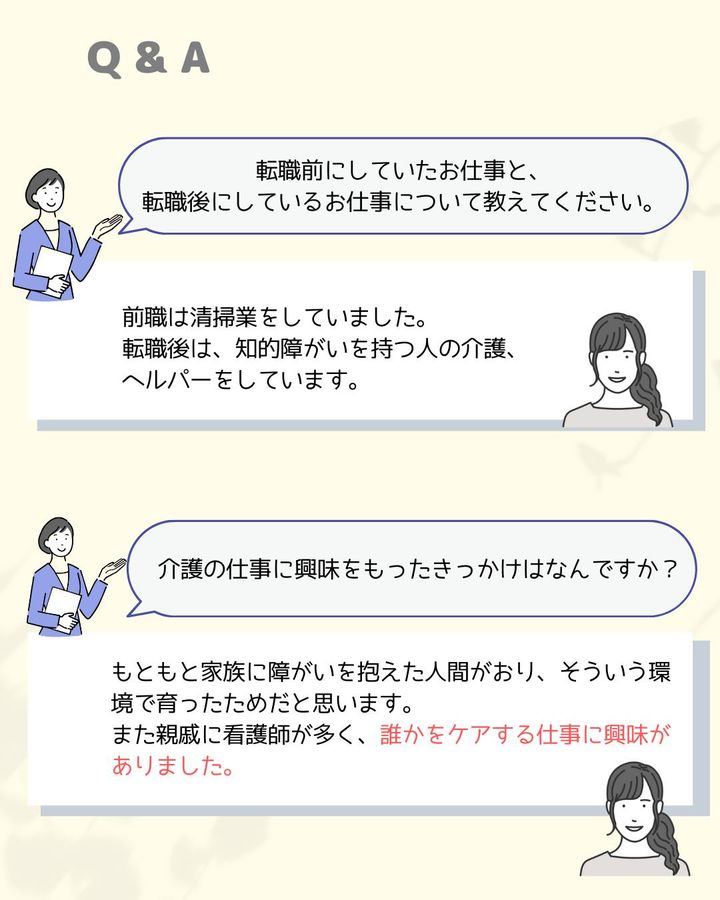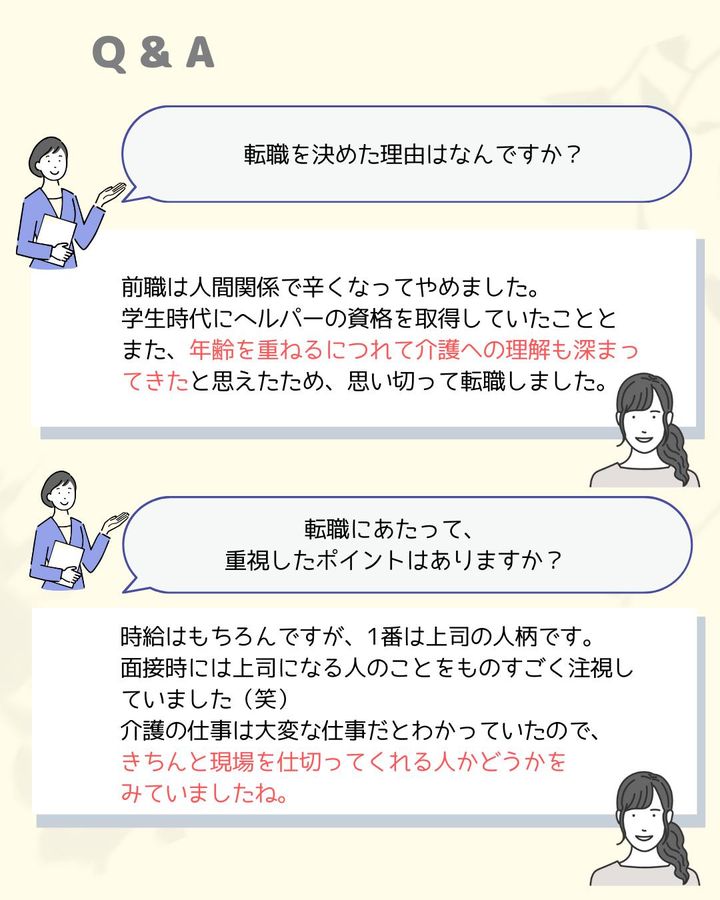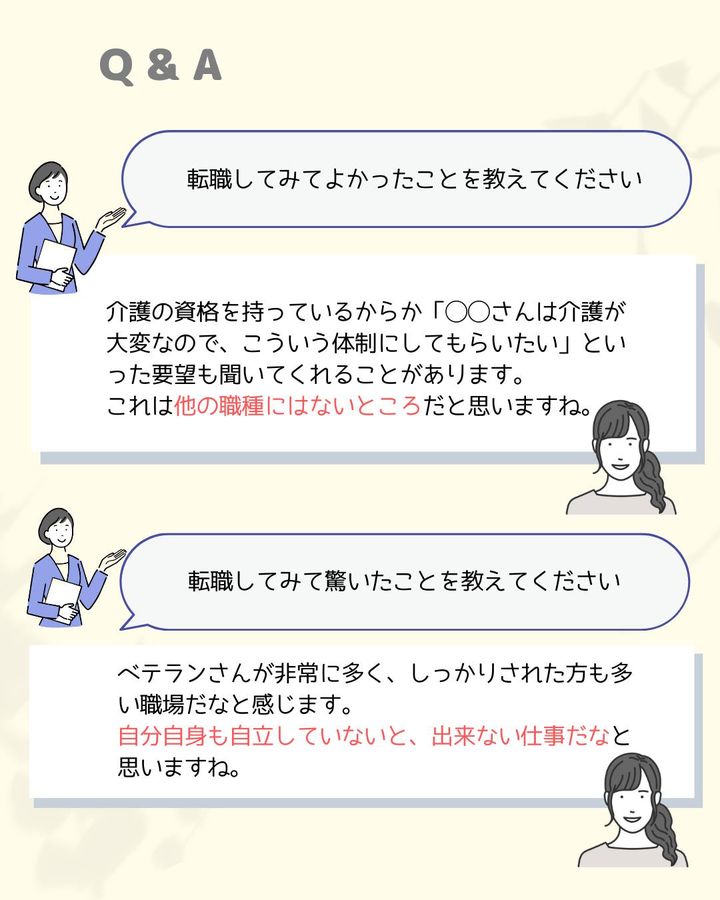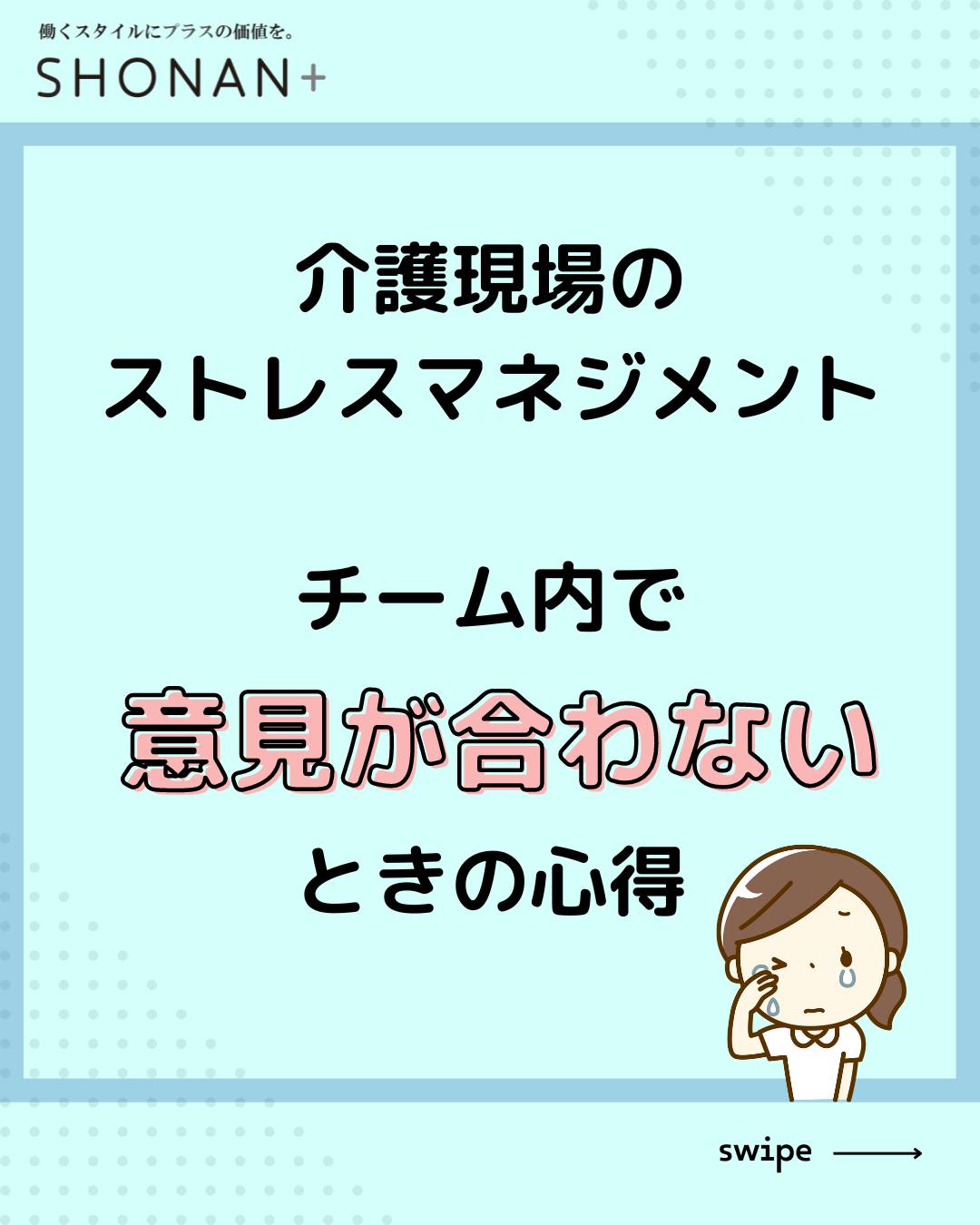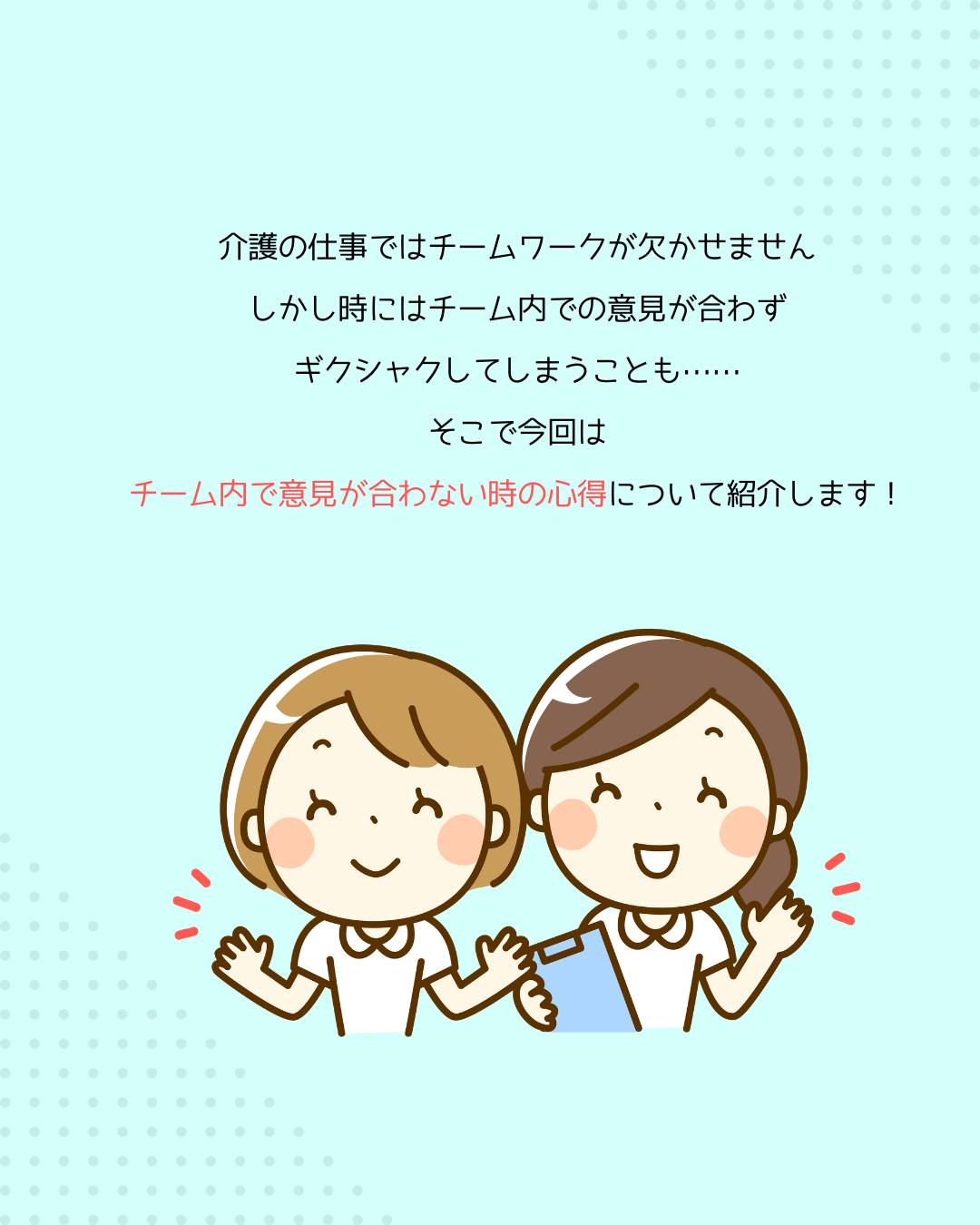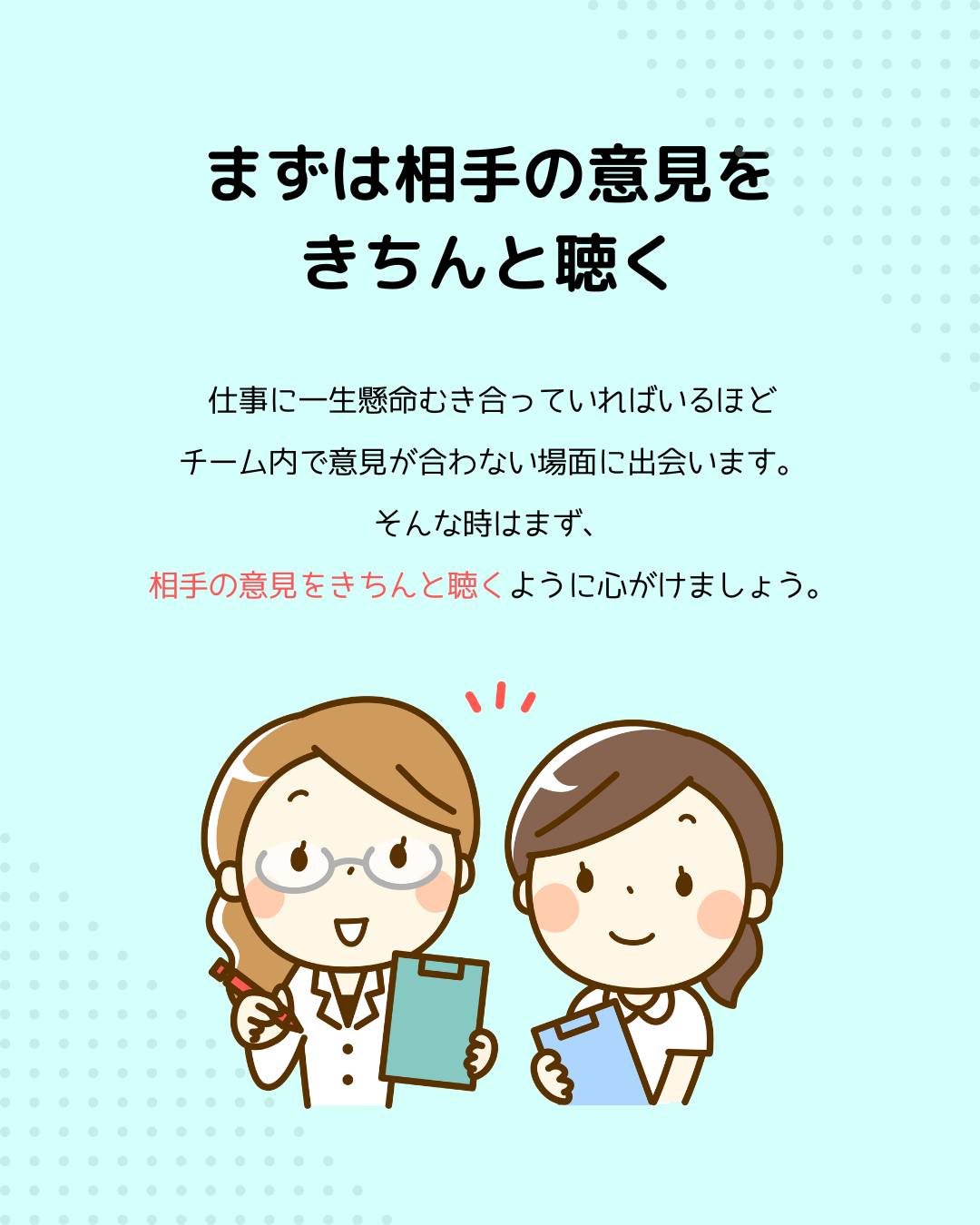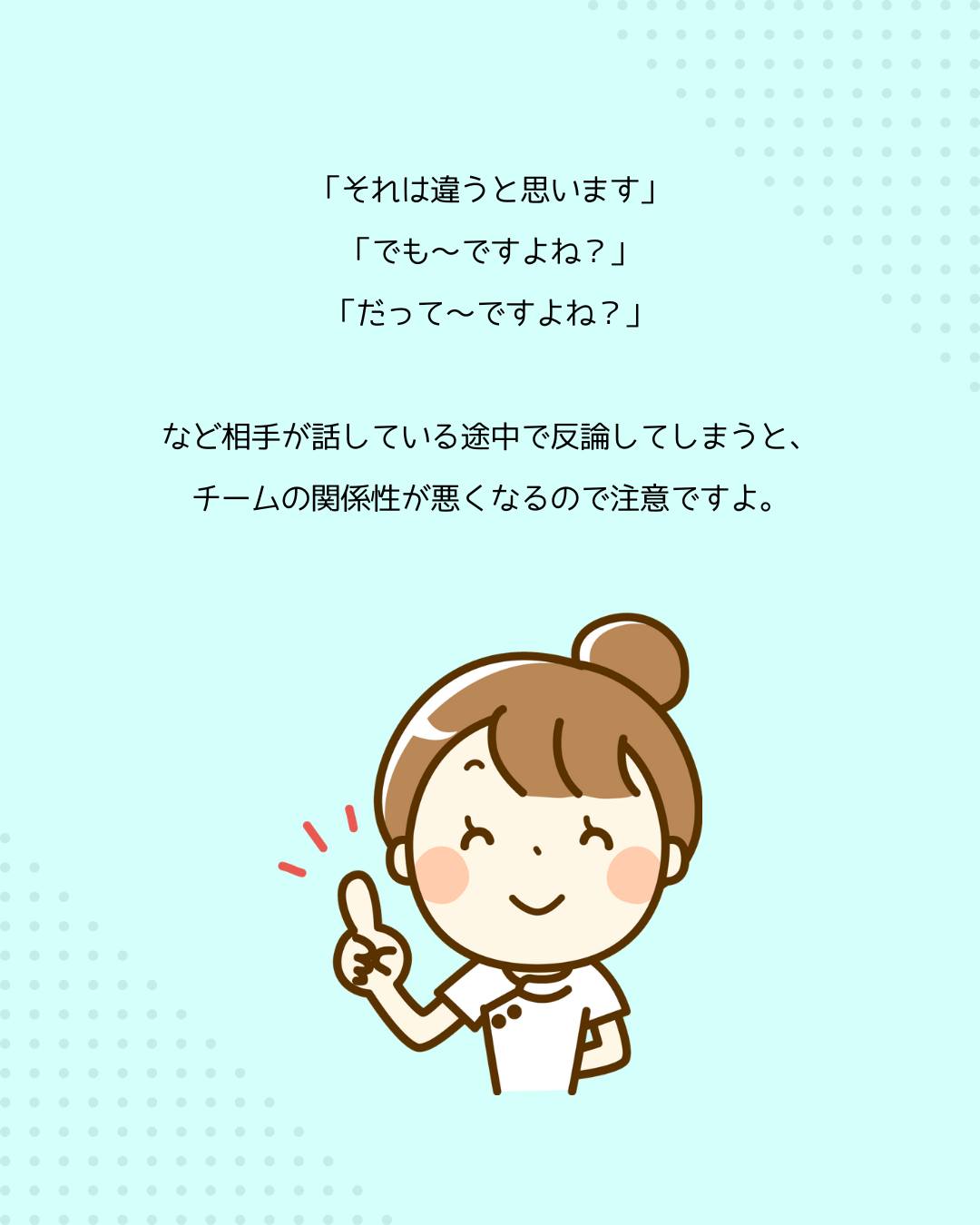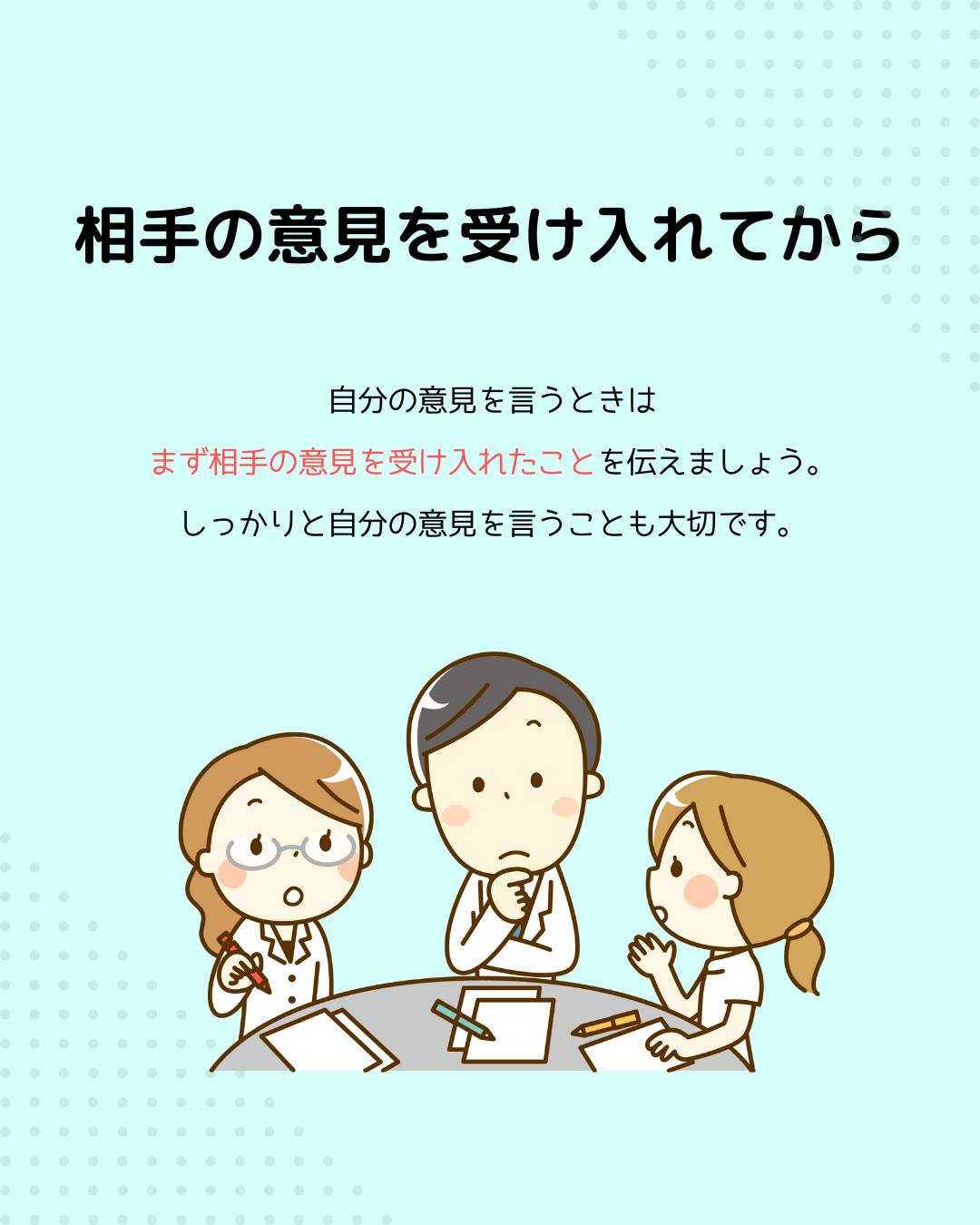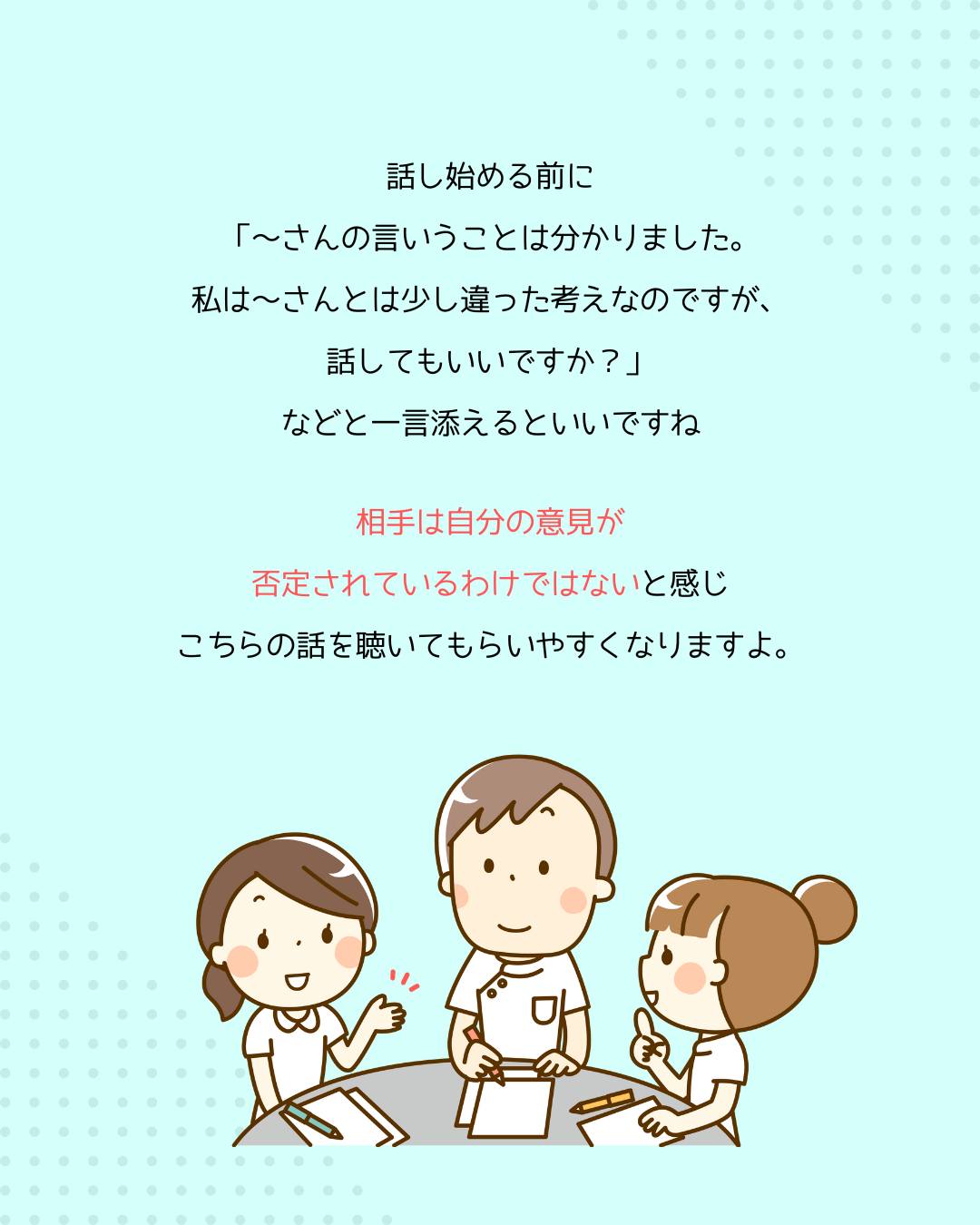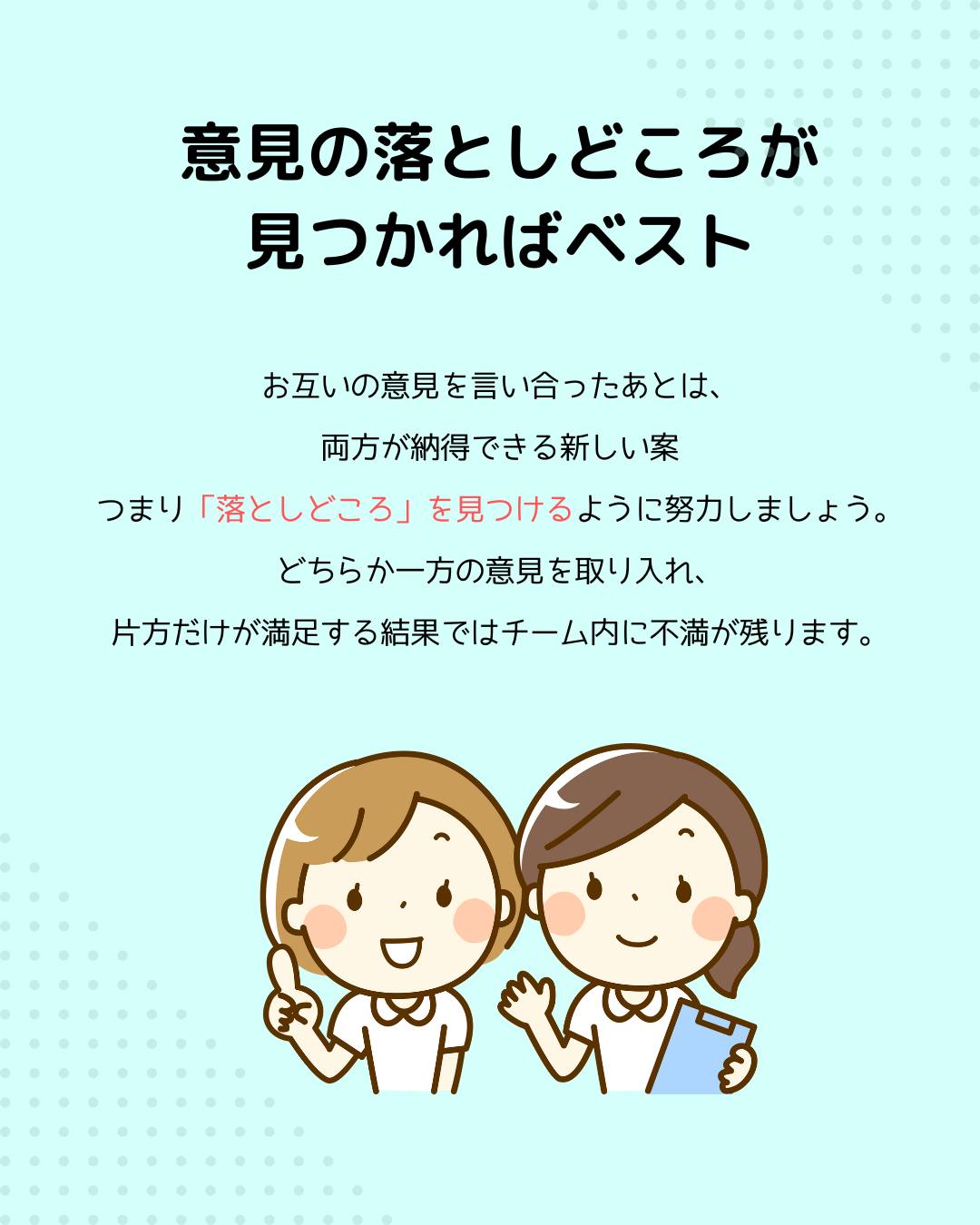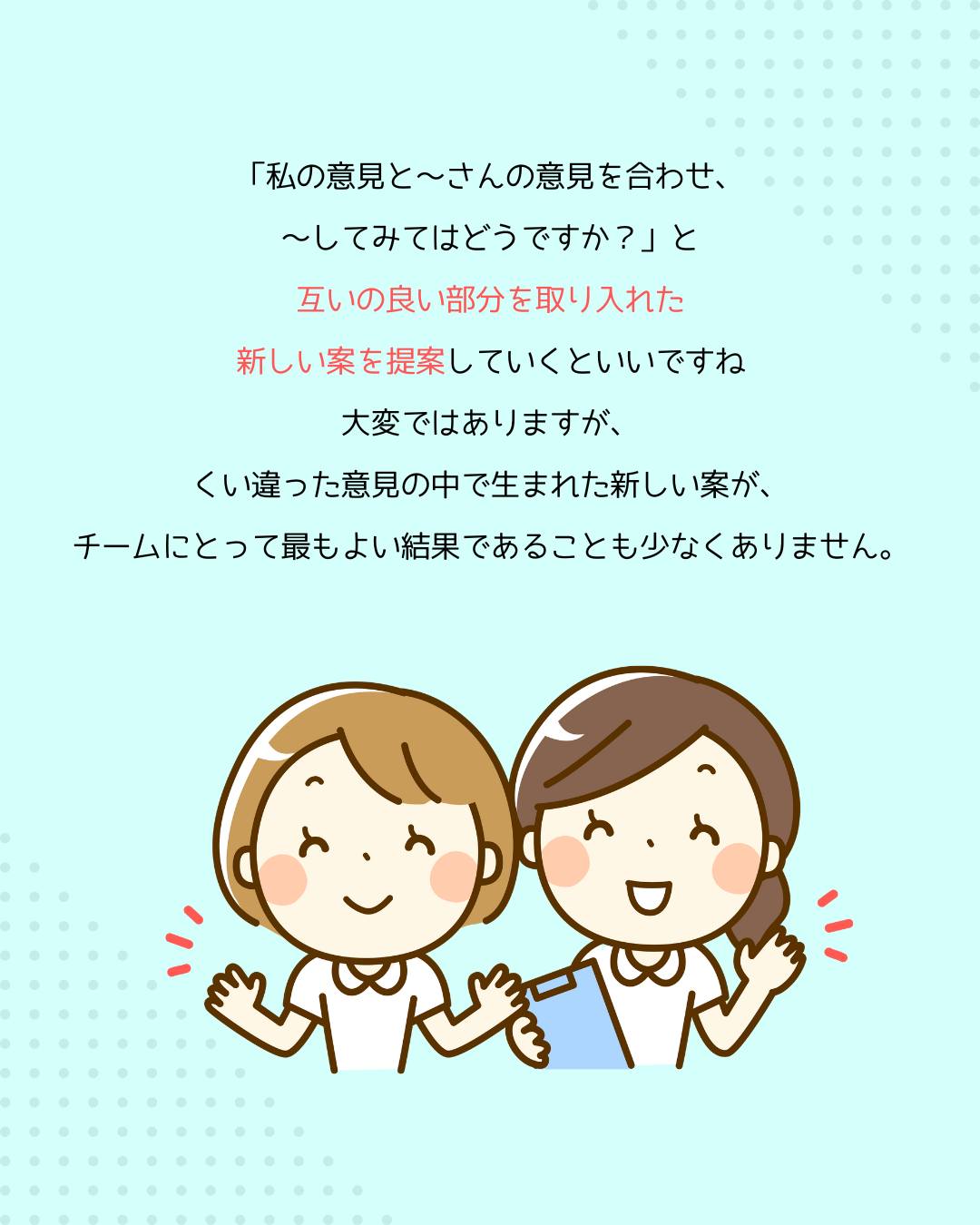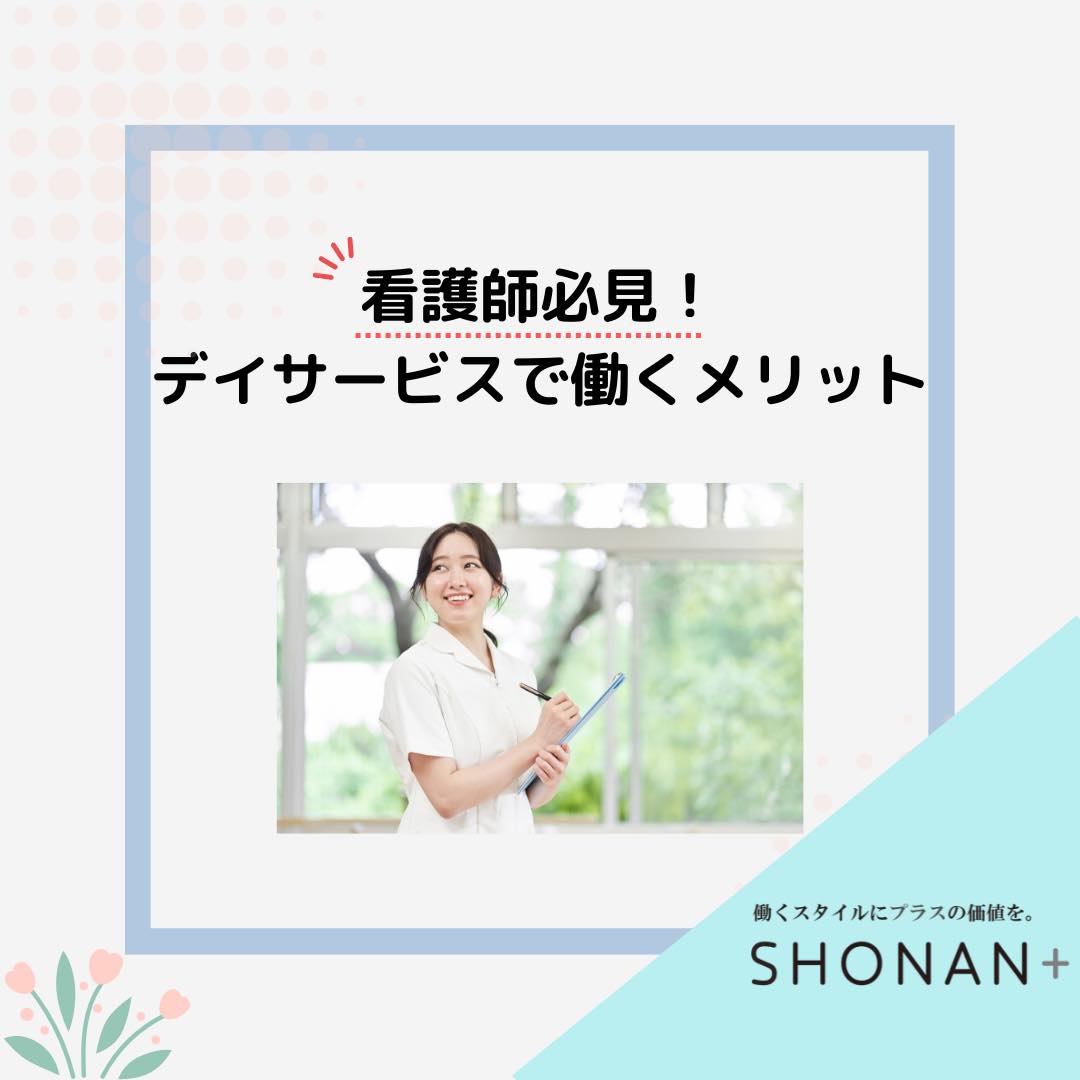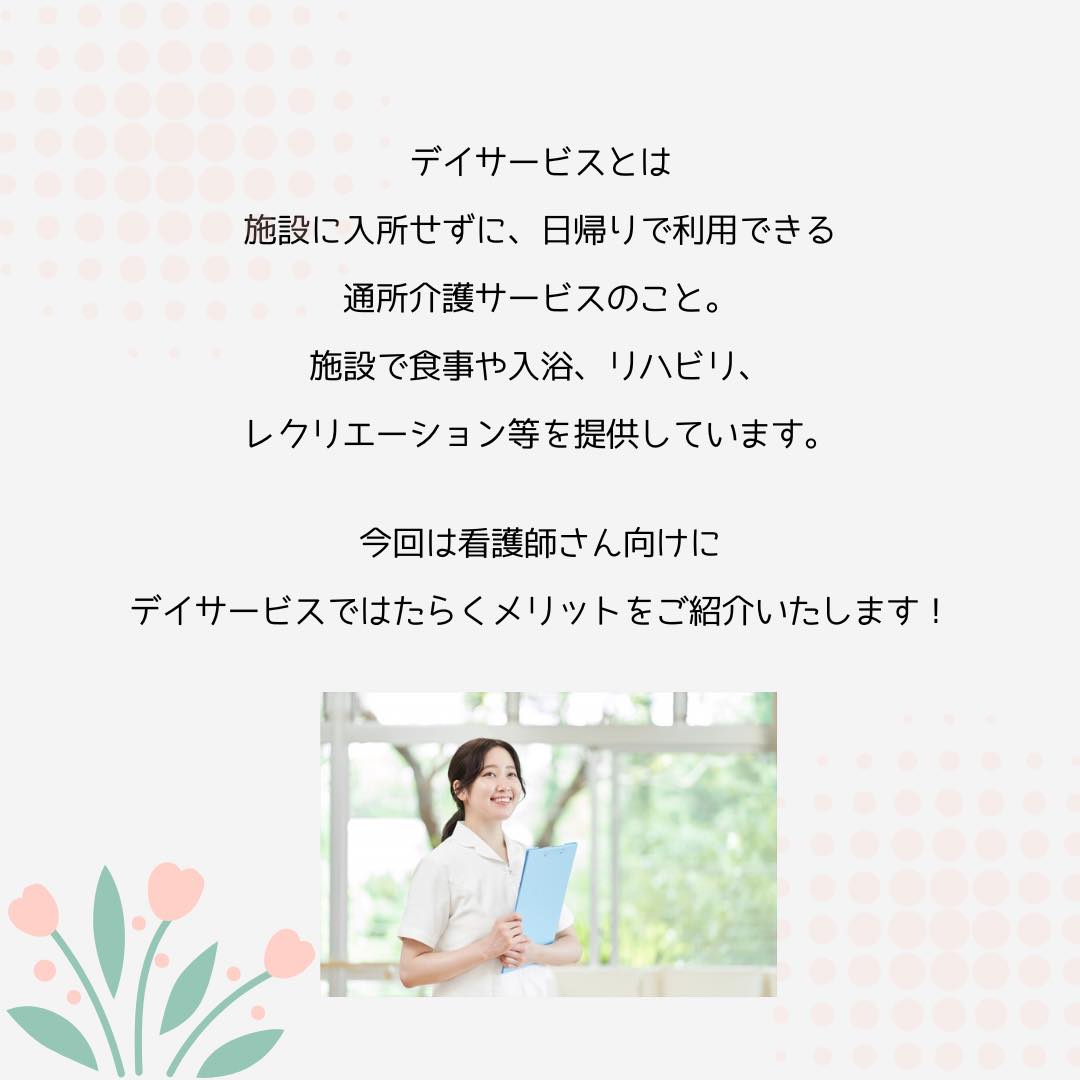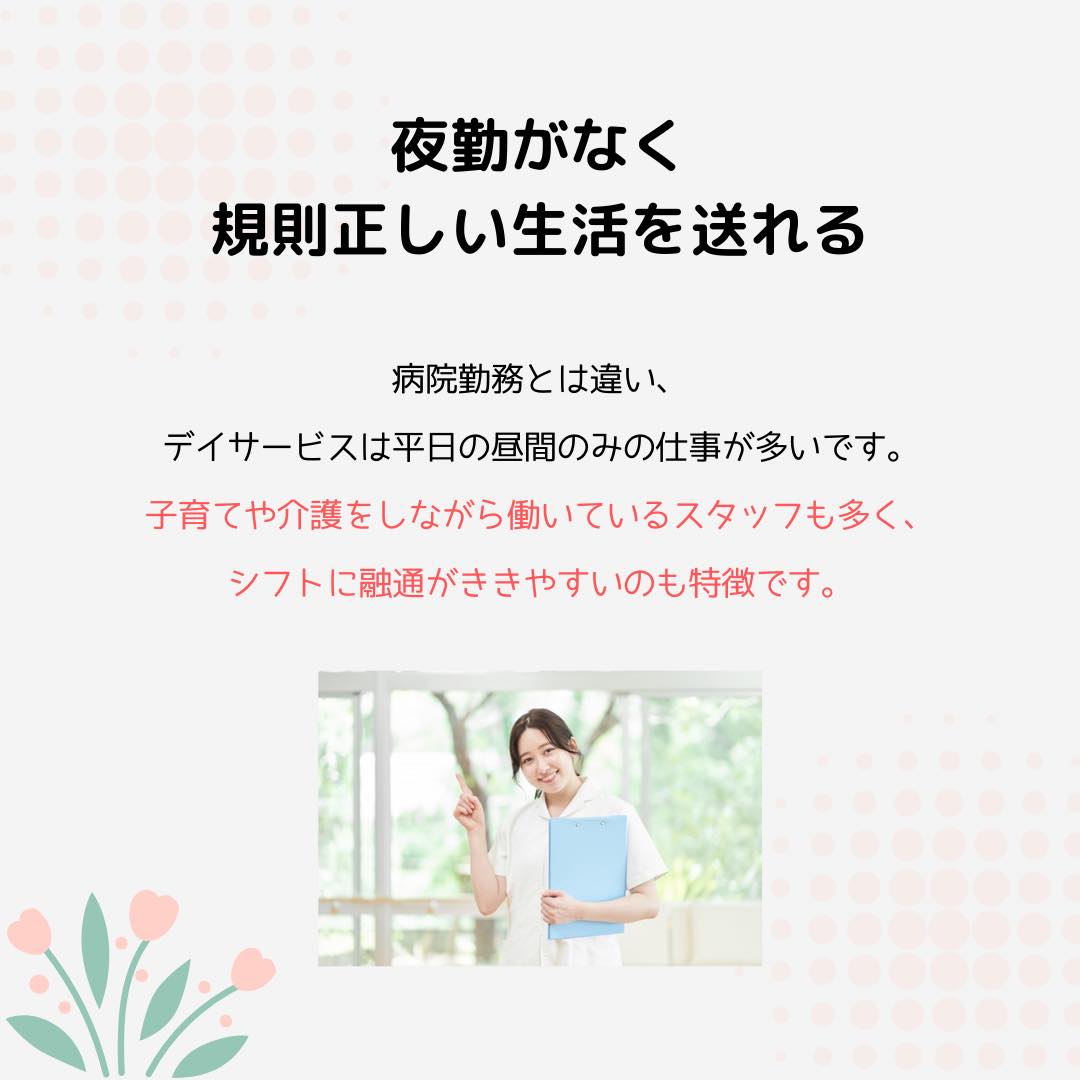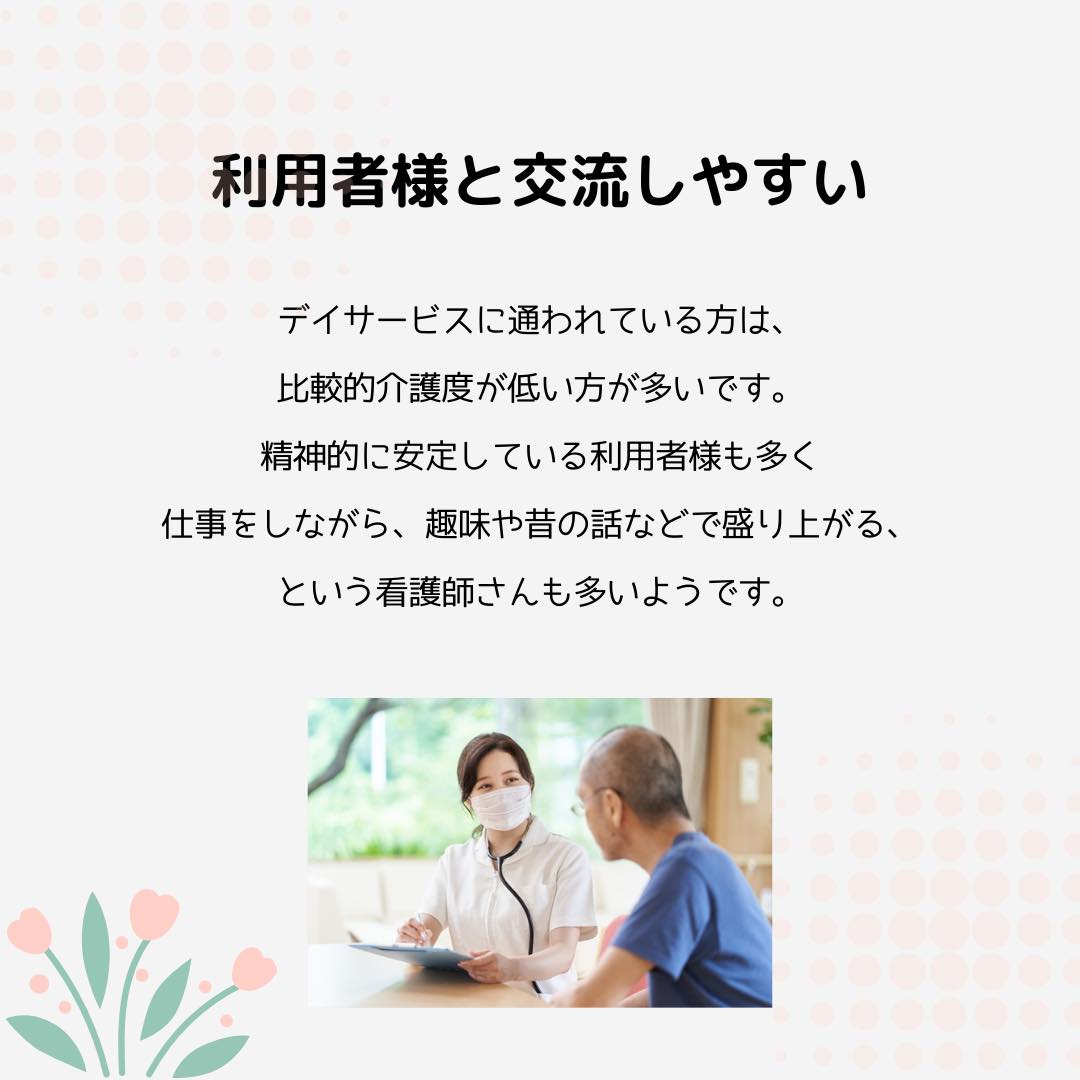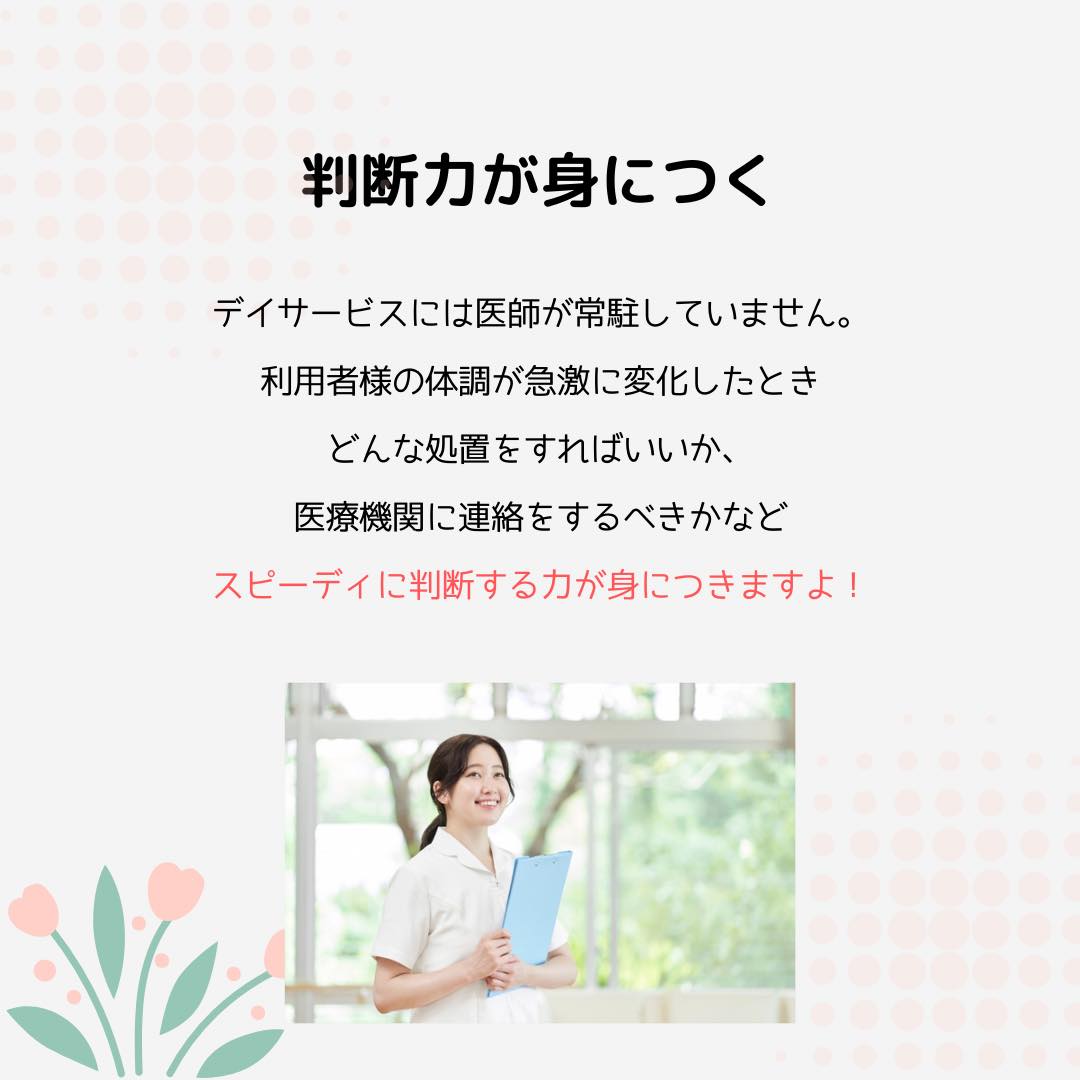掲載:2023.02.06現役看護師の 転職エピソードvol.2
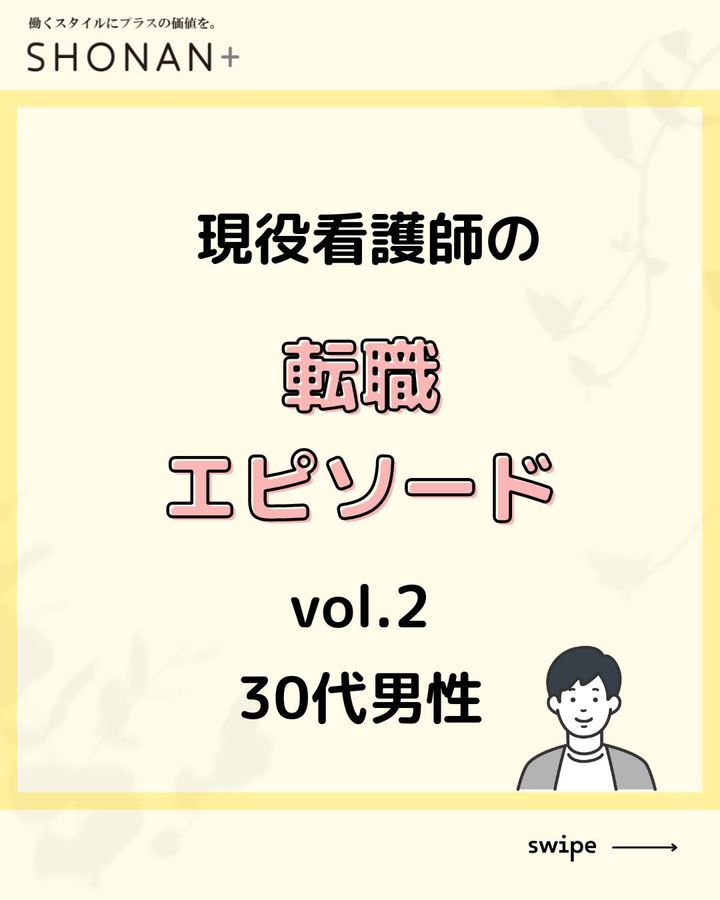
現役看護師の転職エピソードvol.2
30代男性
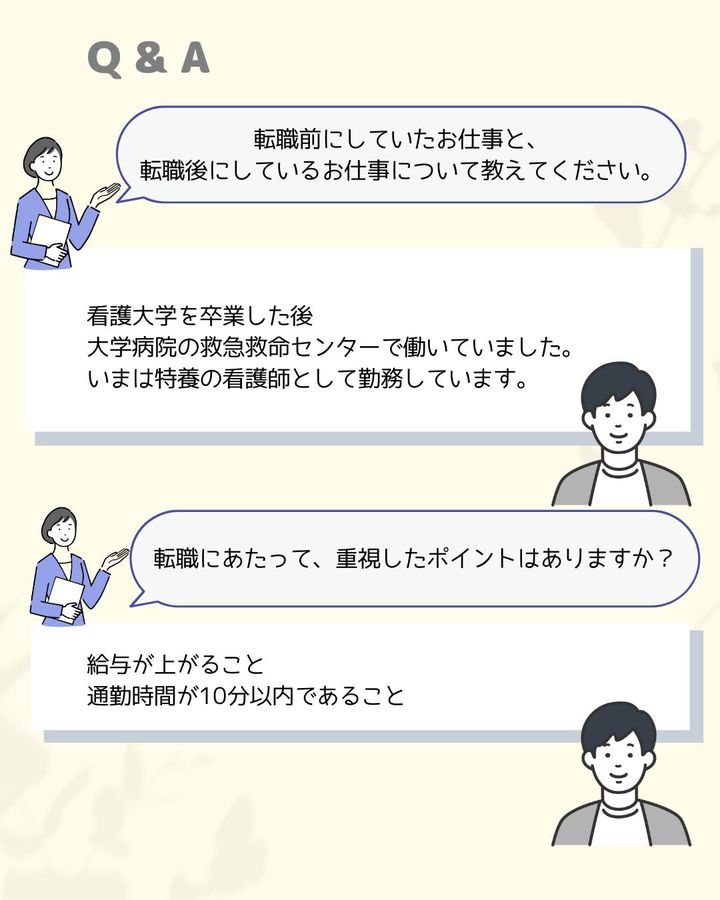
▼転職前にしていたお仕事と、転職後にしているお仕事について教えてください。
看護大学を卒業した後
大学病院の救急救命センターで働いていました。
いまは特養の看護師として勤務しています。
▼転職にあたって、重視したポイントはありますか?
給与が上がること
通勤時間が10分以内であること
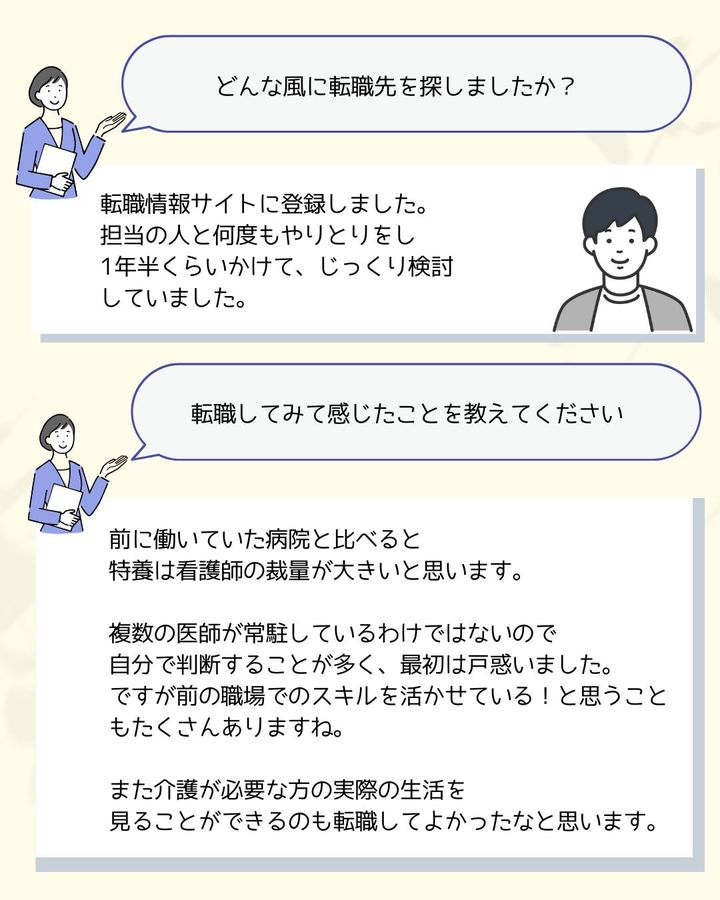
▼どんな風に転職先を探しましたか?
転職情報サイトに登録しました。
担当の人と何度もやりとりをし、
1年半くらいかけて、じっくり検討していました。
▼転職してみて感じたことを教えてください
前に働いていた病院と比べると
特養は看護師の裁量が大きいと思います。
複数の医師が常駐しているわけではないので
自分で判断することが多く、最初は戸惑いました。
ですが前の職場でのスキルを活かせている!と思うこともたくさんありますね。
また介護が必要な方の実際の生活を見ることができるのも
転職してよかったなと思います。

SHONAN+(湘南プラス)は【永久無料】であなたの転職をサポートいたします。
藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、鎌倉市などの湘南エリアと、横浜エリアの転職に強いSHONAN+(湘南プラス)は、医療・福祉・介護を専門とした人材紹介会社です。
一般公開されない[非公開案件]も含めたお仕事情報を、随時3000件以上保有しており、その中からご希望のお仕事を、忙しいあなたに代わって慎重に探し、内定・就労までの道のりを全てバックアップし、あなたを「希望通りの転職」へと導きます。
▼SHONAN+で現在募集している看護の求人情報
-
無料WEB登録はこちら
必要事項を入力するだけで簡単・仮登録!
数多くのお仕事の提案を受けながら就職活動を始めましょう。
-
お仕事情報メール配信サービスこちら
メールアドレスと希望条件を入力するだ。
SHONAN+から新着のお仕事情報をメール配信いたします。